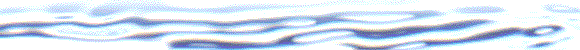はうぅっ、はうっ、ああっ、先生っ、っちゃいそうっ」
「まだだよ、我慢しなさい」
「だめぇっ、ああっ、そんなにされたら、ああんっ、我慢できないっ」
宏一は更にペースを上げた。肉棒が肉壁の中で強く擦り上げられ、二人の中に最高の快感を生み出している。
「先生、もうだめ、あああっ、あぁぁぁーっ」
「洋恵ちゃん、出すよ、出すよ」
「早くぅっ、ああぁぁっ、もうだめぇーっ」
我慢の限界を超えた洋恵が一瞬早く達した。その締め付けで宏一も最後の時を迎える。今まで何度も焦らされていた肉棒は、グッと傘を大きく開くと今まで堪っていた精を一気に少女の中に吐き出した。ドクッドクッと濃い液体が少女の中を満たしていく。肉棒の傘が大きく張りだしたことで、今達したばかりの洋恵が再度絶頂を迎えた。
「はうぅ・ううぅ・・・うううぅぅううぅーーーっ」
洋恵の肉壁が強烈に締め上げ、固く刺さっている肉棒から精を無理やり搾り取る。
「おおっ、ううぅっ、くっ」
宏一は放出直後で敏感になっている肉棒を無理やり締め上げられて声を上げた。しかし、直ぐに洋恵をもっと感じようと更に肉棒を深く押し込む。
「うぐぅぅーーっ」
更に声にならない熱い息を吐いて仰け反り突き上げられた洋恵の乳房を揉み上げて唇を奪う。洋恵は上手く対応できずに歯を食いしばって快感に耐えているだけだった。バチバチバチッと洋恵の頭の中は電気がショートしたみたいに火花が散って何がなんだかよく分からなくなった。ただ、気持ち良いと言うことだけしか頭になかった。洋恵はどこかに落ちていきそうで、飛んでいきそうな不安感から両手と両足で宏一に抱きつき、
「うぁぁぁっ、いやぁぁぁぁーっ」
と声を上げた。洋恵には宏一の肉棒が身体の中心に刺さって快感を生み出していることだけがはっきり分かっていた。最高だった。今までの中で最高の絶頂だった。
「うぅぅっ、ううぅっ、ううぅーっ」
洋恵は入り口がびくんと痙攣する度に更に快感が身体の中を走り抜け、それをしっかりと楽しもうと宏一にしがみついて結合を解こうとしなかった。しかし、洋恵の中に刺さった肉棒は役目を終えるとゆっくりと硬度を失っていく。
「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ」
やがて洋恵の肉壁がびくんと痙攣し、締め付ける力がゆっくりと抜けていった。しかし洋恵の肉壁はそれを許さないかのようにザラザラと撫で上げている。このまましばらくすれば、再び肉棒は固さを取り戻すであろう事は明らかだった。『ここで止めないと家族が帰ってくる時間を過ぎてしまう』そう思った宏一は意志の力で肉棒を抜き去ることにした。
「洋恵ちゃん、最高だったよ」
そう言うと、宏一はゆっくりと肉棒を引き抜いていった。
「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、せ、・・先生・・・、はぁ、はぁ、ああんっ」
宏一の肉棒が抜き去られると、洋恵は全身の力が抜けてしまったようで、全く動くことができなかった。洋恵の中から出てきた肉棒は、既に固くなり始めていた。それを洋恵が名残惜しそうにじっと見つめている。
「気持ち良かった?」
洋恵は上手く話せないようで、唇を震わせながらうんうんと頷いている。宏一はそのまましばらく洋恵を抱き寄せて髪を撫でていたが、ふと時計を見ると既に9時をだいぶ回っている。
「ごめんよ、洋恵ちゃん、もう時間を過ぎてるよ。帰らなきゃ」
そう言うと、
「うん」
と小さな声が帰ってきた。
宏一はゆっくりとベッドから降りると、身支度を調えたが、その間洋恵は全く動かなかった。洋恵も起きあがって服を着なくてはいけなかったのだが、たっぷりと幸福感に満たされた身体はだるくて動かせそうになかった。そして宏一の支度が終わると、
「また今度ね」
と言って洋恵に優しくキスをして宏一は部屋を出て行った。
宏一が部屋を出て行っても、まだしばらくの間洋恵は満足感に浸っていた。洋恵は全身を使って宏一を愛し、また、身体の奥の奥まで愛されたという実感を持っていた。
そしてそれから十分ほどして洋恵がやっと身体を起こした時、洋恵は乱れたベッド、脱ぎ散らかされた服、そして身体の中から染み出す液体に気が付いた。しばらくの間じっとそれらを見ていた洋恵は、最初は宏一に抱かれるつもりが全くなかったことを思い出した。正確に言えばその想いは抱かれている間にも心のどこかにずっとあったのだが、今まで宏一に与えられる快感がそれを覆い隠していた。しかし、今はその感覚も次第に薄れ、現実が洋恵の目の前にある。
「う・・・うう・・・・」
洋恵は自分が泣き出したことに驚いたが、直ぐに悲しみがわっと心を満たした。
「うあぁぁ、ああっぁぁぁぁ、ああぁぁぁ」
『こんなことするつもりなんて無かったのに』『勉強しようって思ってたのに』心の中ではそんな言葉が渦巻いている。『悪い子だ』と言う宏一の言葉が心に突き刺さった。『悪い子なんかじゃない』心の中で叫び返してみる。
洋恵は涙をボロボロとこぼしながら乱れたベッドを直し、服を着た。
『あんなこと、したくなんて無かった。先生にあんなことされなきゃ、普通の女の子で居たのに。私、あんなことしたくなかった』洋恵の心の中では後悔ばかりが渦巻いていた。涙がポロポロと止め処なく流れ落ちる。『先生といると、私、悪い子になっちゃう。あんなことなんて・・・・』散らかった部屋を片づけながら洋恵はあることを心に決めた。『もう先生と一緒に居るのは嫌。私が普通に勉強したくても、先生は私を悪い子にしちゃう。もう先生と一緒に勉強するのは嫌』
そんなことは全く知らない宏一は、洋恵と予想以上に濃厚なセックスを楽しめたことに満足していた。本当に素晴らしい時間だった。宏一の頭の中では激しく悶えながら声を上げる洋恵の姿が繰り返しフラッシュバックし、これから洋恵と過ごす時間がどんなものになっていくのか、そればかり気になっていた。
しかし、宏一が部屋に帰ると洋恵の両親から留守電が入っており、直ぐに電話が欲しいという。そして電話をすると激しい調子で責められた。どうやら洋恵は宏一が帰ったあと、ずっと泣き続けていたらしい。両親が帰ってきても泣きやまなかったので、両親は洋恵を問いつめたようだ。洋恵は宏一に抱かれたとことは話さなかったようだが、両親は洋恵のただならぬ雰囲気に宏一に何かされたと思ったらしい。とにかくもう来ないで欲しい、今日までのお金は送るから、と強い調子で言われ、洋恵の家庭教師を首になった。
宏一は突然のことに唖然とした。いつかは親に知れてしまうことなのかも知れなかったが、いきなりのことでショックが大きかった。ほんの1時間ほど前まで宏一の肉棒を受け入れて声を上げていた少女が突然いなくなってしまったのだ。宏一は洋恵を本当に可愛らしく思っていた。由美に対する感情とは全く違うものだったが、洋恵の身体はずっと前からじっくりと時間をかけて開発してきたのだ。初体験を既に済ませていた由美とは異なり、生まれて最初の快感を宏一が与え、一つずつ丁寧に教え、開発してきたのだ。宏一の頭の中では、まだ乳房を触られてもなんにも感じなかった頃の洋恵が『先生ったら、エッチなんだからぁ』と恥ずかしそうにはにかみながら身体を預けてきた時の姿が浮かんでいた。洋恵の乳房を初めて露わにした時に、宏一の目の前にそっと差し出された淡い色の乳首、まだ子供っぽさの残る薄い茂み、そして外見からは想像できない液体に濡れる秘唇、力強く扱き上げる肉壁、それらが一瞬にして遠くに行ってしまった。あれだけ丁寧に時間をかけて宏一好みに教えてきた少女に、もう会うことはできない。あの乳房を揉み上げられて悶える姿を見ることはできない、肉棒をおねだりする恥ずかしそうな表情を見ることができない、肉棒に激しく悶える全裸の少女を見ることができない、そう思うだけでやりきれない気持ちになる。そして何より、洋恵に必要とされていない自分が悲しかった。
『もう洋恵に会えない』と思うと、心の中にぽっかり穴が開いたみたいな寂しい気持ちになった。
翌日は土曜日だったが、工事予定が遅れているので宏一は会社に出なくてはいけなかった。本当は無理をすれば休めないこともなかったのだが、洋恵に会えなくなってしまったことがショックで、部屋にいても気持ちを切り替えられないと思い、やはり予定通り出てくることにしたのだ。昨日の夕方は友絵も出てくると言い張ったのだが、それではあまりに可愛そうなので今日は宏一しか出てきてはいない。9時を回るといつもと同じ忙しい時間が過ぎていったが、やはり休日はどこか平日と違う雰囲気がある。もともと土曜日には工事予定が無く、いくつか遅れている工事を予定の所まで進めるのが休日工事の目的なので、今日は予定表に追われる心配もなく、精神的にはだいぶ楽だった。十時頃、友絵から連絡が入った。
「三谷さん、どうですか?」
友絵は宏一が会社にいるので名字で話しかけてきた。
「ああ、今日は何の問題もなく順調に進んでいるよ」
「良かった。カテゴリー6のケーブル、入ってきました?」
「うん、さっき届いた」
「良かった」
「うん、本当だよ。これで更にトラブったら目も当てられない」
「そうですね」
友絵の声の調子はどこか考え込んでいるような、少し慎重な感じだった。工事の進み具合を心配しているのかと思った宏一は、
「だから今日は順調だよ。心配してくれてありがとう。今日中に何とかなりそうだし、もう俺がいなくても良いみたいだ」
と友絵が出てこなくてもいいように万事順調であることを強調した。
「三谷さん、今日は何時頃終わりそうですか?」
「う〜ん、早いよ。昼時には終わるんじゃないかな?どうして?」
「良かったら会いたいな・・・なんて・・・」
「会いたい?」
宏一は一瞬言葉に詰まった。毎日顔をつきあわせている友絵の言葉とは思えなかったのだ。
「嘘です。毎日会ってるんだもの」
「そりゃそうだけど・・・」
「良かったら夕食にでも出かけようか?」
「大丈夫です。そんなに三谷さんに付き合わせたらバチが当たりますよ」
「何言ってるの。6時に川崎駅で会わない?」
「本当にいいんです。また月曜日に会いましょう」
「そうなの?俺はいいのに」
「ごめんなさい。変なこと言って」
「ううん、いつでも連絡頂戴ね」
「はい、ありがとうございます」
「それじゃね」
「はい、月曜日に」
友絵は携帯を切ると、自分から言いだしておきながら宏一の誘いを受けられなかった自分に後悔していた。ただ、今でさえ十分に好きな宏一にこれ以上のめり込むと、二度と引き返せない道に入り込むような気がして少し怖かった。しかし同時に宏一を自分だけで独占したい、プライベートな時間も全て自分だけを見ていて欲しい、と言う気持ちも強くなっていた。でも、今日だけはやらなければいけないことがある。それでも、少しでも宏一と一緒にいる時間を持ちたかった。
宏一も電話を切ってから同じ様なことを考えていた。どうもすっきりしない。このまま忘れても良いのだろうが、宏一の心の中では小さな危険信号が点っていた。『もしかしたら嫌がられるかも知れないけど・・・』と想いながら再度友絵の携帯を鳴らした。
「もしもし?」
「宏一さん・・・・」
「友絵さん、どうしたの?なんか気になって。ちょっと会って話せない?」
宏一はいきなり用件を切り出した。こう言う時はごちゃごちゃ言っても意味がない。
「え・・・・・・・いいんですか?」
友絵も宏一の迫力に押されたのか、直ぐに承諾してくれた。
「もちろんだよ。いつも顔は見てるけど、なかなか二人でゆっくりと話なんて出来ないし」
「うん・・・・嬉しいな..そんな風に言ってもらえると」
「どうしたの?何かいつもと違う見たいだよ」
「会ってからにしませんか?」
「わかった。どこで待ち合わせる?」
「宏一さんは何時頃出てこれますか?」
「えーと、たぶんお昼前には出られるよ。これだけ順調なら、これ以上いても仕方ないし」
「ええと、それじゃ、ハチ公前で
12時でどうですか?」「わかった。ハチ公前で
12時だね?」「すぐに行きます」
すぐにと言っても、ハチ公前なら友絵の方が近いはずで、まだ
1時間以上ある。友絵の場所ならこれから準備に30分以上かけられるはずだが、女の子はいろいろとすることがあるのだろう。宏一はとりあえず渋谷に行ってから時間をつぶすことにしてまず移動することにした。
その途中、電話の今日の友絵の様子が少しおかしい事を気にしていた。何か言いたい様子だったが、言いにくいような、それでもやっぱり話したいことがあるような、そんな感じだった。考えて見れば2,3日前の仕事中にも週末の予定を尋ねられたような気がする。単に宏一と一緒に週末を過ごしたいと言うような甘い感じでは無い気がした。
友絵は時間に少し遅れて現れた。赤いベルトがアクセントになっているプレーンな感じの緑のワンピースで、友絵の魅力を素直に引き出している。
「ごめんなさい。少し遅れましたね」
「大丈夫。これくらいの遅れなんて工事の遅れに比べれば大したことないよ」
「ふふ、そんな事言うと共栄オプティックスの中村さんに言いつけますよ。あれだけ一生懸命調整してくれたのに」
「ごめん、それは許して。今あそこにつむじを曲げられたらお手上げになっちゃうじゃない」
「冗談ですよ」
「よかった。さて、お昼だよね。どこに行こうか?食べたいものはある?」
「お任せします」
「それじゃ、餃子なんてどう?近くにおいしい店があるよ。二人で食べれば気にならないだろ?」
「ご、ごめんなさい・・・・・。今日はあとで人と会う予定があるから・・・・」
それを聞いて宏一は少しがっかりした。今日は一日友絵とデートできると思っていたのだ。それだと、一緒に居られる時間はちょっとだけと言うことだ。
「そうか、それじゃ仕方ないね。洋食はどう?」
「はい、大好きです」
「決まりだね」
宏一は友絵を渋谷駅から東急沿いに少し歩いた明るい感じの小さなレストランに案内した。まだお昼を回ったばかりなのでそれほど混んでもおらず、何とか待たずに座ることができた。
「メニューの選択は任せてくれる?」
「はい、お願いします」
宏一は少しゆっくり話をしたかったので、オードブルとパスタを二人にひとつずつオーダーした。
「宏一さん、ムール貝のつぼ焼きって何ですか?」
「そのままだね。見れば判るよ。この店の定番メニューで結構人気があるんだ」
「ふうん、どんなのか楽しみにしてます」
それから二人は話し始めたが、友絵はいつまで経っても用件を言おうとしなかった。だから会話していても何となく気まずい雰囲気が流れる。宏一は思い切って聞いて見ることにした。
「ところで友絵さん、今日は何となく何時もと違う雰囲気何だけど、何か困ったことでもあったの?」
「あ・・・・、判っちゃったんですね・・・」
「そりゃ毎日会ってるんだもの、判るよ」
「そう・・・宏一さんには伝わっちゃうンだ・・・」
それから友絵はしばらく黙り込んでしまった。よほど言い難いことらしい。
「あの、無理して言わなくても・・」
「ダメです。そんな事言うと、また宏一さんに甘えちやうから」
「え?どういうこと?」
「ううん、なんでもありません。ちょっと気が重かったものだから・・・・」
「何か判らないけど、大変なことなんだね」
「そう・・・です・・・」
「それじゃ、聞かない方が良いのかな?」
「そんなことないけど・・・・」
どうも要領を得ない感じで、友絵も話して良いものかどうか迷っているみたいだ。少しの間黙っていた友絵だったが、ふっと顔を上げると話始めた。
「宏一さん、今日の夜また会ってもらえます?」
「夜?いいけど?」
「夕方に人に会ってくるんで、その後で会いたいんです。よかったら夕食をいっしょにしてもらえると嬉しいな・・・」
「わかった。そうしよう。場所は?」
「会うのが品川なんで、その辺りならどこでも」
「それじゃ、品川にしようか?」
「・・でも品川駅は・・・」
「それじゃ、大井町にしようか」
「いいですよ。でも、私はあんまり詳しくないけど・・・」
「大丈夫、JR側から東急への改札があるから西口にある東急の改札で待ち合わせよう」
「はい」
「何時が良い?」
「7時ごろになるかもしれない・・・」
「わかった。7時にしよう。でももし、友絵さんが遅れても必ず待ってるから安心してね」
「はい、私も宏一さんが遅れてもずっと待ってます・・・嬉しい.・・・私にそんなことまで。・・・」
友絵は目を少し赤くしてうつむいてしまった。
「本当ならちゃんと話さなきゃいけないのに、私は自分のことばっかり考えて」
「そんなに自分を責めるもんじゃないよ。誰にだって言いにくい事はあるんだから。さぁ、話は決まった。元気を出して食べようよ」
「はい」
友絵は元気を出して食べ始めた。
「ムール貝ってパスタと一緒に食べたことはあるけど、こんなの初めて」
「面白いだろ?」
「こうしてあるだけで楽しいですね」
友絵の心の中ではまだ複雑な気持ちが渦巻いていた。しかし、宏一が何も聞かずに友絵の心を気遣ってくれたことで、自分の心が宏一に更に大きく傾いていくのを感じていた。それはどうしようもない、と言うのと、心地よいのでもっと甘えたい、と言うのが半分ずつだった。
「美味しいお店ですね。宏一さんの知っているお店ってちょっと洒落てて楽しいお店ばっかりで、食事に誘ってもらえるのが楽しみになっちゃう」
「友絵さんもお世辞を言うのが上手くなったね」
「お世辞?私、お世辞は言いません。正直な気持ちですよ」
「そうか、それなら夕食はがんばらないとね」
「あ、そんな高いお店じゃなくていいんです。一緒に食事できれば」
「任せておいて、好きなようにさせてよ」
「はい・・・・、嬉しい・・・」
何かをしていないと感情が吹き出しそうになる。友絵はパスタを食べながら半分泣き顔になっていることに気が付いたが、それでも宏一の側にいたくて必死に涙を堪えていた。宏一も友絵の目が赤いことに気が付いたが、友絵が何も言わないのでそっとしておくことにした。きっと余程のことなのだろう、とは思ったが、そう言う時に自分の側にいてくれることを選んでくれたのだから、友絵の気持ちをそっと受け止めるだけにしておこうと思った。
「あー美味しかった」
「気に入ってくれた?」
「すっごく気に入りました。私もこの店、使いますよ」
「それは良かった。どうする?少し歩こうか?」
「最近、運動不足ですからね、ふふ」
宏一は勘定を済ませて店を出ると、友絵を原宿の方に誘った。最短距離を行くのなら一度渋谷駅に戻るのが近いのだが、宏一はNHKから代々木公園を抜けるルートを選んだ。歩くと少し距離があるが、公園に入れば日陰もあるので今の二人には丁度良い距離だった。少し汗をかいたが、二人とも全く気にせず、殆ど話もせずに歩き通した。それは二人にとって初めての静かな時間だった。
やがて二人は原宿の喧噪の中に出ると、どちらとも無く会話を始めた。
「やっぱりいつ来ても混んでるね」
「久しぶりだなぁ、原宿なんて」
「友絵さんでもしばらく来てないの?」
「高校生以来じゃないかな?」
「だいぶ替わってる?」
「大きいビルなんかはそのままみたいだけど、小さい店なんか全部替わったかも・・・全然知らないのばっかり」
「どう、せっかく来たんだから竹下通りに行ってみない?」
「・・・・そう・・・でも・・・」
友絵には余りその気がなかったみたいだが、宏一は半ば強引に友絵を連れて竹下通りに入っていった。
「うわぁ、凄い人だ」
「やっぱり、ここはいつでも変わんないんだ」
「ちょっと横道に入ってみようか?」
「え?でも私もよく知らないから」
「なんとかなるよ」
二人は竹下通りから一本表参道寄りの狭い道に入った。ブラームスの小道と言う表示が見えたので名前が付いている道らしい。
「あーあ、一息ついた」
「凄かったね」
「やっぱり二十歳を超えてからだと、ここを歩くのは勇気が要りますね」
「うん、なんか修学旅行の団体に迷い込んだみたいだものね」
「でもこの道は静かで良い雰囲気」
「そうだね」
「宏一さん、あのー?」
「なあに?」
「ちょっと行ってみたい所って言うか、おねだりしてもいいですか?」
「いいよ?どうしたの?」
「この通りは竹下通りの一本横なんだから、こっちへ行けばそろそろあるはず・・・あ、あった!」
友絵は一軒のクレープ屋を見つけると、嬉しそうに宏一を手招きして店内に入っていった。
「前から知ってる店なの?」
「中学の時に初めて原宿に来てから、来ると必ず寄ってるんです。って言っても何年も来てないけど」
「歴史のあるクレープ屋さんなんだね」
「確か20年以上の歴史があるって・・・」
「へぇ、そりゃすごいや」
「買ってもらってもいいですか?」
「もちろん」
「それじゃ、私は定番のバナナチョコ生クリームにしようっと。宏一さんは?」
「う〜んと、シナモンアップルかな?」
友絵は嬉しそうにクレープを注文して受け取ると、笑顔一杯で店を出た。
「やっぱりこういう所なら歩きながら食べないと、ね?」
「ねぇ、友絵さん、普通チョコバナナって言うのに、あの店ではバナナチョコだよね?どうして?」
「さぁ?よく分かんないけど、昔からある店ってメニューの名前が違ってたりしますよね?」
「そう言われてみればそうかなぁ?」
「あんまり気にしなくていいんじゃないですか?」
「それもそうか」
「嬉しいな、宏一さんに買ってもらっちゃった」
どうやら友絵には何か原宿での思い出があるらしく、宏一にクレープを一つ買ってもらったのがとても嬉しいようだった。
「美味しい?」
「もちろん。最高です。あ、味だけじゃ、無いですよ」
そう言うと友絵はにっこり笑った。クレープを食べてからの友絵は、何かが吹っ切れたかのように明るくなっていた。そして宏一をヴィトンやらベネトンへ連れ回し、何を買う訳でもなかったがとにかく楽しそうだった。楽しそうに宏一に話しかける友絵は、時折宏一の腕を取ってじゃれつくように宏一に甘えてきたし、宏一も悪い気はしないのでかなり陽気に友絵に話しかけた。
二人は表参道の駅まで来た時、時刻は既に3時近くになっており、ごく自然に友絵は宏一と別れた。
「それじゃ宏一さん、時間に遅れちゃダメですよ」
「ああ、美味しいものでも食べようね」
「何をおねだりしようかな?」
「それまでに考えておいてね」
「はい、それじゃ、行ってきます」
「うん、待ってるよ」
友絵はそう言うと宏一に背を向けて歩き出した。しかしその表情は一転して硬く、味方によっては辛そうとも思えるほど沈んだものだった。
宏一は友絵がこんなにも陽気なデートをすることに新鮮な驚きを感じたが、『きっと仕事のストレスが溜まっていたんだろうな』と軽く考え、友絵を見送ってからどこに行こうか考えてみた。
特に今行きたい場所も用事もないのだが、ふと明日は一枝と午後を一緒に過ごさなくてはいけないことを思い出した。そして部屋に食べ物や飲み物を買っておいた方が良いだろうと思いついた。明日部屋に入る時に買っても良いのだが、もし忘れると飲まず食わずで半日過ごすことになりかねない。気軽に外に買いに行ける雰囲気になれば良いのだが、そうならない可能性もある。何しろ一枝とじっくり二人になるのは初めてなのだ。
宏一は表参道から何度も乗り換えていつものワンルームマンションの最寄り駅まで来ると、近くのコンビニで買い物をした。
そして、飲み物は少し多目に買って部屋に向かった。既に4時前なので友絵との待ち合わせの大井駅に7時に着くためには2時間半くらいしか時間がない。宏一は来たついでにいつものワンルームの部屋で一眠りしてから出かけようと軽い気持ちで部屋を開けた。
カチャッと鍵を外して部屋に入ると、見慣れた靴があった。そして少し落ち着かない様子でベッドに座っている由美の姿が見えた。
「あれ?由美ちゃん、どうしたの?」
「ええ・・・・ちょっと・・・・」
なんか由美の様子が変な気はしたが、それが特に重大なことにも思えなかったので、宏一は更に気楽に話しかけた。
「まさか由美ちゃんが来てるなんて思わなかったよ。コンビニで食料を調達してきたから冷蔵庫に入れておこうと思って」
「ちょっとシーツを交換しておこうと思ったから・・・」
見ると、木曜日にあれだけ激しく愛し合ったのに、今は綺麗にベッドメーキングされていた。このマンションでは1階のエレベーターの奥にランドリーボックスがあり、そこに洗濯物を入れておくと業者がクリーニングを掛けて、中の封筒に入れておいたお金からクリーニング代を引いていく。宏一はそれをやってくれた由美の気持ちに気づくことなく、
「ありがとう、由美ちゃんて良く気が付くよね」
と気軽に応じて、由美の隣に座った。
由美はその宏一の無神経さに少し苛立った。自分がどんな気持ちで明日、宏一が一枝を抱くこのベッドのメーキングをしたと思っているのだろうか?更に気に障ることに、一枝は月曜日になれば、またチラッと由美に自慢げに何かをほのめかすに違いない。そして由美はこのベッドの上で何が行われたか想像することになるのだ。それは由美にとって耐え難い屈辱だった。自分で言い出した事とはいえ、宏一が一枝を抱いている姿を想像すると髪の毛が逆立つほど腹が立つ。一枝の性格からすれば、楽しそうに由美に仄めかすことくらいは想像できるのだが、一枝にも由美に対して気を遣って欲しかった。
宏一は自然に由美の背中から手を回して由美を軽く引き寄せた。
「いや、だめ・・・です・・・」
「どうしたの?」
「今は・・・・ちょっと気持ちが・・・・・きっと感じないと思うんです」
そう言いながら、小さな膨らみに回ってきた手を軽く押しのけた。今日の由美はチェックのミニスカートに薄いブラウス姿だ。制服の時より少し大人に見えるが、十分に由美の魅力を引き出している。
しかし宏一は、思いがけず由美と一緒の時間を過ごせることで、すっかり由美を抱く気になっていた。由美が宏一の手を払いのけようとすると、その細い手を握って、
「どうしたの?せっかく二人で過ごせる時間ができたのに」
と言いながら由美の手に自分の手を重ねる。
すると由美は慌てて右手を更に払いのけて、
「今日は時間もないし・・・・」
と宏一の腕の中から立ち上がって逃げ出そうとした。
「どうしたの?何時まで良いの?」
宏一は慌てて由美を引き戻すと、優しく由美の耳元で囁いた。
「由美ちゃん、怒ってるの?」
宏一にそう言われては由美もどうして良いか分からない。
「そんなこと・・無い・・・ですけど・・・・・」
「じゃあ、何時まで一緒にいられるの?」
由美はそのまま宏一の誘いを断って部屋を出ても良かったのだが、少しだけ宏一と一緒に過ごしたいという気持ちの方が強かった。
「6時頃には出ていかないと・・・」
「それなら6時までは一緒に居ても良い?」
「・・・・・・・はい・・・・・」
相変わらず硬い表情のままで由美は頷いた。しかし、宏一に抱き寄せられていると少しずつ気持ちが宏一に傾いていく。もともと由美は宏一が大好きなのだ。そんなに宏一を拒み続けられる訳がない。それは由美自身にもよく分かっていた。
しかし今、宏一に抱かれるのは恥ずかしかった。その前に手を洗っておきたかった。宏一は由美のそんな気持ちには全く気付かず、由美の耳元で優しく囁いてくる。
トップ |