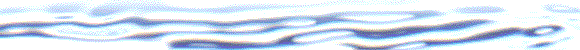「せっかくこうやって二人になったんだから、こっちへおいでよ」
宏一は二人の距離が縮まれば、新しい展開があるかと思って一枝を再びベッドに座っている宏一の横に誘った。一枝にそれは命令のように響いた。あまり嫌がると宏一が諦めて帰ってしまうかもしれないと思った。それは由美に対する一枝の敗北を意味している。自分から言い出しておいて宏一が呆れて帰ってしまえば、明日学校で由美の顔を見るのが辛くなる。
「はい・・・・」
一枝はほとんどいやいやながら宏一の横に座った。すると、すぐに宏一の手が背中から横へと回され、一枝の身体をさらに宏一の方へと引き寄せられた。
「あ、ちょっと・・・、い・・・や・・・・」
「どうしたの?こうするだけでもいや?まだ何にもしてないのに」
「そういうことじゃなくて・・・ちょっとぉ、・・いや・・・・」
一枝は宏一の腕の中でじたばたしていた。まだ心の準備ができていないのに、宏一の腕の中に入るのはどうにも嫌だった。
宏一は何とか一枝の気持ちをすっきりとさせて、早く一枝の身体を開発したかった。このままでは時間がかかるばかりで、由美が苦しむ日が長くなる。だから少しだけ焦っていた。その焦りはいつもの余裕をなくしてしまっていた。
「一枝ちゃん、俺はね、昨日は会社に少し出て、午前中は仕事をしていたんだ。それから渋谷で友達と会って、お昼を食べてね・・・」
いつもの一枝にそんなことを言えば、たちどころに『それって女の人?』と突っ込まれるところだが、一枝はほとんど話を聞いていなかった。それでも静かに宏一の話を聴いているように見えたので、宏一は少しずつ一枝の顔に近づいていった。
たちどころに一枝が反応し、
「嫌、ちょっと、近づかないで、ちょっと、いやだってば」
と立ち上がって逃げ出そうとする。しかし、こんなことを繰り返していても埒が明かないので、宏一は少し強引だとは思ったが、一枝の身体をグイッと引き寄せるとキスをしようとした。
「いやっ、ちょっと、なにするのよ!」
一枝は無理やり宏一の手を振り解くと立ち上がって部屋の隅に行き、猛烈に怒った。
「まだ心の準備ができていないのがわかんないの?無理やりしようとするなんてサイテー!」
その言い方があまりにもきつかったので宏一は驚いて謝った。
「ごめん」
「ゆんにはそうやって謝れば済むんでしょうけど、私はゆんじゃ無いのよ。宏一さんだったら優しく教えてくれるかと思ったけど、嫌がってる女の子に無理矢理しようとするなんてサイテーじゃないの。宏一さんがこんな人だったなんて思っていなかった。こんな人に近寄られるだけでも気持ち悪いわ!私、帰るっ!」
一枝はそう言うと、慌てて荷物を掴むとさっさと帰ってしまった。後にはぽつんと宏一が残された。
宏一は猛烈に後悔していた。『もっと優しくしてあげればよかった』と思った。しかし、それではいつまで経っても同じことだ、とも思った。いずれにせよ、由美の一枝への思いを台無しにしてしまった。どうすれば良かったのかは分からなかったが、これでまた由美が悲しむと思うと気が重かった。
部屋を飛び出した一枝はもっと大変だった。部屋から出るときにもう後悔し始めていたし、エレベーターを降りてロビーに出たときすでに悲しさで目に涙が浮かんでいた。『どうして素直になれないの?せっかく宏一さんが作ってくれたチャンスなのに。せっかくのチャンスを自分から溝に捨てるなんて。それだからいつまでたっても恋人もできないの。またやっちゃったじゃないの』後から後からもう一人の自分の声が湧き上がってきた。
このままでは泣き顔で駅まで歩いていきそうだったので、とりあえずコンビニに入って本のコーナーの角で雑誌を食い入るように見ている振りをして顔を隠し、落ち着くのを待つことにした。
そして少し落ち着いたとき、自然に由美に電話していた。由美も気にしていたのだろう。1回のコールで出た。
「ゆん・・・・」
「一枝ちゃん・・・・・?」
「ごめん・・・・」
「どうしたの?」
「出てきちゃった」
「どこ?」
「そばのコンビニ」
「・・・・・逢える?」
「いいの?」
「どこがいい?」
「エクセルシオールは?」
「三茶の?」
「うん」
「わかった」
「同じくらいに着くと思うけど、一枝ちゃんが先に着いたら待っててね」
「うん」
一枝は電話を切手から、どうして由美に電話したんだろうと不思議に思った。本来なら由美にこそは絶対に黙っていたいことのはずなのに。でも、それが自分と由美との関係なのだと思った。そう思うと少し気が楽になり、ゆっくりと待ち合わせ場所に向かって歩くのもそれほど辛くはなかった。
待ち合わせのコーヒーショップに由美は早めに来ていた。一枝が現れると由美はその表情からどんなことが起こったのか、だいたいの察しは付いた。いつもの一枝は元気で快活だが、本当は恐がりで気の小さい女の子なのだ。それを隠すためにいつもは威勢良く振る舞っているのだが、未知のことにはうまく対処できないことがある。一枝のそう言う部分が、いつもはおとなしいのにいざとなると大胆になる由美と正反対で、お互いに惹かれあっている部分なのだ。だから由美は一枝の恐がりの性格が出たのだと直ぐに見抜いた。
「ゆん・・・・またやっちゃった・・・・」
「大丈夫。宏一さんはきっと気にしてないから」
「でもね・・・・私、言っちゃったの・・・・サイテーって・・・」
「大丈夫よ。宏一さんは大人だから」
「だって・・・・・」
それから二人は長い間顔を寄せ合って話し込んだ。何度もコーヒーをお代わりし、いろんな話題で話し続けた。本当にこんなにたくさん話をしたのは久しぶりだった。一枝はどうしてこんなに素直に話ができるのか、自分でも不思議だったが、心の中に溜まっていたいろんな事が素直に口から出てきた。由美は静かにそれを聞き、優しく受け答えしていた。
再び忙しい週が始まった。出社した宏一は友絵と今週の予定を確認する。二人の机はこの部屋の中で二つだけの事務机で、向かい合わせにおいてあるので打ち合わせはやりやすい。どこの職場でも月曜日にはミーティングがあるものなので、今日も廊下の人通りは少なく、第三応接は他の職場と離れていることもあってとても静かだった。この部屋にいつも出入りしている工事業者にしても打ち合わせが月曜にあるのは同じなので、まだどの工事業者も来ていない。
「・・・そう、それが終わるといよいよファイバーケーブルの設置になるんだね」
「はい、そうなると思います。もっともユニワンケーブルさんの都合もあるとは思いますが」
「それじゃ、水曜日にケーブルをユニワンの倉庫から運び込む手配をお願い」
「はい、分かりました。水曜日の夕方くらいになると思います」
「問題ないよ」
「次はルーターですけど・・・」
二人は次々に予定を確認し、手配の順を決め、工事予定を実行に移していく。しんと静まりかえった部屋の中に二人の声だけが響き、エアコンだけが相づちの音を出しているかのようだった。工事業者も昼前にならないと入ってこないだろう。
「話し続けたから少し喉が渇いたな。それじゃ、お茶にしようか。お茶菓子買ってくるの、忘れたけど」
「大丈夫です。一口饅頭が残っていたはずですよ」
友絵はそう言うと部屋の隅にあるポットからお茶を入れて応接テーブルに並べた。宏一はブラインドの隙間から外を眺めていた。外の景色もどことなく動きに欠けるような感じがして、月曜であることがよく分かる。昨日の一枝のことが気にならないではなかったが、今は仕事に集中するときだ。そして今は目の前にいる友絵が気になり始めていた。本当は、今は少し友絵に甘えたい気分だ。
「三谷さん、お茶、入りましたから休憩しましょう」
そう言いながら友絵が宏一の横を通り過ぎようとした時、宏一が手を伸ばして友絵を振り向かせて、そのまま腕の中に抱きしめた。突然のことで驚いて目を丸くした友絵が腕の中で逃げようとしている。まだお茶を運んだお盆を持ったままなので、それを宏一の胸に押しつける。
「友絵さん、今日は月曜。まだ午前中だから誰も来ないよ」
「だめ・・・だめ・・・いや・・・」
友絵は顔を背けて宏一を見ないようにしている。しかし宏一にはそのわずかに覗いたうなじがとても刺激的だった。ゆっくりと顔を近づけていく。
「ダメです。今は仕事中だし、それに週が始まったばかり・・・」
友絵の抗議は宏一の唇がうなじに触れた瞬間に途切れた。すっと目をつぶった友絵を宏一の唇がゆっくり細いうなじを征服していく。
「うっ・・・・・くっ・・・・」
友絵は今抗議をするとおかしな声になりそうで、黙って耐えるしかなかった。その間にゆっくりと友絵の身体が宏一に反応を始める。頭の中では『これ以上はだめ。早く逃げ出さなきゃ』と思っているのだが、しっかりと抱きしめられているので身体を捻ることさえできなかった。
宏一は友絵のうなじをたっぷりと味わい、可愛らしい耳を唇で挟んで舌を耳の裏に這わせる。ここは友絵がかなり感じる場所だった。ピクッと小さな体が震えるのが宏一にもわかる。顔を真っ赤にして小刻みに震え始めた友絵は、
「だめ・・・・許して・・・・これ以上は本当に・・・・」
とうわずったような声で囁いた。しかし押しのけようと突っ張っているはずの手には力が入らない。宏一は更に唇を奪おうと舌を這わせながら、友絵がしっかりと抱えているお盆をゆっくりと取り上げ、ソファの上に置いた。そして友絵を優しく抱きしめて唇が重なり合うと、友絵も観念したのか抵抗が無くなり、友絵の手が宏一の首に回される。友絵はすでにかなり感じてしまっているので、宏一に掴まらないとふらつきそうだと心の中で自分に言い訳をしている。
静かな部屋で二人はそのまましばらく大胆に唇を求め、やがて大胆に舌を絡め合った。友恵はここまで来ると化粧を全てやり直さなくてはいけないので、却って気が楽になったらしく、宏一の手が胸の膨らみを撫で始めてもされるがままに感じていた。
「せめてブラインドを・・・閉めてください・・・」
それだけを言うと、友絵は宏一の腕の中で熱い息を弾ませる。宏一がその通りにすると、
「仕事が始まったばっかりなのに」
と可愛らしく睨み付け、今度は積極的に首に手を回して唇を押しつけてきた。
しかし、この部屋でできることなど知れている。友絵もそれが分かっているからこそ大胆にキスをせがむことができたのだ。しかし宏一としてはこのままやめる気にはなれなかった。まだ工事業者が来るまでは時間があるし、ほとんどの部署は週始めの会議中だからほとんどみんな自分の机にいるはずだ、だからこの第三応接の周りにある他の応接室も月曜の午前中に使われるとは思えなかった。
そのまま宏一は友絵をロングソファに誘い、自分の膝の上に抱き上げて横向きに座らせた。友絵もしばらくは誰も来ないと思ったのか、もう嫌がらない。
「少しだけですよ」
友絵は今度は全く嫌がらずに大人しく宏一に身を任せる。宏一は友絵の唇をねっとりと味わいながら、ミニスカートの中に手を入れて奥の秘密の場所を探り始めた。抵抗されるかと思ったが、友絵は軽く足を開いて宏一の手が動くスペースを与えてくれた。ストッキングを履いているので肌の感触は分からない。しかし、宏一の手が太股を撫でながら奥に入っていくと急に瑞々しい肌を探り当てた。どうやら今日の友絵はパンティーストッキングではなく、ガーターベルトで釣るストッキングを履いているようだ。更に先を探っていくと、思った通りパンティの軽やかな布地を見つけることができた。
トップ |