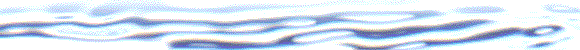「私、可愛くない?」「どうして?そんなことないよ。とっても可愛いよ」
「だって、何もしなかったくせに」
「一枝ちゃんと話もせずに、すぐに身体だけ抱くのは嫌だっただけだよ。こんな風に話をして、一枝ちゃんの気持ちも抱きたいんだ。すぐにでもベッドに押し倒したいって気持ちはあるんだよ。今でも」
「そうなの?」
「もちろん」
「ゆんみたいにプロポーション、よくなかったでしょ?」
「あのね、一度はっきり言っておくけど、由美ちゃんは一枝ちゃんじゃないの。違う人を比べてみても仕方ないでしょ。そう思わない?」
「思うけど・・・・。なんか騙されてるみたい」
「そうか、それじゃぁこう言おうか。もし由美が今の一枝ちゃんみたいに、お互いによく話もしないうちから服を脱いで『抱いてください』って言ったって、きっと今みたいに『服を着てほしい』って言ったと思うよ」
これは本心だった。
「あんなにきれいでも?」
「きれいな身体はとっても魅力的だけど、気持ちが付いていない身体には魅力は無いと思うな」
「そう?」
「うん。だから、一枝ちゃんも気持ちも抱かせてくれないと、このまま何もしないよ」
「どうすればいいの?」
「そうだね。まずはこうかな?」
宏一は隣に座っている一枝をさらに引き寄せ、少し自分に寄りかからせる感じで後ろから手を回して一枝の前で組んだ。宏一の得意の体勢だ。
「いや?」
「ううん、だいじょうぶ・・・・たぶん・・」
「ちょっと緊張してるかな?」
「すごく・・・だと思う・・・」
「そうか、それじゃ、緊張がほぐれるまではこのままだね」
「今日中にほぐれなかったら?」
「また今度だね」
「それじゃ、いつになるかわからないじゃない。『今日こそは』って思ってきたのに」
「だめなの?」
「そんなにいつまでも持たない・・・・」
「持たない?」
「・・・・今日だってすごく緊張して、それでもなんとかここまで来たのに。これから先もいつまで緊張し続けなきゃいけないのかわからないなんて、私には無理」
「大丈夫だよ」
「どうして?」
「だって、昨日この部屋を出て行ったときはもっと緊張していて、怖かったろう?」
「うん」
「今日はそれより楽なんじゃない?」
「うん・・・」
「大丈夫。きっとどんどん緊張しなくなっていくよ」
「うん」
一枝は宏一と少し話をしただけで、自分の緊張がだいぶほぐれてきたことに気が付いた。今でも怖いことには変わりないが、我慢できる程度の怖さだ。
宏一は、一枝が宏一の存在を受け入れようとしていることに気が付くと、また少しだけ一枝に近づき、耳元で囁くように話を続けた。
「ほら、こうするだけでもだいぶ感じが違うだろ?」
一枝は耳元で囁く宏一の声に少しびっくりした。ほんの少し宏一の顔が近づいただけなのに、全然感じが違う。『これが恋人の距離って言うんだな』と思った。
宏一は一枝が嫌がらないので、焦らずにこのまま一枝の緊張を解す事にした。一枝が腕の中にいるのだから、ほんの少し手を伸ばせばツンと張り出した乳房を自由にすることもできるのだが、一枝が感じてくれないのでは意味が無い。一枝が感じるようになるまではもう少し我慢が必要なのだ。
それに今の宏一にとって、一枝は可愛らしい存在になりつつあった。この一枝の身体が可愛らしい声と共に仰け反る姿を想像するだけでもワクワクしてくる。そして宏一が望むように一枝の身体を開発する楽しみは一度しか味わえないのだ。その為には、今は一枝が宏一に抱かれたいと思う環境を作り出すことが大切だった。
「一枝ちゃんのこと、聞いてもいい?」
「うん」
「一枝ちゃんは彼氏、いたの?」
「友達ならたくさんいるけど、彼はいないな」
「前も?」
「うーん、中学の時にはそれっぽい人はいたけど、結局だめだったみたい」
「ふられちゃったの?」
「ううん、告らなかったから」
「お互いに?」
「いい雰囲気になったことはあったけど、それでも相手から何も言われないってことは、そういうことだったのかなって」
「相手もそう思ってたんじゃない?」
「そうかもね。でも、私も告らなかったし」
「好きだった?」
「うん」
「そう、残念だったね」
「そうだね。今から思うとね」
一枝は耳元で宏一が囁くたびに、少しくすぐったくなってきた。宏一の息が耳元にかかると、耳の辺りがくすぐったくなるのだ。これは初めての経験だった。背中からも、身体の前に回された手からも、そして意気からも宏一の体温が感じられる。『包まれるってこんな感じなのかな?』と漠然と思った。
「宏一さんは高校のとき、彼女いたの?」
「1年のとき?」
「うん」
「ちょっとだけいたよ」
「ちょっと?」
「そう、中学の後輩の女の子」
「告った?」
「う〜ん、そうだったかなぁ。でも、なんとなく付き合って、友達も俺たちを二人にしようとしたがって、二人だけでいたときにいい雰囲気になってキスして・・・そんな感じだったと思う。はっきり好きだって言ったのはその後かな?」
「好きだった?」
「もちろん」
「相手の子も?」
「うん」
「いいなぁ。わたし、そんな風にはなんなかったから」
「そうだね。大切な思い出だよ」
「どうして別れたの?自然消滅?」
「それが違うんだな」
「ふられたの?」
「そう、だね」
「相手の子に好きな人ができたの?」
「違うよ」
「喧嘩したの?」
「違うよ」
「どうして?」
「相手の子が疲れちゃった、って言うところかな」
「疲れた?」
「そう、好きな相手ができると、その人のことがものすごく気になるでしょ?」
「たぶん・・・そんな事なったこと無いからわからないけど」
「一枝ちゃんだって、彼氏にはならなかったかもしれないけど、相手のことはすごく気になってたはずだよ」
「そう・・・」
「でも、俺は高校だし相手は中学で、なかなか会えないでしょ?それで、その会えない関係がとても辛くなったみたいだね。そして、あるときにその関係に耐え続けるのに耐えられなくなった、みたい」
「それでふられた・・・」
「そう、『これからはもう一度友達の関係にしましょう』って言われた」
「それで、終わり?」
「そう、結果的にね。その子の友達の彼が親友で、そいつ経由で聞いたんだけど、別れ話をしてすぐにその子はものすごく後悔したんだって。でも、戻ってはこなかったな。俺の方からもう一度声をかけたらって何度も言われたんだけど」
「後悔してる?」
「あの時、俺からもう一回声をかけなかったこと?」
「そう。だって、そうすれば元に戻ったかもしれないでしょ?」
「そうだね。正直に言うと少し後悔してるよ。でもね、きっと同じことだったと思う。元に戻っても、きっとまたふられただろうね。二人がなかなか会えないって関係は変わらないんだから」
「そうか・・・・」
一枝は宏一の腕の中にいるのがとても気持ち良くなってきた。由美以外に、こんなに正直に自分の心の中を話したこともなかったし、宏一も正直に話をしてくれている。今は宏一の体温を通して宏一の心に包まれているようで、とても気持ちよかった。
「でも・・・」
「なんか残念だったね」
「そう思うよ。今でも時々ね」
「ねぇ」
「なあに?」
「こんな話、ゆん以外にしたのは初めてだよ」
「そうか、それは光栄だね」
「もう、分かってよ〜」
「何が?」
「私、さっきから待ってるんだよ」
「ん?」
「もう、鈍感!」
「こういう事?」
宏一は一枝の体を自分のひざの上にそっと倒した。一枝は急に宏一を見上げる姿勢になったので、少し驚いた。宏一は一枝の首の下に左手を当てて、そっと上半身を支えてくれている。完全に横抱きにされている形だ。
「こうして欲しいの?」
「あ・・・あの・・・・・・」
宏一は右手の指先で一枝のうなじをそっと撫ぜながら、
「ほら、こうすると気持ちいいでしょ?」
と一枝のほうに顔を近づけながら囁いた。
「・・・で・・・そうじゃ・・・」
「違うの?」
確かにそっとうなじを指先で撫で上げられるとくすぐったいような不思議な感じがする。しかし、一枝はどう答えていいのか分からなかった。
トップ |