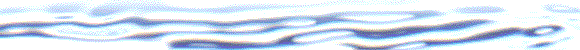「これなら見えないからいいだろ?」「ああん、だって、こんなことされるなんて・・・」
「いや?」
「そんなことないけどぉ・・・」
「良かった。だんだん感じてくるだろ?」
「そんなこと、耳元で言わないで・・・」
一枝は耳元で宏一が囁く度に、宏一の息が耳とその周りの髪の毛にかかり、さっきよりもずっとくすぐったく感じるようになってきた。
「だって、こんなかわいらしい耳が目の前にあるんだもん。よし、食べちゃおうかな?」
そう言うと、宏一は両手で膨らみを優しく撫で回しながら一枝の耳をそっと唇で挟んだ。
「あんっ!」
一枝は新しい感覚が身体の中で小さく弾けた事に驚いた。『宏一さんに胸を触られながら耳を食べられてる!』そう思うだけで自分の今の姿が頭の中で想像され、恥ずかしくて仕方がない。しかし、恥ずかしいだけではない、何か新しい感覚に包まれていることも確かだった。
「可愛い耳だね」
「そ・・・そ・・・そう?・・・」
どう答えていいのか分からない。一枝は次第に胸の感覚も高まってきたことに気が付いた。宏一はさらに一枝の耳を唇で挟むだけではなく、そっと舌で舐めてみた。
「ああっ!」
「いや?」
一枝はもう何も言えない。ただ、恥ずかしいのと変な感覚が身体を走り抜けることを受け入れるだけで精一杯だった。そのまま宏一は一枝の小さなうなじを唇と舌で愛撫する。
「はあぁっ、あんっ、だめ・・・・そんなにしないで・・・・ああんっ、いきなりこんなこと・・・・」
「いきなりじゃないよ。一枝ちゃんだって分かってるだろ?」
「でも・・・まだ・・・・あん・・・」
一枝は自分の声が裏返りそうで、ちゃんと話すだけでも大変だった。
「まだ始まったばかりだよ。一枝ちゃんの身体もやっと準備を始めたみたいだね」
「そう・・・なの・・・?」
「身体が熱くなってきた?」
「うん」
「ほら、ここだって触られて反応してきたみたい」
宏一はやっと固くしこってきた膨らみの先端を親指と人差し指で確かめるように軽く布地の上から摘んでみた。
「・・・・・・・・・・」
一枝は何も言わない。痒いようなくすぐったいような、不思議な感覚だ。由美にこんなことをすれば声を上げて仰け反るのだが、一枝はまだ感覚が開発されていないから、快感なのかどうかも分からないらしい。
「こ・・・・宏一さん・・・・」
「なあに?」
「なんか変なの・・・。でも・・・よくわかんない・・・・」
「良いんだよ。初めてなんだから」
「でもぉ、感じなきゃいけないんでしょ?」
「そんなことないよ。でも、一枝ちゃんは感じてるみたいに見えるけどね」
「変な感じがするだけ・・・」
「いいよ。無理しなくても」
「ちょっとだけ、手をどけてくれる?」
「いやなの?」
「ううん、そうじゃないけど・・・・・」
一枝はそう言うと、宏一の二の腕をつかんで両手を服の中から引き出した。とにかく一度気持ちを整理したかったらしい。宏一はそのまま一枝を再び横抱きにする形で膝の上に横たえると、上気した顔の不安そうな少女がじっと宏一を見つめていた。
「一枝ちゃん、可愛いよ。大丈夫。任せておいて」
そのまま自然に唇が重なる。それは先程よりも感情のこもったものだった。一枝は宏一に身体を寄せて、甘えるようにして必死にキスをした。何かに縋っていないと耐えられないほど恥ずかしくて怖い。宏一も、そんな一枝が可愛くて優しく教えてあげたくて仕方なかった。宏一の気持ちとしては『教える』というより『守る』という感覚に近い。
一枝は宏一の舌が口の中に入ってくると、一瞬だけ戸惑ったが、すぐにおずおずと自分の舌を突き出してみた。そして、何度か逃げ回っていた舌がつんつんと宏一の舌にぶつかり、次第に何度かしっかりとくっつき、そして絡み合うようになるまでそれほど時間はかからなかった。
一枝はうっとりとしながら初めてのディープキスに夢中になっていた。頭の中がぼうっとなり、なんとも言えない不思議な気持ちになっている。舌を絡めながらブラジャーの上から膨らみを探られるととても気持ちが良かった。ぼうっとした意識のまま『私、感じてる』と思うと少し嬉しかった。
やっとディープキスにも慣れてきたころ、一枝は宏一の手が胸を探っていないことに気が付いた。胸を触られる感覚に慣れてきたので、それが無いとちょっとだけ寂しかった。
ふと気が付くと、スカートの布地が少しずつずり上がっている。『!!!!!』一枝は宏一が何をしようとしているのか即座に理解した。もし、こんな状況でなければ宏一を突き飛ばして逃げ出すところだが、なぜか身体は弱くしか反応しない。
「いや・・・それはいや・・・・いや・・・だめ・・・・下はだめ・・・」
横を向いてキスをやめると、小さな声で言うのが精一杯だった。身体を起こそうとするのだが、うまく力が入らない。何とか手で宏一の手を探し出して押し出そうとしたが、全く力が入らなかった。
「一枝ちゃん、大丈夫。任せておいて」
「いや・・・下はいや・・・・いや・・・」
宏一は再び優しくキスをした。キスをしている間、一枝は積極的に唇を返してくる。何かに夢中になっていないと怖くて仕方ないのだ。宏一は少しの間キスを楽しんだ。
「一枝ちゃん、大丈夫。落ち着いて」
「いや・・・それはいや・・・いやなの・・・」
「一枝ちゃん、手をどけてくれないかな」
「いやなの・・・怖いの・・・」
「一枝ちゃん、一枝ちゃんが受け入れてくれないと、これ以上はできないよ。そのほうが良い?」
「だって、怖いから・・・・」
「急にはしないから安心して。少しずつ慣らして行こう。一枝ちゃんが嫌がっているうちはしないからね」
そう言うと宏一は、再びキスをしながら胸を愛撫してくれた。一枝にしてみればここまでできただけでも大成功だった。それまで心のどこかでは『自分は男の人とキスをすることや身体を触られることなんて絶対できないんじゃないか』『すぐに逃げ出して、その逃げ出す自分を見るのが怖くて、男の人と付き合うことなんてできないんじゃないか』と思っていた。だから、宏一に優しくリードされてここまでできただけでも十分な気がした。
宏一は一枝に拒絶されたことなど気にしていないかのように優しく触ってくれている。最初のときよりもしっかりと触られており、もはや撫でるだけではなく、時折軽く揉んでくるし、乳首の辺りを丁寧に指先で刺激してくる。それは一枝を飽きさせずに夢中にする優しくて上手な愛撫だった。
時折宏一の手はスカートの方に下がると、その中に入ってきたが、その度に一枝の手は宏一の手を拒んだ。すると宏一の手は大人しく胸へと戻って再び胸を愛撫してくれた。
最初のうち、宏一の手がスカートの中に入ろうとする度、一枝は絶対にいやだと思っていた。胸だけで十分だと思っていた。しかし、その感覚にも慣れてくると、心の中に少しだけ冒険してみたい、という気持ちが湧き上がってきた。しかし、自分でもしっかりと奥まで見たことのない場所を触られるのは絶対に嫌だった。
それが何度も何度も宏一の手を拒んでいるうちに『ちょっとだけパンツの上から触られるだけなら良いんじゃないかな』と思い始めた。夜ベッドに入ってから自分だけの秘密として触っているときにどんな感じがするのかは分かっていたので、パンツの上からそっと触られるだけなら良いかもしれない、と思い始めたのだ。
ただ、それでも宏一の力強い手をスカートの中に受け入れるには時間がかかった。それでも宏一は何度でも辛抱強く試みてきた。
そして一枝が宏一にもっと先のことを教えてほしくなって心を決めたとき、一枝の手は宏一の首に回ってしっかりと引き寄せ、キスをしていた。
宏一は一枝が受け入れる決心をしたことに気が付いた。そっとスカートを捲り上げても一枝の手は宏一の首に巻きついたままだ。
時折宏一の手はスカートの方に下がると、その中に入ってきたが、最初は何度か一枝の手は宏一の手を拒んだ。すると宏一の手は大人しく胸へと戻って再び胸を愛撫してくれた。
宏一の手がスカートの中に入ろうとすると、一枝は心の中では冒険したいと思っていても、身体がそれを拒絶してしまうのだ。それに、冒険はしたいと思っていても、一方では胸だけで十分だとも思っていた。しかし、胸を愛撫される感覚にも慣れてくると、心の中に『あと少しだけ冒険してみたい、もうちょっとなら大丈夫』という気持ちが強くなってきた。しかし、自分でもしっかりと見たことのない場所を触られるのは不安だった。
それが何度も何度も宏一の手を拒んでいるうちに『本当にちょっとだけパンツの上から触られるだけなら良いんじゃないかな』と思いが強くなってきた。
一枝の手はさらにしっかりと宏一の首に巻きつき、ほとんどしがみついているみたいだ。宏一の右手がすぅーっと一枝の太ももを撫で上がり、小さな布地にたどり着いたとき、一枝の身体がびくっと震えた。
一枝は宏一がすぐに触ってくるものだと思っていた。そして、触りさえすれば宏一が満足して手を引いてくれることを祈っていた。しかし、宏一の手は指先で小さな布地の上を円を描くように撫でまわり、奥の敏感なほうへも行かないし、引き上げられることもなかった。
「嫌・・・早く、するならして・・・」
一枝は宏一の耳元で小さく囁いた。宏一が安心させようとキスしに行っても顔を横に向けてしまう。
「怖い?」
「早く・・・・怖いの・・・」
宏一は一枝がとても可愛らしく思えた。そして『これなら上手くいきそうだな』と少し安心した。
宏一の指先は、さらにしっかりと布地の上を動き回り、布地の下に隠されているものを確かめようとしているらしかった。それは一枝には耐えられないほどの不安だった。触られても快感など何も無いのだ。もう少し指が下に動いても今と同じだったら、自分が自分自身の身体に失望するんじゃないか、という怖さだ。
「宏一さん・・・・もう、早く、お願い、これ以上我慢できない」
宏一は布地の下に隠されている茂みが由美よりも少し濃いことに気がついた。茂みが濃い場合はそうっと触らないと、毛の硬さで敏感な部分が痛みを覚えることがある。宏一は慎重に指先を奥へと進めていった。
慎重に指を進めていくと、布地の最も狭い部分にかかるまでは確かに茂みが濃い感じがしたのだが、そこを越すと急に薄くなった感じがした。途端に、
「ううっ」
と一枝がうめき声を上げた。あわてて指を離し、
「痛かった?」
と聞くと一枝は、
「わかんない・・」
とだけ答えた。宏一は、
「もう一回触るからね。今度はもっとそっと」
と言うと、最初よりももっとゆっくり、軽く撫でるように触り始めた。布地の一番狭い部分を通り越し、茂みの感覚がほとんど無くなった辺りでそうっと布地を撫で始める。
「んんっ、うっ、んっ」
一枝が反応した。しかし、痛がっているのとは少し違うようだ。宏一は緊張していて身体が快感を受け入れるのを拒否しているのだと思い、時間をかけてそっと撫で続ける。
一枝は最も敏感な部分を宏一が触りまくっていることに怖がり、宏一ができるだけそうっと触っていることなど全然分からなかった。
トップ |