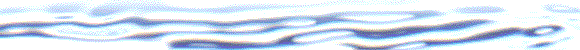「ああぁっ、宏一さん、許してぇ、そんなところ、あああぁぁぁっ、はうぅぅぅっ」
どんな感覚でも、一度知ってしまえばそれほど怖くは無くなる。恥ずかしさは無くならないが、次第に一枝もこの状況に慣れてきたらしい。一枝の声は少しずつ感じている声の部分が多くなってきた。もちろん、感じていると言ってもまだ開発が始まったばかりの一枝の身体は、由美程の快感を与えていないのだが、それを一枝が知るのはもっと後のことだった。
「一枝ちゃん、恥ずかしいのをよく我慢したね。ご褒美だよ」
そう言うと宏一は、両手を伸ばして乳房を揉み上げながら舌を丁寧に使った。舌の先で秘核を舐め上げたり転がしたり、そしてつんつんと押し込んだり、更に舌全体を使って非新語とゆっくり舐め上げたり、と一枝を夢中にしていった。
もう一枝には何も守るものが残っていない。全てを宏一に知られ、宏一に差し出してしまったという思いと、新たに乳房を揉み上げられた快感とが一枝の意識を押し流していく。
「あああぁーーーっ、そんなあぁーーっ」
こんなに気持ちいい事を覚えてしまって良いのだろうか、と言う小さな思いと、もっと覚えたいという素直な欲望が身体の中で渦巻いている。そして一枝は更に大きな快感に包まれ、身体を左右によじって悶えながら強烈な感覚に夢中になっていった。今の一枝は足を全開まで開き、少しだけ大きめの秘核とやっと開いてきた秘唇を舐められながら乳房を揉まれ、声を上げながら悶えているだけだ。頭の中にあった可愛らしく感じさせられながら甘えるように宏一に抱かれている自分など、既にどこかに行ってしまった。宏一は一枝がやっと夢中になって感じてくれたことが嬉しく、たっぷりと一枝が満足するまで丁寧に何度も秘核を舐め上げ、転がし、そして軽く吸い付いたり、舌で押し込んだり、とバージンの少女には濃すぎるテクニックを駆使して一枝を夢中にした。
やがて一枝の身体が快感に満足したのか、愛撫に対して反応が鈍くなると、宏一は一枝を解放した。
一枝は宏一の視線を感じながらも、足を大きく広げて秘部を丸見えの状態にしたままぐったりとしている。恥ずかしさはまだ残っていたが、夢中になって感じたので身体中がだるく、足を閉じることができない。その秘部は宏一の唾液と一枝の愛液でたっぷりと濡れているのがよく見えた。こんな恥ずかしい格好でいられるのは一枝がバージンだからだ。経験を重ねてくると、どんなに激しく感じた後でも、愛撫が終われば相手の視線を気にして足を閉じ、必ず恥ずかしくない、可愛らしい格好をするだけの心と身体の余裕ができてくる。今の一枝は精一杯恥ずかしがってたっぷり感じた後なので、もう何もする気力が残っていなかった。
だから、宏一が最後の一枚、スカートをそっと脱がしていっても、殆ど嫌がりもしなかったし、腰を浮かしたりといった協力もしなかった。それでも宏一は少し一枝の腰を持ち上げると、するりとスカートを脱がした。
そしてもう一度一枝の足を開くと秘部に舌を這わせていった。
「ああぁぁ、もうだめぇ、はうあう、宏一さん、もう、もうダメなのぉ、許して、これ以上はダメ・・・・あぁぁ・・・また、ああんっ、だめよう、はああぁぁぁーーっ、まだするのぉ?」
一枝は更に丁寧に舌を使われながら乳房を揉まれ、殆ど嫌がる気力が残っていなかったが、まだ口先だけは嫌がっていた。しかし一枝の身体は確実に宏一の舌を喜び、乳房の揉まれる感覚に夢中になっていった。宏一がやっと口を離して一枝を開放したとき、既に完全に力が抜けていた一枝は、しばらくはその状態でじっとしているしかなかった。本当に身体中の力が完全になくなり、手も足も鉛のように重く感じられて全く動かすことができなかった。
一枝は秘部を見られることはもちろん恥ずかしかったが、それよりもまた宏一が顔を埋めてこないかどうかが心配だった。これ以上されたら感じすぎて本当に死んでしまうのではないかとさえ思った。
一枝は生まれたままの姿で恥ずかしいところをたっぷりと舐め上げられ、乳房を揉まれているのが、恥ずかしいのに気持ち良い、そして嬉しいことに戸惑っていた。自分の声がもはや甘えるような喜びの声になっていることに気づいていたが、この時はそれが心からのものなのかどうか、心の隅でまだ疑っていた。
だから少しして身体に力が戻ってくると自然にうつ伏せになって何となく宏一からガードする姿勢を取った。
宏一が優しく一枝のうなじに唇を這わせながら、
「恥ずかしかった?」
と囁くと、一枝は小さくだが何度も頷いた。この時一枝はぼうっとした頭の中では、宏一が次に何をしてくるのか考えていた。そして既に裸にされてされることは全てされてしまったと思った。だから一枝は次には宏一が挿入してくるものと思った。既に一枝にはそれを拒む力など残ってはいない。『でも宏一さんがあれを私に入れようとするなら、もう一度仰向けにならないとダメよね、だからその時に心の準備をすればいいんだ。それまでは少し休ませてもらおう。とにかく身体が重くて・・・』と思った。それに、宏一が一枝に施したテクニックは、一枝にはかなり刺激が強すぎて、少し時間をかけないと心が受け入れきれないと思った。
しかし、宏一はすぐに一枝の尻に手を伸ばしてきた。たっぷりと宏一の口で愛され、熱を持っている秘唇が敏感に反応する。
「ああんっ、ちょっと、ああぁっ、待って・・まだ・・・」
一枝の声とは裏腹に一枝の腰がぴくっと反応して突き上げられる。
「ほうら、さっきとは違った感覚だろ?感じてごらん」
「あん、宏一さん、ちょっと、ちょっと休ませて・・・・」
「だって、一枝ちゃんのお尻は喜んでるみたいだよ。ほら、どんどん高くなってくる」
「いやぁ、ああん、見ないで、いやぁ、だめぇ、いやよう」
一枝は自分から自然に腰を高く突き上げていくのがどうしてなのか分からなかったし、お尻をどんどん突き上げていくのを宏一に見られているのが恥ずかしかったが、自分から進んで恥ずかしい格好を取ってしまった。一枝の頭では拒否しているが、身体は既にこの姿勢を覚えてしまった証拠だった。
「身体、身体がぁっ、はああぅ、ううっ、だめっ」
宏一の指は巧みに秘唇を刺激しながら秘核ぎりぎりを刺激し、一枝が少しでも腰を持ち上げると一瞬だけとろけるような感覚が湧き上がるような微妙な刺激を続けた。
一枝は何とか声だけでも抑えようと、枕をしっかりと握り締め、顔を押し付けて我慢していたので、宏一から見ると尻だけをだんだん高く突き上げる刺激的な姿勢になっていった。
「ほら、足を少し開いて、この方が安定するから」
宏一はそういうと一枝の両足を開いて突き上げられた腰をしっかりと固定した。
すでにたっぷりと口で愛された後なので、一枝の秘唇は綺麗に開いている。宏一はさらに指で秘唇のあちこちを丁寧に刺激しながら、一枝の一番喜ぶ場所を探った。
「ほら、ここも感じるかな?」
「ああん、恥ずかしいのぉ」
「こっちは?これもいいかな?」
「ああん、そんなに丁寧にされたらぁ」
「感じる?」
一枝は枕に顔をうずめたまま何度も頷く。
「それじゃ、ここはどうかな?痛い?」
「ああぁぁーっ、そこはぁーっ」
「ほら、こんなに大きくなって、尖ってるみたいだよ」
「そんなこと言っちゃいやぁ」
「痛くない?」
また一枝は頷いた。
「ここはどうかな?」
「そこはだめっ、まだいやぁっ」
「でも感じるでしょ?」
「分かんないっ、まだ入れちゃいやぁっ」
「一枝ちゃんのはまだ小さなスリットだね」
「いやぁ、嫌らしい。そこはまだだめなのぉ」
「こっちの方がいいの?」
「ああぁぁぁっ、はああぅぅ、ああんっ」
まず一枝には快感をしっかりと覚えこんでもらわなくてはこの先の開発がうまくいかないので、宏一はおねだりをさせるよりも感じさせることを最優先にした。何度も一枝が枕に声を染み込ませ、それでも我慢できなくなってくると、優しく肩の下に手を入れて上半身を持ち上げてやり、四つんばいの姿勢を取らせてから、先程は我慢していた下向きに尖った乳房を揉み込んでやった。
「ああぁぁぁぁっ、くううぅぅぅっ」
宏一に乳房を揉まれると、一枝の身体の中に吹き上がるような快感が巻き起こる。一枝は四つん這いのまま仰け反り、快感の大きさを宏一に伝えた。
「いい子だ。上手に感じられるようになってきたね」
そう言いながら宏一は秘核を刺激しながら乳房を交互に揉み続ける。
「こんなこと教えられたらぁ、ああぅぅ、宏一さん、上手すぎるぅ」
一枝はたっぷりと感じた後、再び顔を枕に埋めた。
宏一は一枝が思い通りの姿勢で感じていることに満足すると、このまま今日のクライマックスへと入っていった。
「いいかい、今度はそっと指を入れてみるからね」
「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、少し・・・、少し休ませて・・・」
一枝は感じすぎて少し息が苦しいようだ。しかしここで休憩すれば、またここまで意識と感覚が盛り上がるのに時間がかかる。宏一は一気に先に進むことにした。
何度も指先で確認してある一枝の小さな秘口に人差し指を宛がうと、ゆっくりと指を入れていく。
「あ、あ、あ・・・・、いやっ、痛いっ、だめえぇっ」
宏一の指が一関節ほど入ったところで指先が狭い部分へと辿り着き、その途端に一枝は痛みを訴えて身体を前へとずらして指から逃げようとした。しかし、宏一の左手がしっかりと一枝の太腿を押さえ込んでおり、前に逃げることができない。
「大丈夫、すぐに入るから。ほら、もうだいぶ入ったよ」
宏一の指先は一枝の中へと入っていき、狭い部分からその奥の温かい、複雑な形をした場所へと進んでいった。宏一の指の中程は痺れるくらい肉門に締め上げられていた。そして指先はそれほど強く締め付けられてはいなかったが、中はかなり複雑な形をしていて、簡単に奥までたどり着けそうな感じではなかった。だから指を入れていく時、何度か無理矢理押し広げる感覚があった。
「・・・・あ・・・・いた・・・・あぁっ・・・・」
宏一が表情を伺うと、一枝はじっとして何とか痛みに耐えようとしているようだ。
「ほら、半分入ったよ」
「まだ・・・はんぶんなの?・・・・」
「大丈夫、もうすぐだから」
一枝は生まれて初めて、身体の中を無理やり押し広げられる感覚を味わった。しかし、指先を入れた時ほど痛みは無い。宏一の指は一枝の肉壁にしっかりと挟まれ、だんだん押し込むのが大変になってきた。
「こ、宏一さん・・・まだ?」
「もうだいぶ入ったよ」
「まだ全部入らないの?」
「よし、これで殆ど入ったよ」
「くぅぅ、こんな・・・・奥まで入るの?」
「痛い?」
「少し・・・・痛い・・・ちょっと・・・・わかんない」
「少しこのままにしてるからね」
「はぁ・・・はぁ、はぁ・・・・う、動けないの」
「動かなくて良いよ。少しこのままの格好でいてね」
一枝は最初に指が入る時だけはキリッと痛みが走ったが、今は指を入れられた辺りがじんじんと痺れてはいるものの、思った程の痛みではなかった。これなら何とか我慢できそうだ。そして、今は痛みと同時に何とも言えない感覚が身体の中から生まれている。快感というのとは少し違う気がしたが、身体中に溢れていく、焦れったいような怠いような、そして少し甘いような不思議な感覚だった。そして、甘いような、とろけるような感覚が少しずつ大きくなっていく。
トップ |