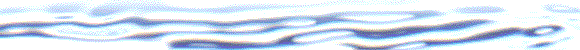「ねぇ、もしゆんから頼まれなかったら、こんなこと引き受けなかった?」
今度は宏一が心の中を見透かされたような気がした。
「そうだね、たぶん・・・・」
「私がそっと宏一さんに会いに行っても?」
「うん、断ったと思うよ」
「でも男の人は、バージンの高校生とか好きなんでしょ?」
「ずばり言うね。それはそうだけど、バージンはセックスの楽しみ方を知らないから、俺みたいに教えるのが好きな人は喜ぶけど、『痛がるばっかりで楽しめない』って言って嫌がる人だっているよ」
「そうなの?知らなかった」
「俺は一枝ちゃんみたいな子、好きだけどね」
「それだったら、いいんじゃないの?」
「でもね、それじゃ、聞きたいんだけど、単に裸にして無理やり入れてって言うだけなら、何も俺に頼まなくたって良かったでしょ?町に出ればいくらでもしてくれる人は見つかるよ。もしかしたらお金だって貰えるかも知れないし。どうしてそうしなかったの?」
「それは・・・、だって、あんまりじゃない。そんなこと・・」
「そうだろ?やっぱり、一枝ちゃんが納得できる人としたかったんだろ?」
「それは・・そう・・・うん」
「そのためには一枝ちゃんが納得できるように優しく、そっと、大切にってことになるんだけど、突然目の前に現れた女の子に『私を大切にして』って言われて、できる?」
「できない・・・」
「だよね。人を大切にするって、突然できるものじゃないから」
「そうか・・・」
「わかってくれた?」
「それじゃ、ゆんと一緒に何回か会って、それで私のことも少しはわかったとして、ゆんが反対してるのに私が押しかけてきたら?」
「う〜ん、そう言う状況なら引き受ける人はいるかもしれないけど、俺はダメ」
「ゆんが好きだから?」
「それもあるし、由美ちゃんと一枝ちゃんの仲が壊れちゃうのも嫌だし。絶対にばれるでしょ?そういうのは」
「そうね・・・」
一枝は少し寂しそうだった。今、自分を裸にして抱いている男の口からほかの女の子が好きだという言葉は、たとえ頭の中で理解していても聞きたくはなかった。一枝が寂しそうにしているので、宏一は少しだけ本音を言った。
「でもね、一枝ちゃん。男って言うのは、やっぱり可愛い女の子がいれば惹かれるものだし、手っ取り早く言えば裸にして自由にしたいって思うんだ。だから女の子は『男って絶対信用できない』って言ったりするけど、男ってそう言う物なんだよ。要はそのスケベな気持ちを使うかどうかってこと、かな?」
「よくわかんない・・・」
「だから、今の一枝ちゃんと由美ちゃんの関係だったら絶対にばれるから、いくら一枝ちゃんが言ってきても、由美ちゃんがダメって言えばダメだけど、もし由美ちゃんに絶対ばれないって言う関係だったら、正直に言えば由美ちゃんに内緒で引き受けたかもしれないね」
「そうなんだ・・・」
そう言われても一枝の心はすっきりとしなかった。やはり、由美に隠れてこそこそと会って抱いてもらうというところが引っかかる。『ありえない展開だけど、本当は由美から私に恋人を換えて欲しいのかな?』とも思ったが、それでも少し心の中に引っ掛かりができてしまう。そう思った時、『私、宏一さんに本気になろうとしてる』と気が付いた。
「俺、一枝ちゃんが好きだよ。一枝ちゃんは素直だし、可愛いし、魅力あるもの」
宏一は一枝を抱き寄せると、もう一度ゆっくりとキスをした。一枝も素直に求められるまま舌を絡めてきた。そのまま一枝の身体を引き上げ、宏一の上に被さる形で四つんばいの姿勢にさせ、優しく大きめの乳房を下から揉みながら、
「一枝ちゃん、それじゃ、そろそろ支度しないとね」
と言いながら可愛らしい乳首に舌を這わせた。一枝は頭の中に霧がかかってくるような感覚を覚えた。だんだん抱かれることしか考えられなくなってくる。
「ああん、宏一さん、言ってることとやってることがぜんぜん違うぅ。だめぇ、また気持ち良くなっちゃうぅ。これじゃぁ、服なんて着られないよぅ」
と軽く仰け反って乳房を宏一の方に突き出しながら再び喘ぎ始める。この姿勢では両手を使えないので、宏一が自分の乳房を揉んだり食べたりしているのを見下ろす事しかできない背徳的な姿勢なのだ。一枝はもうあと数秒続けられたら、服を着るのを嫌がるだろうと思った。しかし宏一は次第に乳房の愛撫を弱くしていくと、最後には一枝をベッドから下ろした。一枝は身体が火照ってきていたが、仕方なく、という感じでのろのろと支度を始めた。
宏一はベッドから降りると、素早く服を身に付け始めた。その様子からはもう、一枝との性の儀式は終わりだという気持ちが表れている。宏一に背を向けて身支度を整えながら一枝は、自分の身体に物足りないものを感じていた。まだ身体の中に炎がくすぶっている。なんとか普段の気持ちに切り替えなきゃ、と思うのだが、思えば思うほど宏一にもう一度愛して欲しくなる。そんな事を考えながら身支度をしていたので、結構時間がかかってしまった。一枝が制服を着始めた時、隣の宏一はすっかり身支度を整え、一枝の支度が終わるのを待っている。本当なら服を着終わってから『お待たせ!』とでもにっこり笑って軽くキスをしてから部屋を出ればよいのだろうが、身支度が終わった時、一枝の心の中には『このまま帰りたくない』という気持ちが渦巻いていた。この時の一枝には、先程宏一が一枝の反応を楽しもうと身体に中途半端に火を付けた事等全く気付いていなかった。
「一枝ちゃん、どう?支度終わった?」
宏一はそう聞いて、そっと一枝を抱き寄せると、素直に宏一の腕の中に飛び込んできた。そのままキスすると、一枝の目が潤んでおり、目が充血していることに気がついた。感じ初めの女の子によくあるパターンで、まだ身体のコントロールがうまくできないのだ。
「こ・・宏一さん・・・私・・・」
そういう一枝を優しく抱きしめ、もう一度ゆっくりとキスをしてやる。
「ああん、宏一さん、私の身体、なんか変なの・・・」
「大丈夫。最初のうちは誰でもあることだから。すぐに普通になるよ」
そう耳元で囁きながら抱きしめてやると、
「もう少しだけ、ちょっとだけ・・・お願い。身体が熱くて・・・このままじゃ帰れないの。お願い」
と一枝はあえぎながら言った。
「わかった。でも、時間が無いから・・・いい?」
「うん」
一枝はそう言うと、服を脱ごうとした。
「ダメ、そのままで良いからベッドに座って」
宏一はそう言うと、一枝をベッドに座らせ、そのままスカートをめくってパンツを露出させた。もし服と下着を脱がせてしまえば、また着る時に同じことになる。
「大丈夫。ちゃんと身体が納得するように感じさせてあげるから」
そう言うと宏一は、スカートの中に手を入れると、一気に一枝のパンツを脱がせた。
「あっ・・・」
一枝は驚いたが、時間が無いのだから仕方が無い。しかし、こういう格好でパンツを脱がされるのは、やはり恥ずかしかった。思わず足をぴったりと閉じて両手で隠してしまう。
しかし宏一は、優しく一枝の両手を外し、露になった一枝の茂みを眺めながらゆっくりと一枝の両足を開いて、膝を左右に高々と持ち上げていく。自然に一枝はベッドの上に寝る事になり、宏一の目の前には液体を湛えた一枝の中心部が丸見えになった。それは一枝にも分かっているはずだが、何も言わずに目をつぶってじっとしている。宏一が秘唇に顔を近づける。まだたっぷりと愛されてから時間が経っていないだけに、一枝の秘唇は綺麗に開いて宏一を待っていた。その中心の秘核はすでに十分膨らんでおり、尖って見えるほどだ。
「良いかい、時間が無いから、思いっきり夢中になるんだよ」
そう言うと宏一は、たっぷりと舌を使って一枝をいきなり快感の中心へと放り込んだ。
「んああぁぁぁーーーっ、はあああぁううぅぅぁあああぁぁーーーーっ」
一枝は突然頭の中が真っ白になり、声を上げることしかできなかった。すると、宏一の手が伸びてきて、制服の上から胸を揉んできた。一枝は夢中になる事しか考えていなかったので、制服の上からの愛撫では物足りなかった。声を上げて身体をくねらせながらも夢中で自分で制服のジッパーを下ろし、何とか背中に手を回してブラジャーのホックを自分で外した。
宏一は、マシュマロのようなふっくらとした乳房が突然手の中に入ってきたことに少し驚いたが、一枝がそれを望むのなら与えてやるしかない。両手で乳房を円を描くように揉み込みながら指先で乳首をコロコロと転がし、そのまま舌と口を使ってしっかりと一枝を感じさせた。
「はあああぁぁーっ、はううぅっ、くはあぁーーっ、あうううぅーーっ」
一枝は全ての恥じらいを捨てて夢中になって感じている。気が付くと、一枝自身は気が付いていないと思うが、宏一のリズムに合わせて一枝も腰を不器用に上下していた。
「ダメぇーーっ、こわれちゃうぅーーっ、だめよぉーーっ」
気持ちいい。とにかく気持ちいい。一枝は今の自分の格好も、時間の事も、全てを忘れて声を上げていた。宏一は頭を抑えられている事に気が付いた。最初、一枝の両手はベッドの上に乗ってシーツを掴んでいたはずなのだが、いつの間にか宏一の頭を両手でしっかりと掴んで自分から秘唇に押し付けていた。宏一は一枝のプリーツスカートが汚れないように気を遣っていたので一枝程夢中にはなれなかったが、一枝は制服を着ている事さえ忘れているように、大胆に身体を動かし、仰け反って感じ続けた。
やがて一枝の身体の反応がゆっくりと鈍くなってきた。どうやら身体が満足したらしい。宏一がゆっくりと両手と口の愛撫を終え、一枝の液体でべっとりと濡れた顔を上げて、ウェットティッシュで拭くと、一枝もゆっくりと身体を起こした。そして、何も言わずに乱れた服を直し、パンツを履いて身支度を調えた。
宏一が一枝の耳元で、
「これでいい?」
と聞くと、耳を真っ赤にして、
「ばか」
とだけ言った。
「大丈夫だった?」
「なにが?」
「壊れちゃうって言ってたから」
「・・え?・・私が?」
「うん。何が壊れちゃうって思ったのかな?」
「ごめんなさい・・よく覚えてないの・・・」
と恥ずかしそうに下を向いて小さな声で言った。
翌日の夕方、由美は心が落ち着かないまま部屋で宏一を待っていた。今日、学校で一枝は由美に何も言わなかった。先週は由美の方から何も仕掛けなくても思わせぶりな仕草を見せ、わざと由美に質問させ、それでも物足りなくて一枝から聞きたくもない事を聞かされたのに、今日は何も言わず、そぶりさえも見せなかった。それが由美には気になって仕方がない。もちろん、一枝と宏一がこの部屋でどんなことをしているのかは知っているが、どこまで行ったのか気になるのだ。あとどれくらい、こんな気持ちで待っていなくてはいけないのか、それが知りたい。あとどれくらいで、一枝が宏一の前からいなくなるのか、それが知りたいのだ。自分でこんな自分の気持ちを身勝手だと思う。もしかしたら、一枝に宏一の事を見せびらかしたかっただけなのかも知れないな、とチラッと思った。一枝には宏一の素晴らしさを教えてから『でも宏一さんは私のものなの』と言いたかったのかも知れない。由美は自分の心の中に、そんな気持ちがある事に気が付いて気が重かった。
さらに由美は、宏一を信じているからこそ、一枝の望みを叶えてあげようという気になったのだが、それでも宏一が一枝に本気にならないという保証はない。
「由美ちゃん、お待たせ」
宏一が入ってくると、由美は宏一の胸に飛び込んで行きたい気持ちをぐっと抑えて問題集に集中した。そのまま宏一を抱きしめてベッドに飛び込みたい、という気持ちが一瞬だけ由美の心の中で沸騰したが、宏一が抱きしめてくれるまでじっと待つだけの余裕が由美にはあった。
トップ |