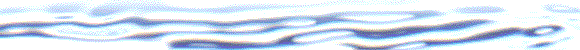「宏一さん、どうでした?」「え?うん、何とか問題なさそうだよ。大丈夫」
「そうですか」
宏一の予想とは異なり、友絵は少し沈んだ雰囲気で答えた。宏一は少し不思議に思ったが、六本木にできた大きなビルの中に入っている店に予約の電話を入れ、二人分の席をリザーブした。それを友絵がじっと見ている。何か言いたそうな雰囲気もあるのだが、別の事を考えているようでもあり、宏一はさほど気にせずに予約を入れていった。
宏一が予約を終えて、
「新藤さん、予約、終わったよ。いつ出られる?こっちは5分で準備ができるけど」
と言うと、友絵はあわてて仕事を片付け始めた。
「ごめんなさい。すぐに終わらせます」
友絵は集中力を復活させると、どんどん仕事を仕舞いにかかった。机の上に出ていた書類に整理のタグを付け、次々に仕舞っていく。もちろん、仕事のきりの良いところまでやってから仕舞うので、宏一よりは遅くまでかかり、二人が会社を出たのは7時を少し回った頃だった。
宏一はタクシーを拾って友絵を押し込み、ビルの名前を告げると、
「お疲れ様でした。友絵さん」
と言った。
「ごめんなさい、宏一さん。少し間に合わなかった・・・」
「偉いよね、友絵さんは。とにかく時間を守るように全力を傾けるもの。メーカー系の人は時間にうるさいのが普通だけど、商社系の人で時間をきっちりと守る人って意外に少ないよ」
と友絵を褒めた。
「そうですか?でも、工事って時間で区切られてるから、どの業者さんも時間の感覚が凄いじゃないですか。私なんて、普通だと思うけど・・・」
「そう?友絵さんは優秀だし、時間は守るし、おまけに・・・」
「え?なんですか?そのあとは?」
「ううん、それは後でのお楽しみ、にしておこう」
と宏一がニヤッと笑うと、
「なあんだ。宏一さん、そんなもったいぶって」
そう言いながら友絵も笑っているところを見ると、友絵もある程度は分かっているようだ。
二人を乗せた車は少し混んでいるところにさしかかったようで、少し動いては泊まっている。友絵は思い切って宏一の横にくっつくと、宏一の肩に頭を寄せて目を閉じた。つかの間の幸せ、そんな言葉が脳裏をよぎる。今はその小さな幸せが友絵にとって大切だった。
やがて車は六本木を通り、話題の大きな再開発地域に着いた。タクシーを降りると、
「うわぁ、凄いところ」
と驚きの声を上げた。確かに東京でもここまでセンスの良いところは少ない。
「友絵さんは何回か来た事あるのかな?」
「いいえ、こんな所、私のお給料じゃ無理です。そんなところに来ても、悲しくなるだけだもの」
「でも、カフェとかランチとかだったら手軽に楽しめるんじゃない?」
「う〜ん、でも、やっぱり私の世界じゃない。せっかく欲しいものが見つかっても我慢しなきゃいけないなら来ない方が良いし、お財布と相談して安いもので間に合わせるなんてしたくないから。それに宏一さんと一緒じゃなきゃ、私、浮き上がっちゃいます」
「友絵さん程美人なら絶対そんな事無いと思うけどなぁ」
「宏一さん、お上手ですね。ありがとうございます」
「それじゃ、今日は俺と一緒だから、いっぱい楽しんでいこうね」
「はい。宜しくお願いします」
「どう?少し散歩してからレストランに行く?散歩するのにちょうど良い設計になっているそうだけど?」
「ううん、今日は真っ直ぐレストランに行きましょう。ゆっくりとお散歩してみたい気もするけど、今からじゃどのみちそんなに時間、取れないし。今はそう言う気分なの」
「そうか。それじゃ、真っ直ぐレストランに突撃だ」
宏一は併設されているホテルに入ると、6Fにあるグリルに友絵を案内した。席に案内されると友絵は、
「うわぁ、素敵なレストランですね」
とホテル内のレストランとは思えない開放感に大喜びだった。窓の外には広いカフェのエリアが広がっているので、6Fとは思えない感じがする。また中は高い天井の上まで大きなガラスで一面を全て被ってあり、広い空間を贅沢に使ってゆったりとテーブルを配置してあるので、混んでいても話し声でうるさいなどという事はなく、プライベートな時間を楽しみたいカップルには最適なレストランだ。
席に着くと宏一は、
「お肉を食べたいって言うからここにしたんだけど、友絵さんの好みに合うかな?少しヘビーだよ」
「大丈夫。今日はとってもおなか、減ってるんです。絶対に全部食べられます。断言できます」
「それはよかった。横浜のときもそうだったけど、ここのレストランも一皿を二人で分けて食べるのは大歓迎なんだ。いろいろ食べようね」
「はい。うれしいな。何にしようかな?」
友絵は無邪気にメニューを見始めた。この無邪気さが友絵の魅力だ。宏一は、この無邪気さを大切にしてあげようと思い、なるべく軽い感じで話しかけた。
「ここのお勧めはやっぱりグリルだから、他のものは少なめにして、お肉をいっぱい食べた方が良いよ。凄い量なんだから」
「宏一さん、そんなに脅かさなくても良いですよ。ちゃんと考えますから」
「うん、あんまりコースの組み立てにこだわらない方が良いと思うんだ」
「コースの組み立てって言われても・・・そんな事、考えてないのに・・」
友絵は少し困った様子でメニューを見返した。友絵は『美味しそうかどうか』を見ていただけで、宏一のように食事を流れとして捉え、皿から皿への変化を予想するなどという事は頭にも浮かばないのだから。友絵は少し気分が落ち込みそうになったのをちょっと我慢して気分を変えると、
「それじゃ、宏一さんがまず決めて下さい」
とにっこり笑って言った。
「そうか、そうだよね。ちょっと貸してみて」
宏一はメニューを手にすると、素早く目を走らせた。実はこのレストラン、価格設定にトリックがあり、食事そのものはこれだけ一流の店の割には余り高くない、と感じるようにできている。と言ってもコースにすれば一万円では利かないが。しかし、ちょっと洒落たワインに手を出すと一万円札がどんどん出て行ってしまう。食事がヘビーなものになりがちなので、食事中には予想以上にワインが進む。ワインリストを眺めた途端に後悔しないためには、思い切って1万円以下の安いワインの中からチリ産やアルゼンチン産の良いものを選び出すワインの知識が必要だ。
宏一は前菜に「ホタテとハーブのレモンバターソース」、スープに「カボチャとリンゴのスープ」、そしてメインに「十勝のサーロイン」を選び出した。
「さぁ、友絵さんはどうしますか?」
「・・・・・・・・・・・困った」
「友絵さん、俺が選ぼうか?」
「宏一さん、そうやって宏一さんに甘えてばっかりだと私、どんどん頼っちゃいます。もう少し時間を下さい」
「それは良いけど・・・・」
宏一は真剣にメニューを見て、メニューに穴が開くんじゃないかと思うくらい真剣な友絵を眺めながら、いつものホワイトワインスピリッツァーを頼んだ。友絵は見ていて気の毒になるくらい、何度も何度も考え直しているようだった。まるで、仕事をしている時の友絵のように、いろいろ考え、調べ直し、修正し、判断している、と言う感じだ。
「友絵さん・・・」
「待って、もう少しだけ」
「はい・・・」
友絵の気迫に思わず押されてしまった。後は静かに友絵が結論を出すのを待つ事にする。
友絵は必死になってメニューに書いてあるものを想像しようとしていた。しかし、例えばアスパラガスのサラダなど、どうしてこんな値段になるのか不思議なくらい高く感じてしまう。それでも宏一が静かに友絵が選ぶのを待ってくれているので、どうして良いか分からないけれどもそれなりに答えを出してみようと思い、
「宏一さん、聞いてもいいですか?」
と切り出した。
「いいよ。なあに?」
「クラブケーキって、興味があるんですが、どんなケーキなんですか?」
「あぁ、カニの身をほぐして味付けして円形の型に入れたものだよ。ケーキって言うけど、小麦粉を入れたあのお菓子のケーキとは何の関係もないよ」
「良かった。それじゃ私、それにします」
「スープやメインは?」
「スープは宏一さんから一口貰って良いですか?」
「もちろん」
「それで十分です」
「メインは?」
「アンガスビーフって言うのにしたいんですけど・・・」
「へぇ、それは凄い」
「そんなに大きいんですか?」
「そんな事はないけど、日本では大きいね。女性が食べるには」
「変ですか?」
「まさか。大丈夫。それじゃぁ注文しようか」
宏一はウェイターを呼ぶと、それぞれの料理を注文した。ウェイターは友絵がアンガスビーフを注文しても何にも言わなかった。友絵は何か言われるかと思ってドキドキしていただけに、そこで初めてホッとした。
「焼き加減は、勝手に注文しちゃったけど、あれで良かったかな?」
「ええ、宏一さんに任せた方が良いもの」
「ありがとう。アンガスビーフはグレインフェッドって言って、穀物を食べさせて太らせるための肉牛なんだけど、日本の和牛よりは赤みが強いんだ。だから、余り生っぽくするよりはミディアムくらいの方が美味しいんだよ。和牛の方は脂身が多いからミディアムレアー位にして、タタキ感覚にした方が美味しい場合が多いけどね」
「それで宏一さんの方はミディアムレアーなのに私のはミディアムなんですね」
「そう言う事。赤身が美味しい牛肉って、日本ではほとんど手に入らないから、友絵さんの選択はかなり玄人っぽいと思うよ。でも心配しないで。脂っこい和牛よりも簡単にお腹に入っちゃうから」
「良かった。私、焼き方を宏一さんに決めて貰ったのは嬉しいんですけど、どうしてそうなったのか聞いても良いかなって思ってたんです」
「どんどん聞いてよ。せっかく二人で食事してるんだもの、我慢してみても仕方ないでしょ」
「そうですよね。昼食だって、いつも二人で食べられる訳じゃないし」
「そうだよね。友絵さんはいつも忙しいからね」
トップ |