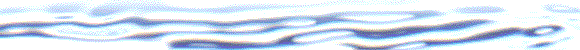友絵は週に二度、宏一と昼食に行く。それは大抵、月曜と水曜で、それ以外の日は宏一が暇そうにしていたとしても誰か他の課の女子を誘って一緒に出て行ってしまう。友絵にしてみれば、宏一と一緒に毎日でも食事に行きたいという気持ちはもちろんある。しかし、突然宏一と二人だけの職場に配属されたので、他の女性社員から除け者にされないように気を遣わなくてはならず、その結果が週に二回だけの昼食になったのだ。これ以上回数を多くすると宏一を独り占めにして周りへの義理を欠いていると言われかないし、これよりも回数を少なくすると不自然になってしまうと言う、ギリギリの設定なのだ。もちろん、他の女子社員の中には週に一度も自分の課の人と食べに行かない、と言う子もいるが、友絵はあくまでも『ちゃんと義理程度は果たしています』というスタンスなので、周りも納得しているようだ。更に宏一と食事に出る時でも、二人は意識して会社の近くの他の女子社員が行くような店を選んでいる。宏一は『そこまでしなくても』と思うのだが、友絵にしてみれば気を遣いすぎるという事はないらしい。おかげで社内での宏一の人気は未だ衰えず、と言ったところだ。「どう?友絵さん、他の女性から虐められてない?」
「今のところは大丈夫みたいです」
「よかった」
「本当はもっと一緒に昼食に出たいんですけど、ごめんなさい」
友絵はそう言って頭を下げながら、その心の裏では『私も宏一さんが好きだし、宏一さんも私を好きでいてくれるからこんな事が言えるんだ』と密かに喜んでいた。
「ううん、友絵さんが喜んでいてくれるなら、それでいいよ」
「私だって別に喜んでいる訳じゃないですよ」
友絵はちょっとだけ拗ねて見せた。
「ごめんよ。そんなこと・・・・ただ」
「分かってます。でも、やっぱり週に二回くらいにしておかないと。それに遠くにはまだ出れそうにありませんね」
「そんなに注目の的なの?」
「凄いんですよ。私のやってる仕事、たぶん他の女子は全部知ってますから」
「ええ?どうして?」
「私が全部話したから。白状させられたんです」
「昼食の時に?」
「そう、凄いでしょ?」
「でも、どうして?」
「わかんないけど、きっと先輩の誰かが私の代わりに宏一さんの所に来ようって思ったんじゃないですか?遅くなって日付を超える事もありますよって言ったら、思いっきりびびってましたから」
「そりゃそうだよね。大変な仕事だよ、女の子には」
「それだけじゃないんです。確認を取ったみたいですよ」
「確認????」
「私がそれだけ仕事をしているのかって言う・・・」
「どうやって?」
「人事の女の子に記録を調べさせたみたいです」
「会社の出勤と退勤の記録を?」
「そうみたい・・・」
「そこまでするのかね?凄いや・・・・・」
「ですよね?」
「どうしてそこまでして、俺と仕事したいのかな?忙しいばっかりで楽しいとは思わないけどなぁ」
「それはですねぇ、たぶん・・・・」
友絵はいったん言葉を切って、しばらく考え込んでから話し始めた。
「確かに宏一さんに人気があるのは確かです。みんな狙ってるんです。でも、それと職場とは別です。私のポジションをみんなが狙ってるのは、宏一さんが素敵だからよりも・・・・上司が居ないからです・・・たぶん」
「上司が居ない?」
「今の決まりでは、一応宏一さんが私の上司になってますけど、それは臨時のものだから」
「そうか、俺は友絵さんに人事の点数を付けるわけでもないし、給料を決めるわけでもないものね」
「そうです。そしてあの部屋には宏一さん以外に上司が居ないでしょ?」
「そうか、業者はたくさん出入りするけど、仕事の評価には関係ないから・・・か」
「そうです」
「俺の事を適当にあしらっておけば、仕事は適当にこなして自分の好きなようにできるって思ったのかな?」
「そうじゃないですか?」
「友絵さん以外に、あれだけこなせる人はいないと思うけどな」
「甘いですよ」
「え?」
「宏一さん、宏一さんだから言いますけど、先輩なんて、仕事をたくさんこなそうとは考えていない人ばっかりですから」
「だって、そうしないと片づかないよ」
「そうです。その分は宏一さんがやるんですよ」
「ええっ、友絵さんのやってる分まで?」
「もちろん、二人しかいない職場ですから」
「そんなの無理だよ。それなら増員して貰わなきゃ」
「同じ様な先輩が増えるだけですよ」
「そんなぁ、やっぱり友絵さんは大切にしなきゃダメって事だね」
「そうなんです。二人だけの職場でいるためには、ね?」
友絵はちょっと誇らしげに笑った。
「友絵さんはどうなの?」
「え?」
「あの職場にもっと居ても良い?」
「もちろん、私は良いですけど・・・」
「『ど』ってなあに?はっきりしないね」
「それは・・・・・」
友絵は少し言葉に詰まった。
「言って欲しいな。お願いだよ」
「でも・・・・」
友絵は何かを良い難そうにしている。しかし、そこまで仄めかせるのなら、宏一は聞きたくなる。
「どうしたの?言えないの?」
宏一は更に念を押すように言った。すると友絵は心を決めたようで、顔を上げると思い切って言った。
「だって、宏一さんはいつも上司で居てくれないから・・・・」
友絵は前回と同じスピリッツァーを飲みながら、少し恥ずかしそうに、そして少し不満そうに言った。月曜日のことを言っているのだ。
「あ・・・ごめん。だって、可愛らしくて・・・」
「それが上司らしくないんです」
友絵はそう言いながらも、宏一だから言えるのだと思った。
「部屋では絶対に上司と部下で居ないと、とんでもない事になります。宏一さんはウチの会社に数ヶ月しか居ないから気楽に考えているのかも知れないけど、社員の私には大きな問題なんです。もしばれちゃったら・・・・」
「ごめんなさい・・・」
宏一は一気に元気を無くしてしまった。友絵に言われたのが特にショックだった。友絵に『遊び気分で手を出さないで』と言われたみたいで、余計に気が重くなった。
「ごめんなさい」
宏一はもう一度、友絵に謝った。
「ちゃんと部下を持った事が無くて、初めて持った部下が友絵さんだったんで舞い上がっちゃったんだ。友絵さんがそんなに迷惑だと思ってたなんて知らなかったよ」
「もう良いです」
「ほんとうにごめんなさい」
「良いですって・・」
「はい・・・ごめんなさい」
友絵は宏一が何度も頭を下げてきたので、少し可哀想になった。確かにあの日、応接セットで感じさせられて宏一を受け入れてしまったのは自分でも大きなショックだった。友絵も嫌がったのは最初のうちだけで、途中からは宏一にされるがままになってしまい、最後は自分も求めていた。あの日の出来事があってからしばらくの間は、自分の仕事のスタイルを自分で壊してしまったような気がして気が重かった。自分で大切にしたいと思っていた宏一との二人だけの部署なのに、それを自分で壊してしまったような気がしたのだ。友絵にとっては会社で自分が女になると言うのは、初めてではないにしても、やはりとても後悔する事に違いはなかった。
実は友絵の心の中は、もっと複雑だった。いつも周りを気にして上手に調整している自分に満足している部分もあるのだが、一方ではそこから逃げ出したいと思っている部分もある。あの時の宏一は友絵のそう言う微妙な部分を上手く突いてきたので、友絵もつい乗せられてしまった。いつの間にか自分が夢中になり、宏一を応接セットで受け入れてしまった時、心の中ではいけない事だと思っていても、宏一に開放されたいと思っていた自分が身体を支配していた。宏一が入ってきた時、身体中を走り抜けた背徳の快感は凄まじいものだった。決してあの時の感覚は忘れられるものではない。その快感が忘れられずに何度も宏一を欲しがりそうな気がして、自分が怖かった。
それに、宏一には他に女性がいることを友絵は承知している。頭の中では分かっているのだが、ふと宏一がその女性から離れて自分へと移ってきてくれないかと願ってしまう。最近は特に独占したいと言う気持ちが強くなってきている。宏一に確かめたいという気持ちもあるが、友絵の女性としての感覚は『それをやったらお終いになるわよ』と言っている。こんなにも自分を大切にしてくれて、支えてくれる宏一だからこそ、自分が独占したいと思ってしまう。それ程宏一のことが好きなのに、自分でもなぜそう思うのか分からないのだが、友絵の女としての感は今、宏一に『私だけと付き合って』と告白する事を許してくれないのだ。
『今日もまたホテルに誘われるのかな?この素敵なホテルに部屋を取るのかな?明日のことを考えたら泊まるなんて無理なのに。それに今日は私・・・・・』そんな風に思うとやりきれなくなってくる。『それだけで十分て言ったのは私なのに・・・宏一さんの全てが欲しくなったの?もう結婚したいの?わかんないよ・・・・』友絵の心の中ではいろんな自分が声を上げていた。
「どうしたの?怒ったの?」
宏一が黙り込んでしまった友絵に、済まなそうに声を掛けてきた。
「え、ごめんなさい。ちょっと考え事をしちゃったみたい」
友絵は慌てて繕った。宏一が悪いわけではないのだ。
「ちょっと、あの時の事を考えちゃった」
「あの時っていうと・・・・?」
「応接セット・・・・」
「ごめん!本当に」
「良いんですよ。私だって同じなんだから」
「同じって?」
「もう、そんな事言わせないで下さい」
「わかった」
ちょうどタイミング良く前菜が運ばれてきて、二人はしばらく食事に夢中になる事ができた。友絵のクラブケーキは、見た目よりも味が繊細でとても美味しかった。友絵は『私、宏一さんを本気で好きになったみたい。本気で恋してる』と自分に話しかけていた。『のめり込むの?他に女の子がいるのを知ってて。それとももう宏一さんと別れるの?』と問いかけると、即座に『絶対イヤ』と答えが返ってくる。それははっきりしていた。運ばれてきた白のハウスワインをゆっくりと口に含みながら、『それでもまだ宏一さんは私にとって必要なの。宏一さんの横にいれば私は元気になっていけるから』と自分に言い聞かせていた。
トップ |