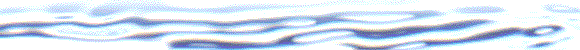そう考えながらゆっくりと口に運んでいるクラブケーキに混ぜ込んであるキュウリの歯ごたえが素晴らしい。友絵の意識を押しのけるかのように、特製のソースの香りが口の中で広がっていく。『これ以上宏一さんを好きになると、別れる時が辛いわよ』と分かり切った質問をしてみると、『それでも良いの。今は宏一さんの側にいたいの。それで良いの』と答えが返ってくる。グラスで取った白ワインを口に含み、ワインの香りがカニやキュウリやソースの香りを流し去り、ふくよかな果物の香りで意識がすっきりとする。そして友絵は再びクラブケーキを口に運んだ。複雑で繊細な味が再び口の中に広がる。友絵は目の前にいる宏一に微笑みかけ、「宏一さん、美味しいですよ。良かったら一口いかがですか?」
と言うと、宏一はナイフとフォークを伸ばしてきて、上手に一口分だけ切り取っていった。
「あ、美味しい。本当だ。こんなクラブケーキ、なかなか無いよ。良い選択だね。俺のホタテも悪くはないけど・・・食べてみる?」
そう言って大きめのホタテを半分切り分けると、友絵の皿に分けてくれた。
「うわぁ、ラッキー」
友絵が小さな声を上げてホタテを口に運んだ。確かにクラブケーキ程美味しくはないようだったが、友絵にはホタテの味などどうでも良かった。宏一が自分のために切り分けてくれた事が嬉しかった。友絵の身体の奥深い部分がゆっくりとやがて始まるであろう二人の儀式のために準備を始めた。
しかし、身体の反応とは裏腹に、友絵の気持ちはまだ乱れていた。今日は宏一の誘いに乗れないのが残念で仕方なかった。
「友絵さん、あんまり食べない方が良いよ。メインはずっとボリュームがあるんだから」
宏一はニコニコしながら友絵がホタテを切り分けて口に運ぶのを楽しそうに見ている。その宏一の視線に包まれているだけで友絵は心が安らぐ。
「宏一さん、今日の私はお腹が減っているんです。覚えてます?」
「もちろん。でも、ねぇ????」
友絵はフォークを止めて宏一を見上げた。
「そ、そんなに凄いんですか?」
「だって、グラム数は見たんだろ?」
「え・・えぇ・・・たぶん・・・よく分かんない・・・・かも・・・???」
「そう、まぁ来てみれば分かるよ」
宏一がそう話している間にスープが運ばれてきた。
「それが『カボチャとリンゴのスープ』なんですか?」
「そうみたいだね」
「甘いんですか?」
「え?ちょっと待って・・・全然甘くないよ・・・・いや、少しだけ甘いかな?」
友絵は宏一からスープを貰って驚いた。
「え?これがカボチャとリンゴのスープ?もっとお菓子っぽい味がするって思ってたのに」
「そうだよね。良くできてるね」
「とっても美味しいです。これなら料理にも合うし」
「もう少し飲んでみる?」
「少しだけ・・」
「美味しい?」
「はい、すごく美味しいですね」
本来なら少し時間を掛けて楽しむところを、二人であっという間に飲んでしまったので、メインが来るまで少し時間が空いた。そこで宏一はワインリストを貰ってアルゼンチンの赤ワインをフルボトルで注文した。やがてワインが運ばれてくると、友絵は目を輝かせて言った。
「何か、いよいよだぞって感じですね」
「どうして?」
「だって、スープも飲んだし、ワインも準備完了だし、お腹もまだ余裕あるし」
「何か友絵さんの話を聞いてると工事の段取りをやってるみたいだね」
「ここでそんな話、しないでください、宏一さんたら」
「ごめん、ごめん。何か今日は友絵さんに謝ってばっかりだなぁ」
「そうですね」
「何か俺、だらしない感じに見えるかな?」
「いいえ、そんなことはないです。良い気分ですよ」
「『良い気分』なの?」
「そうです。上司が謝ってくれるなんて珍しいことでしょ?」
「ここでそんな話、しないでよ」
「ははははは、上手ですね、宏一さん、ははははは」
友絵は声を上げて笑った。ちょうど二人のメインが運ばれてきて、友絵の目がまん丸に開いて皿に釘付けになる。今までの笑い声は驚きに変わった。
「こ、宏一さん・・・これ・・・」
「そんな驚くほどの大きさじゃないだろ?」
「だって、厚さがすごいですよ、こんな厚いお肉、見たこと無い。平べったくないお肉なんて・・・これ、塊みたい」
「冷めないうちに食べようね。今日のお肉に乾杯」
「はい、乾杯。何なんですか、お肉にって?」
「友絵さんを驚かしたアンガスビーフは偉いって事かな?」
「確かに・・・・すごいです。このお肉」
「食べられるんだよね?確か」
宏一がさらりと意地悪を言う。
「自信が無くなってきました」
「とにかく食べよう。楽しまなきゃ」
宏一は十勝牛でかなり脂の乗った肉だが、友絵の方は赤身の部分があっさりとしていて食べやすい。日本ではミディアムのステーキを頼んでも、下手をすると真ん中が冷たいものを平気で出してくる店があるが、さすがにこのクラスの店ともなるとステーキの火の通し方は絶妙だった。宏一のミディアムレアーの肉でもしっかりと中は暖かくなっている。脂の乗った肉で中が冷たいときの悲惨さは言葉で表せるものではない。
友絵は『さぁ、食べるぞ』と気合いを入れると、ナイフで切り分けて食べ始めた。切るのに少し力がいるが、噛みしめればどんどん味が出てくる。『美味しい。これ、赤身なのに柔らかい。それにあっさりしてる。でも、全部食べられるかな?がんばるぞ!』確かに日本の肉とは違ってあっさりとしているのに柔らかくて美味しい。和牛の味は脂っこい味で、時々しつこすぎると思うことがあるが、これはそんなことは全くない。友絵があまりに一心不乱にステーキに挑戦していたので、宏一は言葉を掛けるのが気後れしてしまった。ふと友絵が気がつくと、
「どうしたんですか?」
と聞いてきた。
「何か、すごく真剣に食べてるから、『神聖な戦い』って感じで話しかけにくくてさ。どう、美味しい?」
「すっごく美味しいです。こんな美味しいお肉、初めて食べました。宏一さんも一口、食べてみますか?」
「ありがとう。でも一口で良いよ」
「たくさんなんてあげませんよ。とっても美味しいんだから」
「それは良かった」
そうは言っても、友絵はかなり大きく一切れを切って宏一の皿に入れてくれた。宏一もお返しに十勝牛を友絵から貰ったのよりも小さく切って友絵の皿に入れた。これなら友絵がステーキを全部食べるのをじゃましたことにはならないだろう。
「何か、もしかしたら全部食べられるんじゃないかって気がしてきましたよ」
「友絵さんが、全部?いくら何でもそれは」
「宏一さん、私を甘く見ましたね」
「そんなことは、ありません・・・絶対に・・・」
「きっと食べられますから」
そう言いながらも友絵は更に一口ステーキを頬張った。宏一も負けじと自分のステーキを食べることにする。
十勝牛のステーキは、所謂「和牛のステーキ」で、口の中に入れるとしゅわっと解けてしまうような豊富な肉汁が持ち味だ。友絵のステーキは食べ続けていると顎が疲れてくるが、十勝牛はナイフすらいらないのではないか、と言うくらいに柔らかい。少し生っぽく上手に焼いてあるので、赤身の部分の味も少しは楽しめた。
「宏一さんのお肉も美味しいですね」
「うん、『和牛』って味だよね」
「宏一さんはどっちのお肉が好きなんですか?」
「そうだなぁ、どっちかって言うとアンガスビーフかな?赤身の味が良いから」
「私も絶対こっちです」
友絵はワインをぐっと飲むと、両手にナイフとフォークを握りしめ、再び神聖な戦いに戻っていった。
宏一は友絵が心から食事を楽しんでいるのを見ながら、『今日食事に誘って良かったな』と思っていた。この天真爛漫な笑顔は会社では見ることのない、とてもプライベートな笑顔だ。宏一は食事の後、友絵をこのホテルの部屋に誘うつもりだった。泊まることはできないかも知れないが、友絵のもっとプライベートな部分を手で確かめたかったし、宏一だけが聞ける喜びの声を上げさせてみたかった。もし友絵が同意してくれれば、二人で朝を迎えてからタクシーを走らせても良いのだ。そう思うと、無邪気な笑顔でステーキを頬張っている友絵が可愛くて仕方なかった。
「友絵さん、本当に全部食べちゃいそうだね」
「そうでしょ?だって、美味しいんだもの」
「美味しいのは分かったけど、レディスサイズのステーキの倍はあったと思うよ」
「倍以上かも知れませんね」
「たいしたもんだ」
「尊敬します?って違うか」
友絵はけたけた笑った。そんな会話をしているうちに、友絵はステーキを平らげてしまった。もちろん、宏一の方はさっさと十勝牛の皿をすっきりとさせてある。
「あー美味しかった。と言っておこう」
「なに?それ?」
「特に意味はありません。ふふ?」
友絵は付け合わせに頼んだアスパラガスの残りをゆっくりと食べながら、お腹いっぱいになった幸せを感じていた。お腹だけでなく、今は心もいっぱいな感じだ。『ワインが回ったのかも知れないな』そんな気がした。
宏一はそろそろ話を切り出す頃合いだと思った。
「ねぇ、友絵さん」
「何ですか?」
「これから部屋を取っても良いよ?それとも、もう少し飲むのにバーにでも行く?」
宏一は友絵が部屋を選んでくれることを願いながら、友絵の返事を待った。雰囲気はよいのだから、宏一が部屋を取ってきても不思議はないはずだ。『宏一さんにお任せします』と友絵が言うのをじっと待った。
しかし、宏一の予想に反して友絵はしばらく何も答えなかった。友絵の表情が宏一の望み通りに行かないことを語っている。こうなれば、ほとんど答えは決まったようなものだ。しかし、宏一としては確かめざるを得なかった。
「友絵さん・・・・」
「宏一さん、今日は令子が来てるんで、帰らないといけないんです。それに、部屋に行ってたら時間が遅くなっちゃうから。ごめんなさい。今日は食事だけで帰ります」
済まなそうに言った友絵の言葉は宏一の頭の中にうつろに響いた。予想外のかなり大きなショックだ。しかし、余りがっかりしていることを友絵に悟られると、友絵が可哀想だ。無理に気持ちを切り替えると、
「そうか、それじゃぁしかたないね。バーもダメ?」
と、もう一度だけがんばってみた。
「ごめんなさい。一緒にお酒を飲んでると、帰りたくなくなりそうで」
そこまで友絵が言うのだから、きっと大切なことがあるのだろう。
トップ |