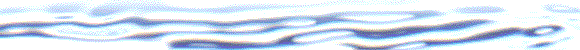いつしか夕刻になり、海岸を列車は走っていた。由美は宏一の
上で腰を動かしながら激しい息をしていた。
「由美ちゃん、そろそろ夕方だね。夕日が射し込んできているの
かな?」
宏一は腰の動きを由美にあわせながらカーテンを開けた。
「あっ、いや、宏一さんカーテンを閉めて下さい」
あわてて宏一に抱きついて窓の下に身体を隠そうとする。
「大丈夫だよ、このあたりは線路の海側に家なんてないから。夕
日が綺麗なはずだよ、そっと体を起こして覗いてごらん」
列車はちょうど富山県を抜けて新潟県を走っていた。由美はおそ
るおそる顔を上げ、窓の外に広がる雄大な景色に驚いた。
「綺麗、海が夕日でオレンジに染まってる、空も。雲が金色に輝
いて、素敵」
思わず腰を止めて窓の外の景色にうっとりとする。
「綺麗だろ、由美ちゃんの身体も夕日に映えてオレンジになって
るよ、とっても綺麗だよ」
宏一は由美の腰を両手で起こして騎上位の体勢にした。外に家が
ないことを知った由美はもういやがらなかった。
「綺麗、でも、気持ちいい、宏一さん、景色を楽しめません、
あーっ、夕日が沈んでいきます。海が光って、ルビーみたい・・
・、ああっ」
由美の腰の動きは円を描くように宏一の腰の上で揺れている。宏
一の肉棒は全て由美の中に飲み込まれ、肉棒の先端にコリッコリ
ッとしたものが当たっているのが分かる。肉壁の締め付け具合は
少しきついが中程のぶつぶつした部分が程良く擦りあげるので宏
一にはちょうど良かった。
「あうっ、宏一さん、オッパイも、私のオッパイも、早く、して」
由美は手を伸ばして宏一の両手を胸の導く。上体を少し起こして
両手で乳房を軽く下から支えてやると、
「イヤン、もっと、揉んで、ああっ、ダメ、いっちゃいそう、お
願いです、早く、ううっ、はうっ、いっちゃいそうです」
由美はもう持たないことを悟ると、宏一の両手を乳房に押し当て
て腰を振った。宏一が両手の人差し指と中指の間に乳首を挟み、
そのまま揉みたてていく。
「ああーっ、きれい、夕日が、沈んでいきます。あっ、エメラル
ド色、ああーっ、もう、いくっ、ううっ、うっ」
由美は一度伸び上がり、一瞬硬直するとゆっくりと宏一の上に崩
れてきた。白い肌に夕日が映り、妖精のようだった。
そのまま二人は夕食の時間まで眠った。宏一が目を覚ますと目
の前5センチくらいのところに由美の寝顔があった。あどけない
寝顔は少女のままだ。
「由美ちゃん、そろそろ夕食の時間だよ。起きなさい」
優しく由美の耳元でささやくと、
「ん・・・、寝ちゃったんですね。ごめんなさい・・・、今、支
度します」
眠そうな顔でゆっくりと起きあがると、身支度を始めた。
宏一は由美の眠そうな顔を見ながら、もう少し寝かせておいて
あげたいと思ったが、夕食の時間は予約制なので自分で変えるわ
けには行かないのが残念だった。
ダイニングカーにいくと、途端に由美は目を覚ました。
「わぁ、素敵、有名なレストランみたいですね。電車の中にこん
な所があるなんて」
と、目を輝かせている。実際には中級のレストランでもこんな内
装にはなっていないが、うまく高級感を出している。
夕食は切符の予約の時に頼んであるコース料理なので、飲み物
だけを注文すればよい。内容を考えると少し高めかな、と思った
が、まあまあの内容である。因みにこのコース料理は時刻表にも
載っている。
由美はそんなことはお構いなしに、シアタービレッジの話や京
都駅での買い物の話など、次から次へと宏一に話しかけてくる。
『やっぱり旅行に連れてきて良かったな』
宏一は満足した。由美を非日常環境に置くことでいつもの性格と
は違うものを引き出せたようだ。食事もメインコースが出た後で
だいぶリラックスした気分になってきた。
「由美ちゃん、少しお酒を飲んでみるかい?」
「えっ、いいんですか?どうしようかな、せっかくの旅行なんで
すから少しだけ飲んでみようかな?」
「何を飲みたいの?カクテルがいいのかな?」
「あの・・・、ブランデーを飲んでみたいんですけど、いいです
か?」
「いいけど、大人っぽいもの飲むんだね」
「あの、好きな小説の中に夕食の後にブランデーを飲むシーンが
あるんです。前に父に飲ませてもらったこともあるんですけど、
そのときは苦いばっかりで少しも美味しくありませんでした。で
も、今なら少しは分かるかも知れないと思って」
「ストレートで飲むと女の子にはきついから、オンザロックにし
てもらおう。氷が十分に溶けてからゆっくり飲んでごらん」
そう言って、ウェイトレスにオーダーしてミニチュアボトルのブ
ランデーを半分ほど氷の入ったグラスに注いでから由美に渡した。
「どう?美味しいかい?」
由美はほとんど舐めるようにして味わっていたが、
「いい香り、口の中からフワーッと広がってくるんですね。これ
がブランデーなんですね」
と、感心したように何度もグラスを見つめていたが、少しずつ口
の中に入れては香りを楽しんでいる。
「由美ちゃんはお酒を楽しむ素質があるみたいだね。美味しいか
い?」
「はい、お酒を楽しむって言うことが分かってきたみたいな気が
します。あの、残りの半分も飲んでいいですか?」
「いいけど、もっとゆっくり飲まないと後で酔っぱらっちゃうよ。
今はお腹にいろいろなものが入っているからお酒の回り方が遅い
けど、飲んだ分は必ず身体の中に入るんだからね。この氷が溶け
たら飲んでいいよ」
宏一は残りをグラスに注いで由美に勧めた。
「そうなんですか、大人になってきたから酔わなくなったのか
と思って安心して飲んでいたんですけど。分かりました、ゆっく
り飲みます」
「由美ちゃんの身体はもうすっかり大人になったみたいだけどね」
そう言って宏一がからかうと、由美は顔を真っ赤にして
「もう、そんなこと、こんな所で言わないで下さい、他の人に聞
こえたらどうするんですか」
「ごめんごめん、よけいなこと言っちゃったね」
「もう、今の一言ですっかりお酒が回っちゃいました。なんか少
し、平衡感覚がおかしいみたいです」
「食事をしながらゆっくり飲んでいれば大丈夫だよ、でも、無理
して飲むこと無いからね。お酒は美味しく飲むものだよ」
「はい、でも、飲んでみたいんです。いいでしょ?お部屋は近い
んだから。宏一さんと一緒なんだもの。少しわがままを聞いて下
さい、宏一さんも一緒にブランデーを飲みませんか?」
少し酔い始めている由美は宏一にもブランデーを飲ませたがった。
宏一は強い方なので、由美の希望通りに付き合うことにした。
二人でグラスを合わせ、
「宏一さん、素敵な旅行をありがとうございました。これからも
よろしくお願いします。私たちに乾杯」
由美はすっかり上機嫌だ。
コーヒーとフルーツを食べ終わる頃になると由美の目はとろん
として言葉も少なくなってきた。だいぶ酒が回ってきたようだ。
「そろそろ部屋に戻ろうか。立てるかい?」
「大丈夫です。あれ?ちょっと待って下さい。なんか変です。宏
一さん、掴まってもいいですか?」
「ああ、調子に乗って飲むからだよ、部屋まですぐだからね」
由美は宏一に抱きかかえられるようにして部屋に戻ると、ソフ
ァーに座り込み、
「なんか、グラグラします。少し、休ませて下さい。休めばすぐ
にすっきりしますから」
そう言って、そのままウトウトし始める。宏一はそうは思わなか
ったが、
「由美ちゃん、先にシャワーを浴びておいで、そうすればすっき
りするよ」
と言って由美を立たせると、バンザイさせてTシャツを脱がし、
ブラジャーを外してからスカートとショーツを下ろしてソックス
を脱がせた。全裸になると由美はふらふらした足取りでシャワー
ルームに向かう。
中で寝てしまうか少し心配でシャワーの音を注意して聞いてい
たが、由美は5分ほどで出てきた。まだ少しふらついている。バ
スタオル一枚の姿で
「宏一さん、先にベッドに行ってますからすぐに来て下さいね」
と言うと、寝室に入っていった。
この調子では、2分もしないうちに寝てしまうだろう、そう思
いながら少し飲ませすぎたかな、と思った。しかし、二日酔いに
なるほどでもないだろうと思い、そのまま休ませることにした。
5分ほどしてから覗いてみると、案の定スヤスヤと可愛らしい寝
顔を見せている。寝顔を見ていると、ふと由美に対する思いに何
か懐かしいものを感じた。『あれ?何だろう』以前にも同じ事が
あったようだ。
宏一は一人でラウンジカーに行って飲み物を買ってくると、居
間のソファーに座り、記憶の中を探った。『そうか、昨日と同じ
だ。あのときと似ているんだ』頭の中に引っかかっていたものが
はっきりしてきた。
『史恵ちゃんの時と似ているんだ。あのときも二人だけの夜を過
ごしたんだ』再び頭の中に、うれしいようなほろ苦いような想い
がよみがえってくる。冷えたビールを流し込むと、ほろ苦さが心
地よい。もうすぐ史恵に逢えるのだと思うとその想いは更に複雑
になった。あのころは真剣に史恵を愛していた。『今回はちゃん
と愛せるだろうか?』大騒ぎだった史恵の初体験を思い起こしな
がら、宏一は再び追憶の中へ入っていった。
宏一が史恵を誘ったのは、史恵が父の転勤について九州に戻る
とうち明けられた一週間後のことだった。宏一はまだ大学生で、
もうすぐ遠くに史恵が行ってしまうと思うといてもたってもいら
れなくなり、なけなしの貯金をはたいて史恵を一泊の旅行に誘っ
た。
史恵も、宏一のことは大好きだったし、自分が心の中をうち明
けられる唯一の人だったから、自分の気持ちに整理を付けたいと
思い、両親に必死に頼み込んで外泊の許可をもらった。史恵は宏
一と外泊することを正直に告げたが、親は史恵の気持ちを知って
いたらしく、そこまで言うのなら、と黙って旅行費用を出してく
れたらしい。
旅行の当日、史恵の家に迎えに行った宏一は、そのまま客間に
通され、母親に挨拶する羽目になった。しかし、優しい母親で、
教師を職業としているだけあり、詮索がましいことは一言も言わ
ず、和やかに話を進めてくれた。出かける前にお腹に何か入れて
置いた方がいいでしょうと寿司の出前を取ってくれたあげく、
「若い人には足りないでしょう」
とラーメンの出前まで取ってくれた。
「それでは明日まで史恵さんをお預かりいたします」
そう挨拶して二人で家を出ると宏一は史恵に言った。
「とっても優しいお母さんだね、いろいろ気を使わせちゃって悪
いことしたよ」
「母は結構宏一さんのことを気に入ったみたいですよ。さっぱり
した感じのいい人ねって言ってたから」
「そうか、それは良かった。ん?何が嬉しいの?」
「私、人を見る目だけはあるんだ。母に自慢できて、少し嬉しい」
「へぇ、それは光栄だね。おっと、予定を少し時間を過ぎちゃっ
たけど、日光に着く頃にはまだ少し見物する時間はあると思うよ」
「ええ、どうしても見物したいところがあるわけじゃないから、
ホテルに着いてから考えましょう」
史恵は軽くそう言って、にっこりと笑った。
父の転勤の日までいくらもなくなった今となっては、史恵は後
で後悔しないようにできるだけ宏一と愛情の確認がしたかった。
宏一にしてみても、今回の旅行では二人の情熱を思いっきり確か
めることができるはずだった。
東京駅から新幹線で宇都宮までは1時間ほどで、そこで宏一
はレンタカーを借りてホテルに向かった。道路が比較的空いて
いたせいか、1時間もかからずに鬼怒川温泉に着いたので、東京
の史恵の家を出てから3時間少々だった。ホテルにチェックイン
する時、宿泊者名簿に三谷宏一、史恵、と二人の名前を書くと、
史恵が、
「私たち結婚しているみたいね」
と笑って言った。フロントマンがじろっと見たが何も言わず、ダブ
ルの部屋のキーを渡してくれた。
エレベーターの中で、
「フロントであんなこと言っちゃダメだよ、びっくりした」
と宏一が言うと、
「だって宏一さんがあんな風に書くんだもの。ちゃんと書けばい
いのに」
と史恵が言うので、
「ホテルの宿泊者カードには名字を書く欄は一つしかないんだよ。
建前上、夫婦や家族でしかホテルは同じ部屋に泊まれないこと
になっているからなんだ」
と宏一が言うと、
「そうなんですか。ごめんなさいね」
と素直に史恵は謝った。
部屋に入ると、荷物を置くのももどかしく史恵を後ろから抱き
しめた。史恵は、
「ちゃんと鍵はかかってる?」
と、感情にまかせていいものかどうか迷っている。
「大丈夫だよ。史恵ちゃん、好きだよ」
そう言いながらうなじに唇を這わせる。宏一の両手はゆっくりと
胸の膨らみを撫でていたが、史恵の息が次第に荒くなってきたの
で軽く膨らみを握ってみる。膨らみは小さめなので、握ると言う
よりは押さえる感じに近い。
「あっ」
史恵は声を出すとビクッと体を震わせ、くるっと後ろを向くと宏
一に抱きついてきた。
お互いに激しく舌を絡め合うディープなキスを楽しんだ後、史
恵を抱き上げてベッドに運んだ。史恵は自分から靴を脱ぎ捨てる
と、
「ねぇ、どこに行くか考えるんじゃなかったの?」
と少しわがままを言ってみた。
「だからこうして二人で考えようって言うんだよ」
「ああん、こんなことしてたら外に出れなくなっちゃう」
宏一が史恵の上に被さってくると、首筋に愛撫を受けながら史恵
が身体をくねらす。
「外に出たいの?」
「宏一さんは?」
「もう少しこうして二人でいたい。史恵ちゃんは?」
「私も」
「それならいいじゃない」
「ああん、こんなことするのならわざわざ日光まで来なくたって
良かったのにぃ、ああっ、宏一さん、好き」
「大好きだよ」
宏一は史恵のワンピースの背中のジッパーをすーっと下げると、
史恵の両手を服から抜いて、ブラジャーの上から小さな膨らみを
唇でなぞるように愛撫する。そして、両手でワンピースを腰から
脱がせようとする。
「あうっ、だめっ、宏一さん、下からは脱げないの。あうっ、上
から、上から脱がせて。私、お尻が大きいから、上からして」
宏一が
「はい、バンザイして」
とワンピースを上から脱がせると、おとなしく協力した。しかし、
ワンピースをベッドの横のテーブルに無造作に放り投げようとす
ると、
「だめ、皺になっちゃう。ちゃんと置かして」
と宏一の手からワンピースを取って自分で畳み始めた。
「なんて言ったの?」
「ちゃんと置かして、って言ったの」
そう言いながら史恵がワンピースを畳んでテーブルの上に置くと、
宏一はいきなり史恵の両手を押さえつけ、
「じゃあ、犯してあげる」
とブラジャーのショルダーストラップを一気に引き下ろした。
「いやっ、そんなのいやっ、だめっ、ちゃんと優しくしてくれな
いと。だめっ」
史恵は激しく抵抗する。
「犯して欲しいんだろ。抵抗しても無駄だよ」
と、宏一はさらに背中のホックを外そうとする。
「いや、そんなのいやっ、ああっ、許して」
史恵の声が悲しい響きを帯びてきたので、宏一は、ちょっとかわ
いそうだったかな、と優しくおでことほっぺたにキスをして、
「だって犯してって言うから、そう言うのが好きなのかなって思
って」
と笑って言うと、
「あーびっくりした。いきなり乱暴にするんだもの」
と史恵も目に涙を浮かべていたが、安心してキスをしてきた。
「でも、本心が出て来ちゃったのかな。宏一さんならいいって」
とポツリとつぶやいた。
宏一が素早くトランクス一枚になって、ゆっくりと首筋から胸
元に唇を下げて行くと、
「はあっ、やっぱり怖い、宏一さん、あっ、ダメ、やっぱりだめ、
ちょっと待って」
と宏一の顔を胸から引き離す。
「どうしたの?」
「今は、胸だけにしてね。それ以上のことは夜までしないでね」
「わかったよ、約束する。さあ、両手を離してごらん」
史恵は少し覚悟を決めたように、ゆっくりと両手を胸から離した。
再び宏一がブラジャーの周りをゆっくりと愛撫して行くと、
「ああっ、ビリビリって電気が走るみたいなの、なんか、身体が
勝手に反応するみたいで、あん、ああん」
史恵は自然に身体をくねらせ始める。さらに宏一がカップの上か
らも分かるくらいになってきた膨らみの頂上を唇で軽く挟むと、
「あーっ、身体が反応してる。私の身体、感じてる」
と身体を反り返らせる。
「じゃあ、これも外すよ」
宏一が背中に手を回してバックストラップを外すと、やはり両手
でカップを押さえてしまう。
「両手をどけてごらん」
「あの、宏一さん、少し休憩しませんか、あの、そんなに急がな
くても・・・」
「さあ、そんなこと言ってないで、ほら、感じてきたら両手を僕
の首に回すんだよ」
そう言いながら史恵をそっと抱きしめると感じやすい首筋から再
び攻め始める。
耳元の近くを軽く愛撫して行くと、
「ああっ、だめ、息をかけないで、宏一さん、好き、優しくして、
ああっ、怖いっ」
快感の波に怯えながら史恵は一線が越えられなかった。どうして
も怖さが先に立って拒絶してしまう。
優しく愛撫していた宏一は少しじれったくなってきた。史恵の
気持ちは分かっているのだから、ここはリードしてやらなければ
先に進めない、そう思うと強硬手段に出ることにした。
ゆっくりとブラジャーのカップの周りを愛撫して史恵が安心し
たところで一気にブラを引き下げる。少し大きめのすでに十分に
尖った乳首が露わになる。
「あっ、いや!」
うっとりしていた史恵が驚いて拒絶したときには宏一は史恵の乳
首を口に含んでいた。
「あっ」
史恵は驚いたが、すぐに抵抗しなくなり、宏一の愛撫を受け入れ
た。
「もう、こんなことするなんて、強引なんだから」
その口調はあきらめの中に少しだけ安心が混じっていた。
「あん、少しくすぐったい」
史恵は怒ってはいないようだ。宏一は安心するとゆっくりと愛撫
を再開した。横になっているときの史恵の乳房はほんの少し膨ら
んでいるだけなので、あまり膨らみは実感できない。
しかし、感度は素晴らしく、頂上に近づいて行く程反応が激し
くなる。
「ああっ、宏一さん、恥ずかしい、見ないで、見ないで、はうっ、
あーっ、もう、あうっ」
唇が左の乳首をとらえると、身体全体がビクッと震え、大きくの
け反る。宏一がゆっくりと乳首を含んだりそっと転がしたりして
いると、
「はあっ、とうとう許しちゃった。あっ、ああっ、いいっ、とっ
てもいいっ」
と初めて身体の中を駆けめぐる快感に喜びを表す。
宏一がそっと唇を離すと、
「こっちも」
と右の乳首を宏一に与えようとした。
「今度はゆっくりとするからね」
そう言って、かすかな膨らみの周りから丹念に同心円を描くよう
にゆっくりと中心に近づいて行く。
「はあっ、こんなの、焦らしちゃいや、ああん、宏一さん、いじ
わる、あ、アアっ」
「優しくしてっていうからゆっくりとしているのに」
「だって、ああっ、頭の中が、ああっ、狂っちゃう、あーっ」
再び宏一の唇が乳首をとらえ、舌で軽く弾くようにすると、史恵
のビクッビクッと身体が反り返る。
この時の宏一は史恵のことが本当に好きだった。少しでも快感
を与えて満足させてやりたかった。
「次は手でしてあげるからね」
両手で脇から軽く撫で上げるようにして乳房の感度を高めておい
てから両手で絞り上げるように揉んで行く。
「あーっ、凄いっ、許してっ」
史恵は快感に体を震わせながら、なぜ胸に触られるだけでこんな
に感じるのか不思議でならなかった。
『きっと、宏一さんのことが好きだからなんだ』そう思うと安心
して身体の感覚に身を任せた。
「アアン、こんなに感じちゃうなんて、少し怖い」
「いっぱい感じてごらん、どんなに気持ちよくなったっていいん
だよ」
宏一が優しく耳元で囁くと、
「ほんと?」
といたずらっぽい目で宏一を見つめる。史恵は自分の膨らみが小
さいので、本当に大人のように感じることができるのか少し心配
だったが、正常に感じていることが嬉しかった。
トップ |