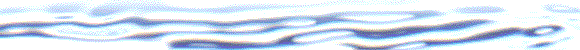改札を抜けて駅の外に出ると日差しは結構強かった。
「何か、都会ですねぇ」
由美は予想と違ったのか、キョロキョロしながらしきりに何か考
えている。
「札幌は百万都市だよ。地下鉄だってあるし。もっと田舎だと思
ってたの?」
「そう言う訳じゃないですけど、なんかアメリカみたいなイメー
ジがあるじゃないですか。広くておっきくてって」
「うーん、少し郊外に出ればさすが北海道って感じになるけど、
こんな街の真ん中じゃあねぇ、大通り公園に行けば少しは気分が
でるかなぁ」
「じゃあ、最初はそこに行きましょう」
「いいんだけど、あんまり時間がないんだ。飛行機に丁度いい空
港行きの列車が2時半に出るから、お昼を食べたらひと休みする
くらいの時間しかないんだよ」
「最後は飛行機にも乗るんですか?凄いですね」
「だって、僕たちは夕方には東京にいるんだよ。飛行機に乗らな
きゃ帰れないよ」
「そうか、そうですね。飛行機にも乗れるんですね」
そう言うと、にこにこして宏一の腕を取った。
しかし、すっと近寄って宏一をのぞき込むように小さな声で、
「でも、宏一さんがホテルに行きたいって言うのなら、それでも
いいですよ。私、この旅行はもう十分に楽しみましたから」
と聞いてくる。
「大丈夫だよ、それとも、由美ちゃんがホテルで楽しみたいのか
な?」
そう笑って言うと、真っ赤な顔をして
「もう、人の気も知らないで。さあ、行きましょう」
と宏一の手を取って先に歩き出す。
「由美ちゃん、怒ったらお腹が減ったんじゃないの?」
宏一が後ろから宏一が追いついて由美の腰に手を回して言うと、
「私怒ってなんかいませんよ。でも、そう言えば何にも食べてま
せんね。何か食べたいですね」
「それじゃ先にお昼にしよう。もし時間が余れば散歩でもすれば
いいさ」
「何を食べさせてくれるんですか?」
「もちろんお楽しみだよ」
二人は楽しそうに身体を寄せ合って歩いていった。
どうせ直ぐに戻ってくるのだから、と荷物をコインロッカー
に預けて身軽になった二人はタクシーに乗ると、宏一が以前行っ
たことのある寿司屋の名前を告げた。由美は、空腹を思い出した
途端にお腹が減って仕方がなかった。
「由美ちゃんはお寿司、好きかい」
「わぁ、あこがれてたんです。テレビでよく見るけど、まさか自
分が札幌でお寿司を食べられるなんて、有名なお寿司屋さんなん
ですか?」
と由美は飛び上がらんばかりだ。
「有名かどうかは知らないけど、結構地元の人で混んでるから、
気に入ってもらえると思うよ」
由美は満足したらしく、
「お寿司なんて、ふふ、素敵」
と外を眺めてニコニコしている。
混雑した駅前から離れたタクシーは、初乗り運賃にほんの少し
足した程度で店の前に止まった。店の中に入ると明るい造りで、
昼時なのでそこそこ混んではいたが、運良く待たずに座ることが
できた。二人はカウンターに着くと、壁一面に貼られたお品書き
を眺めた。
「凄いですね、私が知らないものがいっぱいある。本当に北海
道に来たんですね」
と由美は変なところで感心している。
「せっかくカウンターに座ったんだから、好きなものを注文して
ごらん」
宏一はそう言うと、日本酒のリストに目を移した。
宏一は、最初軽く日本酒を飲みながら造りを楽しむことにした
のだが、由美はすかさずお好みであれこれ注文を始めた。冷酒は
なかなか美味しかったので、
「由美ちゃん、一口飲んでみるかい。なかなか美味しいよ」
と言うと、
「いいえ、遠慮します。お酒は、結構です」
と素っ気ない。昨日の一件が堪えているようだ。それでもうれし
くて仕方ないらしく、
「宏一さん、オヒョウって何ですか?」
「ヒラメのおっきい奴だよ」
「8月なのにサンマがありますよ」
「こっちでは今がシーズンだからね」
「あっちにあるおっきい魚は何ですか?」
「あれはホッケだよ。東京のは小さいから分からないのも無理な
いね」
などと、宏一がゆっくり酒を楽しむ暇もない。
あまり由美がしゃべるので、
「由美ちゃん、ちゃんと黙って食べないと、お腹に悪いよ」
と言うと、急にシュンとなって
「ごめんなさい」
と黙って食べ始めた。板前さんが、
「お嬢さんみたいに可愛い人なら店の中が明るくなっていいです
よ」
と由美を慰める。それで少し元気を取り戻したのか、少しずつ元
気を取り戻し、
「このタラバ蟹のおみそ汁、とってもいい香りですね」
とか宏一がつまみに頼んだホヤを味見して
「ホヤって不思議な味がしますね」
などとぶつぶつ言いながらも、美味しい美味しいと盛んに食べ始
めた。
由美があまり美味しそうにぱく付くので宏一もゆっくり飲む気
分ではなくなってきた。
「さて、それじゃこっちも握ってもらえますか?」
そう言うと、矢継ぎ早に、赤貝、サンマ、ホタテ、ウニ、と注文
していく。由美も負けずに注文したので、ひととき板前は専属の
ように握り続ける羽目になった。
由美はオヒョウを食べながら、
「あの、寝ているときに不思議なものを見たんです」
そう言うと、夢うつつで眺めたアニメーションの話を始めた。
「何か、窓がスクリーンになったみたいで、ずっと、っていって
もそんなに長くありませんけど、いろいろ動いているのが見えた
んです。寝ぼけて昨日のシアタービレッジの夢でも見たのかなぁ
って考えたんですけど、でも見たんです」
由美は、不思議そうに、まるで怪談でも話すように小声で宏一に
そう言った。
宏一は口を動かすのをやめてニッコリ笑うと
「そうか、由美ちゃんはあれを見れたんだね。それは良かったね。
寝る前に言おうかと思ったんだけど、とても起きていられそうに
なかったからそのまま寝ちゃったんだ。ごめんね」
と言った。由美はますます不思議そうな顔をしている。
「あのね、青函トンネルの途中にLEDの発光器が仕掛けてあっ
て、列車のスピードに応じて上手くアニメーションが出るように
光るんだよ。トンネルの途中に一カ所しかないし、時間も短いか
らなかなか見れないんだよ。あ、成田空港の駅の出口にもあるよ」
と説明した。
「そうなんですか。何なんだろうって不思議に思っていたんで
す。宏一さんに聞いて良かった」
「青函トンネルの前後にはいくつかトンネルがあるから、他のト
ンネルと間違わないようにしてあるのかも知れないね」
「何か幻想的って言うのかしら、宏一さんも起こしてあげれば良
かったですね」
とクスッと笑う由美に、
「僕は疲れてたから、たぶん起きなかったと思うよ。誰かさんの
おかげで」
とニヤッと笑う。由美はぷいと前を向くと、知らん顔をしてそっ
と肘でこずいた。
結局、由美は二十カン近くも食べ、店の人が
「これだけ美味しい美味しいと食べてもらえると造り概がありま
すわ」
と笑って言うと、由美はあっさり、
「でも、本当に美味しいんですから。ごちそうさまでした」
とケロッとしている。
二人は店を出てからしばらく歩いて大通り公園に行った。屋台
でアイスクリームを買い、空いているベンチに腰を下ろす。高校
生の女の子は仲間同士でトウモロコシを分け合っている。
「まだ時間は大丈夫ですか?」
「うーん、もう少ししたら行った方がいいね。でも、アイスクリ
ームを食べる時間ぐらいはあるよ」
「えーと、おとといになるのかしら、清水で食べたアイスも美味
しかったけど、ここのは本当に美味しいですね」
「まあ、気分の問題もあるだろうけど、トウモロコシとアイスク
リームは美味しいと思うよ」
「絶対美味しいですよ。気分だけじゃないですよ」
「気に入ってもらえたんならうれしいよ」
「宏一さんはどこでも知っているんですね」
「大学の時に鉄道研究会であちこち旅行したし、この仕事を始め
てからもあちこちに行ったからね」
「そうなんですか。うらやましいな、私なんか、親の実家以外に
旅行に行ったのは修学旅行ぐらいなものですよ」
「由美ちゃんぐらいの年だとみんなそうだと思うよ。僕だって由
美ちゃんぐらいの時はそうだったよ」
「でも、私これで少し自信がつきました。もしかしたら自分で旅
行できるようになるかも知れないなって」
由美はニッコリと笑って言った。
「宏一さんのおかげです。感謝してます」
そう言うと、身体を宏一に預けてくる。
そこは、確かに日差しは強かったが、京都や東京に比べれば天
国だった。人通りは多かったが、東京出身の由美にしてみれば少
ない方だった。アイスクリームは普通のバニラだったが香りと口
当たりは素晴らしかった。ここにはあくせく生活している東京人
にとってはどこかゆっくりと時間が流れていくような、そんな雄
大さがあった。第一、札幌の人間は東京人ほど速く歩かない。
澄み切った青空を眺め、宏一の肩により掛かっていると、この
ままずっとここにいたいという思いがしてくる。しかし、由美に
は分かっていた。
明日からはまたいつもの生活が待っている。楽しめるのも今のう
ちなのだ。よく分かっている分だけ気分が沈んできた。一口ずつ
大切にアイスクリームを食べていると、これが今の楽しさを象徴
しているように思えてきた。
突然、何か分からないが、由美は悲しくなってきた。コーンの
最後まで食べ終わったとき、由美の頬には涙が光っていた。赤い
目をした由美は、無理に宏一に微笑むとできるだけ元気を出して
言った。
「さあ、帰らなきゃ。両親が待ってます」
宏一は、痛々しいほど元気を出している由美を抱き寄せると唇を
重ねた。そして二人は立ち上がると無言で歩き始めた。
タクシー乗り場が見えてくると、由美は足を止めた。周りには
あまり人はいない。宏一の首に手を回し、自分から唇を求める。
「宏一さん・・・・宏一さん・・・」
後は言葉にならなかった。
由美の頬を涙が止めどもなく流れ続ける。宏一の腕の中でかすか
に奮えている由美を抱きしめながら、『こうなったらやれるだけ
やるしかないな』と宏一は意思を固めた。
札幌から快速に乗り、千歳空港駅で降りて、隣接する空港で
羽田行きの飛行機に乗るまで二人は不思議とあまり話をしなかっ
た。千歳空港は国内線がほとんどを占める空港にしては非常に大
きいターミナルで、帰り客を目当てに生チョコレートから生きた
蟹まで、ちょっとした市場に相当するくらいの店が軒を連ねて客
を集めていた。
人混みの中で由美は宏一の手をしっかり握って離そうとしない。
途中でポツリと、
「さすがにここでのお土産を買うわけにはいきませんね」
とつぶやいた。離陸後、姿勢が安定したころに由美は宏一の肩に
頭を預けて目をつぶり、宏一のことを考えていた。由美はまだ高
校生だが一通りの常識は持っていたし、並の高校一年生よりは考
えることもできた。
宏一は不思議な人物である。突然由美の前に現れ、由美の体を
大人にしていった。本人の意思とは関係なく。何のためかは分か
らないが、二人が過ごすのは普段人気のない小さなマンションの
一室だ。まるで、由美との時間を過ごすのが目的であるかのよう
に机とベッドが用意されている。そして、平気で由美に大金をつ
ぎ込んでいる。
良くは分からないが、由美と過ごす部屋代を入れると月に数万円
にはなるはずだ。
今回の旅行にしても全て惜しみなく金がつぎ込まれている。由
美の身体が目当てにしては出来過ぎだった。父親の会社の人がこ
んな事するだろうか、考えてみたが分からなかった。今、宏一は
確かに自分が助けてあげると言っている。父親の何百万もの不正
を帳消しにすると言っているのだ。謎だらけである。宏一がどこ
に住んでいるのかさえ由美は知らない。
今の由美は宏一のことを真剣に考えるようになっていた。自分
でも宏一に熱烈に恋していることに気付いている。好きな人のこ
とはどこまででも知りたい。
もっと宏一に訪ねようかとも思った。しかし、女の感としてよけ
いな詮索はしない方がよいような感じがした。もし、宏一が聞い
て欲しくないことを聞いてしまったら宏一は由美から去っていく
かも知れない。それを思うと、今と未来を信じる以外になかった。
ふと、小さいときに読んだ足長おじさんの話を思い出した。
『今の宏一さんは私の足長おじさんなのかしら?信じるしかない
し、他に手だてがあるわけでもないし・・・・、パパにこっそり
聞いてみようかな?』
そう思っては見たが、もし横領が本当だったとしたら父にどうこ
うできる問題ではなさそうだ。それでなくても由美の家は身体の
弱い母がいるので三人家族としてはそれぞれの負担が大きくなっ
ている。
今、父が問題を起こせば母の容態にいい影響が出るはずがない。
『もう少しがんばって宏一さんに付いていこう』
結局由美は今の宏一を選んだ。
ふと横を見ると宏一は寝ているらしい。宏一の寝顔を見るのは
由美にとって初めてだ。自信に満ちているときの宏一は体中から
力が溢れ、知らないうちにその中に巻き込まれて行くほど力強い
が、寝顔は子供っぽいところさえ感じられる。
『うふ、可愛い』
宏一の秘密を覗いたようで少しうれしかった。そのままそっと宏
一の肩に自分の頭を預け、目をつぶる。
既に宏一に由美の体は全て知られてしまっている。由美自身、
普段は少し大人しい方だと思っているが、宏一と一緒にいるとき
の由美はHで大胆な由美だ。宏一に、普段の自分も見て欲しかっ
たが、宏一に引き出されたもう一人の自分も嫌いではなかった。
人前で堂々とキスできる自分は前から欲しいと思っていた自信を
持った自分だ。
『今日は帰ったら一枝ちゃんに電話しなきゃ。何を聞かれるか
な?何を話そうかな?』
一枝に少しほのめかすように自慢できるのがうれしかった。今ま
で成績以外では一枝に頼りっぱなしだったので、初めて一歩リー
ドした形だ。
『でも、宏一さんは帰る前に部屋で私を愛してくれるかしら・・
・、そうしたら優しく抱きしめてもらって、いっぱいキスをしな
がら・・・・』
そこまで考えて、自分で勝手に想像して顔を真っ赤にしているの
が恥ずかしくなった。今まではこんな想像はしたことがなかった。
しかし、この三日間は由美にとってものすごい体験だったので、
いつの間にかこれくらいの想像はするようになってしまったらし
い。
飛行機が羽田への着陸態勢に入ったとき、由美は今回の旅行を
かみしめるように思い出していた。東京からの新幹線の中で、嫌
がるのを無理やり感じさせられ、あと少しだけ、と思いながらも
次第に大胆になっていったことや、やっと満足するまで何回も宏
一を受け入れたこと、一枝と電話をしながら宏一に愛されたこと。
そして、何と言っても早朝のホテルの庭園で宏一にTシャツを捲
り上げられ、後ろから入られて最後には恥ずかしがりながらも自
分から求め、いってしまったことが頭の中を駆けめぐった。
そして、生まれて初めてブルートレインに乗って、宏一の胸に
安心して身体を預けることができた。肉体的な満足感も素晴らし
かったが、今はその後になっても心が落ち着いているところが今
までと決定的に異なっていた。
もしかしたら、今までのように貪欲に快感を求めなくても良いか
も知れない、そんな思いも芽生えてきた。
機内放送に宏一が目を覚ましたようだ。由美はさわやかな笑顔
でにっこりと微笑む。宏一は手を握ってきただけで、何もしな
かった。
「由美ちゃん、楽しかったよ。ありがとうね」
その言葉で由美は宏一がこのままどこかの駅で別れるつもりであ
ることを悟った。一瞬、もう少し宏一と一緒にいたい、と言う想
いが胸を突き上げる。
「宏一さん・・・」
「なんだい?」
「え、あの・・・ありがとうございました。本当に楽しかったで
す」
「じゃあ、今度の火曜日だね」
「はい、部屋で待っています」
飛行機が着陸した。機内手荷物のみなので二人とも早々とコンコ
ースを抜けてモノレールに乗る。混雑している車内では、由美は
宏一に身体を預けていた。宏一も目立たない程度に由美を抱いて
いた。
宏一は浜松町の駅で、
「ちょっと寄るところがあるから」
と言うと、
「もう!・・・」
と由美は少し驚いたようだったが、
「ありがとうございました」
というと由美は宏一に軽く口づけてきた。唇を離した由美の目に
は涙が光っていた。
宏一はすぐにタクシーに乗ると会社に向かった。一刻も早く確
かめておきたいことがあったのだ。部屋に入るとサーバーマシン
を立ち上げ、管理者用の環境を立ち上げる。
大型のシステムと異なり、この程度の会社のシステムならば管理
者は全てのことができる。現在使用中の経理システムを立ち上げ、
月末に作成される営業報告シートを丹念に調べていく。
宏一は損金と売り掛けの関係を調べていた。通常、取引が成立
しても直ぐに現金は入ってこない。大抵は手形で決済する。その
手形に記載された決済期日でいつ現金になるかが決まる。ここの
会社では手形が振り出された時点で売り上げを計上すると同時に
一旦損金としても計上し、後日現金化された時点で損金を相殺す
るシステムを取っていた。
従って、営業報告がなされた時点では、売り上げて入ってきた現
金と売上高は一致していない。
更に丹念に損金の項目を順に調べていった宏一は予想が当た
っていたことに満足してシステムを落とした。この会社の経理シ
ステムでは損金の額は売掛金の手形を全て実際に調べて見ないと
本当のことは分からないのだ。
あってはならないことだが、実際には手形に記載された金額の合
計が常に会社に入ってくるわけではない。仕入れの関係でどうし
ても直ぐに現金が欲しくなった場合は手形を第三者に売って現金
に変えることもある。
当然、手形の金額の数パーセントから2割程度は第三者の手数料
になるので、その分は損することになる。これが本当の損金なの
だが、この金額を特定することはこのシステムでは不可能なのだ。
更に、手形で取引した後になって手形を現金化する際に値引き
と同じ意味で幾ばくかの商品の納入を求められることもあり、得
意先に対しては品物代を損金に計上して実際は只で納めることも
ある。
これらを厳密に調べた上でないと、木下部長の横領の結果である、
現金化されることのない偽の売り上げを特定はできない。その内、
手形が決済されたことにしてしまえば誰も知らないうちに横領は
完成する。これは営業部長なら簡単だ。
一世代以上前の経理システムなので、損金は来月に回してしま
えば経理上は帳簿が合うからいいじゃないか、と言う程度のシス
テムである。年商数十億の会社としては恐るべき怠慢であるが、
細かくない分だけ自由も利くので、慣れていると不自由は感じな
いようだ。
宏一が設計している新システムではこの損金を構成する一つず
つの取引が全ていつまでも記録として残っているので、誰の取引
が現金化されていないかは表に出せば一目瞭然になる。
当然、何ヶ月か経つと、あの取引はどうして手形のままなんだ、
となり、担当の営業マンに催促が行くことになる。しかし、そん
な取引はした覚えがない、と営業マンが言えば(木下部長が勝手
にでっち上げた取引なので当然言うだろうが)、後はどうにもな
らなくなるのは目に見えている。
このシステムの欠陥を宏一は利用することにした。具体的な手
順はまだ決めていなかったが、何とかなりそうであった。元はと
言えばこのシステムにこのような重大な欠陥があり、実際に損害
も発生しているからこそ新システムの設計依頼が宏一に来たので
あるから、考えてみれば当然の結末だ。
宏一は次にネットワークのシステム設計の仕事の手直しに入っ
た。木下部長の横領額の全体像は明日以降に調べる予定だが、宏
一の貯金でまかなえる量など知れている。
ある程度は会社の経費で落としてしまわなければならない。そこ
で、ネットワークシステムのグレードをあげて宏一が手に入れら
れるリベートを吊り上げ、そこから補填する事にしたのだ。
明日一番で部長会に提案できるように全体の骨子の作成を始めた。
誰にもじゃまされたくなかったので、携帯のスイッチを切って
一気に仕事にかかる。最初は各部のパソコン同士を単に繋いで、
それぞれのネットワークサーバーを経由して全ての情報を管理す
ることを考えていたが、一応まともなループ型のネットワークを
作ることにした。
こうしておけばデータ量が増えてもパソコンの通信の反応が鈍く
なることはないし、将来の拡張時にも投資が少なくて済む。そこ
の点を重視して簡単なプレゼンテーション用の資料を作成した。
次に配線工事の手配の変更に入った。由美と出かける前に、発
注すればよいだけにしておいた工事手配書を新しい仕様に合わせ
て変更する。これは結構面倒な作業で、いろいろなカタログを調
べたり、実際に該当する部屋に行って長さを測ったり、手間がか
かる割になかなか進まない。
宏一は夕食も食べずにがんばったが、夜までには終わらなかっ
た。いくつか電話をかけて値段を調べる必要もあったので仕上げ
るのは明日に回すことにして会社を後にする。
時計を見るとすでに十時を回っていた。どこかで軽く食事を済ま
せて帰ろうと思ったとき、ふと思い出して携帯のスイッチを入れ
ると直ぐに携帯が軽い音を響かせた。
「もしもし?宏一さん?あーやっと繋がった」
「明子さん?どうしたの?」
「そっちこそどうしたのよ、携帯のスイッチを切ってたんでしょ?」
「今、会社を出た所なんだ。仕事が溜まってたから一気に片付け
たから」
「そうなの?もう帰ろうかと思ってたのよ」
「え?今どこなの?」
「宏一さんのアパートの近くの喫茶店。四時間も待ったんだから」
「鍵を持ってるんだから中に入っていればいいのに」
「だって、宏一さんに勝手に入るなんて悪いじゃない」
「気にしなくたっていいよ」
「じゃあ、今度からそうしようかな?」
宏一は一瞬言葉に詰まった。
洋恵を抱いているところにでも押しかけられたら目も当てられ
ない。
「ウソよ。安心して。ちゃんと断ってから入るわよ」
明子に変に思われたと思って宏一は少しあわてた。
「いいよ。勝手に入って、それで食事でも作っておいてくれたら
言うことないんだけどな」
宏一は必死に取り繕おうとした。しかし、明子は
「そんなこと言ってないで、早く戻ってきて」
と、取り合おうとしない。
「直ぐに帰るからね、待っててね」
「もう一杯紅茶を頼むわ、五杯目よ」
「ごめん、直ぐにいく」
早足で駅に向かった。宏一は旅行用のバッグを駅のコインロッカ
ーに入れると、ホームに向かって走り出す。
まさか今日、明子が来るとは思わなかった。明子にはふらりと
旅に出るかな、程度のことしか言っていなかったから、宏一の予
定は確かに知らない。
何もこんな時に来なくたって、と思いながら電車の速度をひどく
もどかしく思った。あわてていたのでコインロッカーにバッグを
預けたまま来てしまった。
旅行に行ってきてから会社にいたと正直に言えば明子だって疑わ
ないだろう。しかし、もうどうしようもない。嘘をつくよりもだ
まっていよう、そう思った。
トップ |