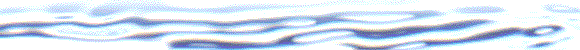明子はふーっとため息をつくと、
「もうすぐ閉店なんですが」
と困った顔の店員に、
「時間になったら出ますから」
と紅茶をもう一杯頼み、先程の会話を思い出していた。
宏一のことだから、会社で仕事をしていたのは本当のことだろう。
しかし、そう言うのは土曜日に済ませて、日曜日は休息にあてよ
うとするのが普通なのではないのか。なぜ、日曜日に遅くまで残
っていたのか。
もちろん、大切な仕事を思いついたと言うこともあるだろう。
しかし、宏一の性格からしてあまりそんな不注意は考えられない。
明子のように人間を相手に商売しているならともかく、計画に沿っ
て着実に仕上げていく仕事なのだから。
それに、さっきは一瞬明らかに会話に詰まっていた。宏一との
関係なら宏一が言うように部屋に入っていても宏一は何も言わな
いだろう。そのために鍵までくれたではないか。明子の頭の中で
何か注意信号のようなものが点っていた。宏一の明子に対する気
持ちに嘘はない。絶対に信じられる。でも何かがおかしい。明子
に飽きてきたのだろうか。
そんなことも断じてない。女の感として、宏一は男の満足を得て
いることは分かる。明子はじっと紅茶のカップから上がる湯気を
見つめていた。
宏一が駅から飛び出すように出てきたとき、明子は只立ち尽く
していた。宏一はそれを、放っておいたので怒っているのだと思
った。
「ごめん、待たせちゃったね。お腹減ってない?何か買っていこ
うか?」
「もう、紅茶でお腹はガボガボよ」
「じゃあ、部屋に入ったら直ぐにシャワー浴びようか」
「もう、それが五時間も待たせた人に言う言葉なの?」
「ごめん、寂しい思いさせちゃったね」
「いいわ、行きましょう」
「うん、部屋についたら紅茶を入れるよ」
「そう」
明子は明らかによそよそしかった。二人は言葉少なに宏一のアパー
トへの道を歩き始めた。
明子の態度がどこか変だと言うことに宏一は気がついたが、そ
れは長時間待たせたからだと思っていた。『早く部屋に入って抱
きしめよう、それから何を話そうか』そんなことばかり考えてい
たので宏一の口数は少なかった。そして、明子の方から特に話し
かけるわけでもなく、ただ宏一の後をついて歩いていた。
明子の脳裏を思い出したくない想いが横切った。やっと立ち直っ
たばかりだというのに。まだあの一人の日々に戻りたくはない。
まだ誰かに側にいて欲しい。
宏一のアパートの入り口まで来たとき、明子は
「ごめんなさい。やっぱり今日は帰るわ。明日の朝は早いの」
と言った。
「えっ、帰っちゃうの。そんな・・・」
宏一は言葉を無くして思わず明子を見つめ直した。明子の表情か
ら感情が消えていた。明子は宏一を試したのだ。こんな事はした
くなかったのだが、やっと宏一との将来を考え始めていただけに
不安で仕方がなかった。
もし、宏一が無理に引き留めて明子を部屋に連れ込めば、何かや
ましいことがあるに違いない。宏一はこの程度のわがままは包み
込める男のはずだ。そう考えていた。
宏一はじっと明子を見つめていたが、
「分かったよ。今日は本当にごめんね。次にはきっと泊まっていっ
てね。いつでも心から待っているよ」
優しい声でそうつぶやくと、明子のほっぺたにチュッとキスをし
てトボトボと階段を上っていく。その後ろ姿を見て明子の胸を後
悔が突き上げた。『自分はなんていやらしい女なんだろう、なんて
ばかなことしてるんだろう』、そう思うと足が自然に宏一に向かっ
て歩き出した。
明子の軽快な足音が近づいてくるので、『え?』と宏一は振り
向くと、明子が腕の中に飛び込んできた。
「ごめんなさい。ちょっとわがまま言ってみただけ。しゃべらな
いで、お願い。何も言わずに部屋に連れてって」
宏一の胸に顔を埋めて明子がささやく。
「うん、うれしいよ。行こう」
「ごめんなさい、今日の私、少し変なの」
「いいよ、さぁ、行こう」
宏一は明子を抱きかかえるようにして部屋に入った。
部屋に入って鍵を閉めた途端、明子が唇を求めてきた。
「お願い、何も聞かないで、何も言わないで、このままシャワー
を浴びましょう」
宏一の耳元でささやく明子の声は震えていた。ぴったりと合わさ
った宏一の頬を温かいものが流れていく。宏一の頬に明子の涙が
流れているのだ。宏一は何が何だかよく分からなかった。自分の
言葉が原因だとは思ってもいなかった。
『何か辛いことがあったんだ。そっとしておいてあげよう』そう
思うと、ゆっくりとキスを続けながら明子の服を脱がし始めた。
バスルームの入り口でお互いに全裸になると、電気もつけずに
中に入ってシャワーを浴びる。明子の身体は小柄だが胸と腰の辺
りはふっくらとしている。
明子は宏一の首に手を回し、ぶら下がるようにしてしっかり抱き
ついていた。宏一は明子の小さな背中をゆっくりと撫で回しなが
らシャワーを明子の身体にかけていく。
明子は小さな声ですすり泣いていた。自分の中で宏一を疑って
いるもう一人の自分がいやだった。さらに、癒されたと思ってい
た心がまだ傷ついたまま直りきっていないことに気がついた。
それが何よりも悲しかった。
宏一にも何となく明子の気持ちが分かってきた。何も言わずに
泣いていることから、宏一に話したくないことに違いない。たぶ
ん、仕事のことではなく、心の中のことなのだろう。その程度の
想像はついた。今の宏一にできることは優しく抱きしめながらキ
スをすることだけだった。
ふと気がつくと、暗い部屋の中で明子がこちらを見ているよう
だった。
「もう上がりましょう。ありがとう。少し落ち着いたわ。もう少
し待ってね」
明子はささやくように言うと、シャワーを止めてバスタオルを手
にした。宏一が出ると無言で丁寧に拭いてくれる。
そのまま二人はベッドに倒れ込んだ。しばらく宏一の腕枕で火
照った身体を冷やしながらじっと抱かれていると少しずつ心が落
ち着いてきた。とにかく、宏一は今、明子のものなのだ。それだ
けは信用できそうだった。
「明子さん、いいかい?」
「ええ、少しだけね」
「今、僕と明子さんのことで考えていることがあるんだ」
「分かったわ、今はそれで十分、それ以上は言わないで。こんな
日に聞きたくないの。ごめんなさい、もう少し待って」
「分かったよ」
明子には宏一の言葉の向こうに待ち望んでいるものがあることを
直感した。心の奥が温かくなってきた。
『信じよう、とにかく信じよう』明子は宏一の腕をしっかり抱き
しめた。
宏一がかけ布団をそっと明子に掛けてくれる。うっとりと目を
閉じようとした途端、布団の中にあった空気が明子を包み込んだ。
『私たちの匂いじゃない!』
明子の目が暗い部屋の中で光ったようだった。明子は直ぐそこに
見える宏一の言葉を手にする前に、乗り越えなければならないも
のがあることを今初めてはっきり知った。
『勝ち取ってみせる。私の全てをかけて』
明子の目は暗闇を見通すかのようにまっすぐ前を見ていたが、疲
れて目をつぶっている宏一は全く気がつかなかった。
その夜、二人は身体を重ねなかった。宏一は旅行の疲れと仕事
の疲れからいくらも目を開けていられなかった。明子はしばらく
宏一に抱かれたまま目を開けていた。宏一の相手は誰なのだろう?
自分の将来を考え始めた矢先に、まだお互いを知り始めたばかり
であることを思い知らされた。明子は宏一にいろいろなことを話
しているが、宏一はあまり話していない。
明子は、宏一の心の中に自分が焦って飛び込もうとしているこ
とに気がついた。『今あわてると、後で後悔するわ。もうそんな
思いはいや。ちゃんと心の準備をしてからでないと』ともすると
くじけそうになる心を奮い起こし、明子の心の戦いが始まった。
『宏一さんの相手の人ってどんな人かしら?』分かるはずもない
問いが繰り返し浮かんでは消えた。が、いつしか眠りに引き込ま
れていた。
宏一はぐっすりと眠った。ここ三日間の疲れが一気に出たよう
だ。物音に気がついたらもう朝だった。明子は既に起きており、
あり合わせの朝食を作っていた。
「ごめん、昨日は直ぐに寝ちゃったみたいだね」
眠そうな声で宏一が明子に声をかけた。
「お早う。さあ、こっちでご飯にしましょう。何かごちゃ混ぜだ
けどできあがった所よ」
明子の声は明るい。
宏一は心の奥からぬくもりが沸き上がってくるようでうれしか
った。宏一が下着を付けて小さなテーブルの前に座る。明子はT
シャツ姿だ。
宏一は早く食べ終わって明子を抱きしめたくなった。しかし、
「さあ、召し上がれ」
そう言って宏一の前に並んだのは一人分の朝食だった。
「あれ?」
不思議そうに見る宏一に、
「ごめんなさい、もう出なきゃいけないの」
そう言うと、明子は身支度を始めた。
「だって、まだ7時前なのに」
「8時には行かなきゃバスに間に合わないわ」
「そんなに早いの?」
「だから昨日は7時から待っていたのよ」
それを言われると宏一は何も言えない。
「ごめんね」
それだけ言うと、黙って朝食を食べ始めた。明子が、
「それじゃまた電話するわ」
そう言ってハンドバックを持つと宏一は立ち上がって近づいてき
た。
『今はキスされたくない。私から嫌がるかも知れない。こないで』
明子は玄関に急いだ。しかし、靴を履き終わったところで宏一が
明子を抱きしめた。
宏一は顔を背ける明子の首筋にキスをすると、
「どうしたの?いやなの?」
と明子の耳元でささやく。宏一の息が首筋を撫で、明子の体中に
電気が走る。一瞬力が抜けてしまった。そのまま宏一は明子の顔
を自分に向けてキスをしてくる。『あ、だめ、今は』そう思いな
がらも唇を重ねられると身動きができなくなってしまう。
しかし、宏一の舌が明子に入ってきても何の反応もしなかった。
宏一が唇を離すと、
「じゃあ、また来るわね」
そう言って素早く部屋を出る。宏一は明子の目に何かが光ったよ
うな気がした。何かが変だとは思ったが、宏一にはどうしても分
からなかった。一人分の朝食を無言で食べ終わると、宏一も出か
ける支度を始めた。今日からは再び仕事が忙しくなる。
明子は、駅の近くまで来たときに、喫茶店が開いていたので中
に入るとモーニングを注文した。朝から目に涙を浮かべている明
子を不思議そうに見ながら店員が水を置いていく。
このまま宏一の前から消えてしまおうか、そんな思いが溢れそ
うになる。しかし、本当にそうなのかどうか少しだけ自信がなか
った。まだ宏一をどこかで信じている自分が情けないような気も
した。しかし、明子にとって宏一はもはや簡単に諦められるよう
な存在ではなかった。
宏一が明子にプロポーズするであろう事は想像できた。たぶん、
それまでに宏一は明子以外の関係を清算するはずだ。プロポーズ
しても他の女と関係を続けるほど恥知らずだとは思わなかった。
いや、思いたくなかった。何を信じていいのかよく分からなかっ
た。しかし、何かを信じなければ生きてゆけない。そして宏一を
信じる以外に明子には思いつかなかった。それはもっとも辛い選
択だった。
宏一は会社に着くと、気合いを入れてシステムを立ち上げた。
今日はやることが多い。まず最初に木下部長の横領額の概要をつ
かまなければいけない。本当は架空の取引の伝票や手形を実際に
集めなければいけないが、それでは監査になってしまうので密か
には行えない。
そこで、横領に使われている口座への入金の履歴を調べること
にした。しかし、まだ会社が小さかった頃の旧式のシステムなの
で、入金の記録は全て残っていたが、口座別にはなっていない。
仕方なく、全てをコピーしてから表計算ソフトで該当する口座だ
け抜き出してまとめる。
1時間ほどで概略はつかんだ。この1年間で約六百万。宏一は
この金額を元に戻すため、二百万は部長から返してもらい、二百
万は今回の宏一の仕事のリベートと残業手当から、更に二百万は
宏一の預金口座から下ろすことにした。
宏一の手で何とかなる金額だったので一安心だ。木下部長から
も返してもらうことにしたのは、こうしておかないといつまた同
じようなことを起こすかも知れないし、自分の体まで使って由美
が必死にがんばっているのに、のんきに横領を繰り返されてたま
るか、と言う率直な気持ちがあったからだ。
これから後、木下部長には宏一のプログラムに従って胃に穴が
あく思いをしてもらうことになる。宏一には木下部長に正義の鉄
槌を下すなどと言う考えはなかった。
胃に穴があく思いをするのは宏一も同じなのだ。只、今の宏一に
は由美がいてくれる。部長には一人で苦しんでもらうが、今まで
美味しい思いをしてきたのだから結局同じ事だ、と考えていた。
更に午前中はあちらこちらに電話をかけ、価格や納期を調べて
宏一の修正プランを完成させた。ふと時計を見ると一時近い。あ
わてて会社の地下の商店街で天ぷら蕎麦をかき込むと、プランを
持って総務部長室を訪ねた。
しかし、総務部長は来客中だったので、購買部長を訪ねる。
購買部長は、宏一の話を聞くと露骨に不快な表情をした。もと
もと購買部長にしてみれば、宏一に任されていることとは言え、
自分を通さずに勝手にお金が出で行くので、その分の手当だけで
も大変なのだ。この上更にシステムにお金をかける必要があるの
か、購買部長には納得できなかった。
「結局、将来の投資を効率的に行えると言うだけで、今のお金
に更に五百万足せと言うんだね」
「はい、今これを入れておけば、将来の二重投資が防げますし、
回線容量にも十分な余裕がありますから社内用のインターネット
や会議システムにも大したお金はかかりません」
「しかし、ねえ、今のままのシステムではだめだというのなら仕
方ないが、今のままで十分なのに更に金額を上乗せするのはねぇ。
もちろん、三谷君の責任に於いてやってもらってかまわないんだ
が、私としては疑問を出さざるを得ないな」
購買部長は最後まで首を縦には振らなかった。宏一の人材派遣
会社との取り決めでは宏一の裁量に任せられているのだから、宏
一が押し切っても文句は言えないのだが、これを無視して突っ走
ると大抵後で良くないことが起きることを宏一は知っていた。
しかし宏一は、自分が全て決められると思っていたからまさか
購買部長が納得しないと言うのは想像していなかった。こんな所
で時間をかけている場合ではない。宏一は少し焦った。取りあえ
ず、ネットワーク以外の部分についてできることを先に済ませて
しまう。
宏一はどうすれば納得させられるか考え続けた。しかし、会社
経験の少ない宏一は大義名分だとか名目だとか言うものには慣れ
ていなかったから、どうしても機能や価格で納得させることぐら
いしか思いつかない。
しかし、機能と価格では既に前の簡単なシステムで納得させてあ
るのだから、『あの時はそう言いましたが、今改めて考えますと
・・・』と前言を翻さないと話が続かなくなる。そんなことをす
れば信用をなくしてしまい、今後の仕事がやりにくくなる。
猛烈な勢いでキーボードをたたき、電話をかけまくるかと思え
ば、じっと考え込んだまま身動き一つしない、と言うような、周
りから見ると奇妙な状態がしばらく続いた。しかし、周りの社員
は、宏一の仕事はそんなものだ、と思っているのか特に不思議に
も思わないようだ。
午後もだいぶ時間が過ぎた頃、木下部長はパソコンの前に座っ
た。何気ない操作で例のワークシートをチェックしてからいつも
のように架空取引を入力し終わり、保存操作をする。しかし、保
存画面にいつもと違うファイルがあることに気がついた。
『木下メモ』と書いてあるファイルを開くと、小さな文章が一言
だけ書いてあった。
「表計算の中にマクロでかき込むとは考えましたね」
それだけである。木下部長は自分の顔から血の気が引いていくの
が分かった。ここのパソコンはネットワークにつながっていると
は言え、まだ普通の共用パソコンでしかないので、NTのように
各人の専用の環境にそれぞれ個人用の保護を掛けることはできな
い。従って、その気になれば誰でも木下部長のディレクトリへの
中をいじることはできる。
宏一は、何食わぬ顔で部長が終了操作を終えて席に戻るのを横
目で見ながら、『さすがに部長ともなると顔には出ないものだな』
と感心していた。しかし、今日の宏一にはそんなことにかまって
いる暇はない。更にシステムの仕上げのピッチを上げた。
そのころ明子は電話をじっとにらみながら考え事をしていた。
今日は宏一に電話をしようかどうか迷っていたのだ。次の日曜日
から宏一は九州に旅行に行ってしまう。
その前に宏一と一緒の時間を作りたかった。しかし、明子の勤務
の関係で今夜以外は確実な時間が見つけられなかった。土曜日に
うまく行けば時間が作れそうだったが、天候や渋滞などで時間が
延びれはそれも危ない。
電話で宏一の声が聞きたかったし、できれば今夜は宏一の部屋
で過ごしたかった。しかし、昨夜のことが頭に浮かぶとどうして
いいものか分からなくなってしまう。せめて、明子が気付いてい
ることは宏一に知られたくなかった。
こんな風にウジウジしている自分が一番いやだった。
「えいっ」
と一言気合いを入れて受話器を取り、宏一の携帯の番号を押す。
二回のコールで宏一が出た。
「もしもし、宏一さん?どうしてる?」
「あぁ、今日は朝から大変だよ、おっと失礼」
宏一は話しながら移動しているようだ。まだ会社の終業時間前な
ので受話器にはいろいろな音が入ってくる。そのうちに静かな部
屋に入ったらしく、雑音は聞こえなくなった。
「何時頃帰れるの?」
「今日は大体一時ぐらいになりそうだな。どうして?」
「ううん、何でもないの、昨日はごめんなさいって、それが言い
たかっただけだから」
「何を言ってるの、僕の方こそすぐに寝ちゃってごめんね。今日、
良かったら家にこない?」
「何言ってるの、一時になんて無理よ、遅すぎるわ」
「前にもそれくらいの時間になったじゃない」
「あの時は特別、いつも一時にされたんじゃかなわないわ」
「そうか・・・、じゃあ、十一時にだったらどう?気合いを入れ
てそれまでに終わらせるよ」
これ以上のスピードなど無理だったが、宏一も明子の肌が恋しか
った。
「だめよ、そんなこと言って、また無理すると、せっかく会って
もすぐに寝ちゃうから」
「そう言われると厳しいな、大丈夫だよ、寝たりしないから」
「ううん、いいの。また今度にする。声が聞けただけで満足。
ごめんなさいね。邪魔しちゃって」
「いつでもいいよ、待ってる」
「ありがと、じゃあね」
明子は電話を切ると、ふぅーっと息をついてイスにもたれかかっ
た。
いつもと変わらない宏一の声だった。考えてみれば、明子が気
がついただけで、宏一はそのままなのは当然である。しかし、却っ
てそのままなのが明子の心を重くしてしまった。
『今までも宏一さんはこうして私を抱いてきたんだわ。私もその
まま抱かれてきた・・・』
身体の力が少しずつ抜けてくるようだ。自然に目が潤んでくる。
宏一のおかげでやっと自分のプライドを取り返せたというのに、
そのプライドが明子を再び苦しめている。何も考えずに宏一の腕
に飛び込めたらどんなにいいだろう。明子はじっと机を見つめ続
けていた。
トップ |