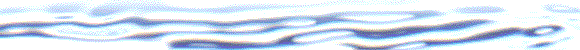「あの、私が旅行に行くときに、一緒にいくことにしてあった
子、一枝ちゃんて言うんですけど、その子に京都から電話をかけ
たんです」
「ああ、ホテルの部屋から携帯で話していた子だね」
宏一は、あの時の由美の乱れ方を思い出しながら頷いた。由美は、
一枝に昨日会ったときのことから話し始めた。
昨日の月曜日は、図書館で勉強してから、一枝にお土産を渡し
に行った。一枝の家は少し遠かったので二人で途中で待ち合わせ
をして喫茶店に入った。少しは覚悟していたが、ちょっぴりほの
めかすように自慢できるような気もして、余り深刻には考えてい
なかった。しかし、一枝の質問責めは強烈だった。一枝はケーキ
とコーヒーが揃ったところで早速追求を開始した。
「ゆん、覚悟はいいわね。私にアリバイづくりの共犯をさせて、
あんな電話かけてくるなんていい根性だわ」
「ごめんね、一枝ちゃんが怒ったのなら謝る。本当にごめんなさ
い」
「怒ったのならですって?あんな電話聞かされて普通でいられる
と思うの?」
ここで初めて由美は電話で由美の声が筒抜けだったことを確信し
た。
「ごめんなさい。宏一さんが電話の最中に私に・・・・」
「私に、何よ。言ってご覧なさいよ」
由美は真っ赤になってうつむきながら、
「私に触ってきたから・・・」
「それで嬉しくてあんな声出したわけ?」
「ごめんなさい。一枝ちゃんにわざと聞かせようとした訳じゃな
いの。途中から訳が分からなくなって・・・」
それは一枝にも分かっていた。もともと一枝は、由美が得意げ
にそんなことを自慢するような子ではないことくらい十分知って
いた。
たぶん、由美には悪気はなく、相手の思い通りにされただけなの
だぐらいの予想はしていた。しかし、それはそれとしても、もう
少しいじめないと気が済まなかった。
「訳が分からなくなって?それでどうしたの?」
由美はどう言おうか言葉を無くした。
「ゆん、ちゃんと答えて。それでどうしたの?」
由美は小刻みに奮えている。
「そう、答えられないわけね。それが協力して外泊までした私へ
のゆんの返事な訳?」
少しかわいそうかとも思ったが、一枝は由美をこれくらいはいじ
めてもいいだろうと思った。
由美は、自分で予想した以上に一枝が怒っているのに戸惑って
いた。一枝にこんなに辛く当たられるのは初めてだった。必死に
謝った。
「ごめんなさい。一枝ちゃん。分かってるじゃないの。電話で聞
いていたのなら。ごめんなさい」
何度も頭を下げて謝る由美を見て、一枝もそろそろ許してやるか、
と思い始めた。
「分かったわ。でもね、私がどんな思いで聞いていたと思う?
少しくらい怒ったって当然でしょ」
「うん、分かる。許して、ごめんね、本当に」
由美は一枝が許してくれるものと思って少しほっとした。
「だけど条件があるわ。まず、全部その人とのことを聞かせて。
それからどうするか考えるから」
一枝は、興味もあったが、少しだけ由美のことも心配していた。
もしかしたら、悪い男にだまされているのかも知れない、と思っ
たのだ。
由美は観念した。一枝がそう言う以上、納得するまで教えない
と他の人に話される恐れがある。話に尾ひれが付いて広まったら
大変だ。
それに、ほんの少しだけ一枝に対する優越感もあったから、由美
は最初からゆっくりと一枝に話し始めた。一枝は、出会いの不自
然さに驚いたが、由美の目を通してみる宏一はさほど悪人とは思
えなかったので、興味は次第にセックスの方に向いていった。
「で、いつ頃最後までいったの?」
「ゆんはどれくらい痛かったの?」
「それからもいつもしてるの?」
「ゆんの方から挑発したことはあるの?」
「ね、どんな風に入れてくるの?」
「いく時ってゆんはなんて言うの?」
容赦のない一枝の質問に、真っ赤になって小さな声で答える由美
は、誰かに聞かれるかも知れないと気が気ではなかった。しかし、
宏一が二人目だと言うことは黙っていた。
大体話を聞き終わると、一枝は考え込んだ。かなり変な話では
あるが、遊ばれているようでもない。相手を盲目的に信用してい
る由美ほどではなかったが、一枝も納得することにした。そして、
この三日間考えてきたアイデアを話すことにした。
「ねえ、ゆんは私がこのこと誰かに話すかも知れないと思って
いるでしょ」
「そんなことない。一枝ちゃんはそんなんじゃない」
そうは言ったが、言葉にあまり力がこもっていなかった。
「私だったら、すっごくしんぱいするわ。だって、思わず口に出
すことだってあるでしょう?」
「ま、まさか、一枝ちゃん、これだけ全部話したのに。そんな」
「大丈夫よ、少し脅かしただけ」
「もう、びっくりさせないでよ」
「だから、そんな心配しなくてもいい方法があるの。私も共犯
になればいいのよ」
「え?共犯?アリバイの?」
「違うわよ、私もゆんと同じ事をすればいいのよ、宏一さんと。
そしたら共犯でしょ?」
「え?一枝ちゃんと宏一さんが?そんな、だって宏一さんは」
「あなたの彼氏よ。それは認めるわ。でも、それじゃ私はいつも
損な立場だわ。私に少しの間だけ彼を貸して、それでおあいこに
しよ」
「そんな事って・・・・」
由美は愕然とした。宏一を貸すなんて、そんなことできるはずが
ない。第一、由美がもし承知しても宏一が断ったらどうするのか。
もちろん由美は承知するつもりはなかった。そんな事するくらい
なら噂をばらまかれた方がましだ。絶対に受け入れられる条件で
はなかった。
「ごめんなさい、それだけは・・・・。絶対にだめ」
由美は覚悟を決めてゆっくりと言った。
「だめよ、ごめんなさい」
もう一度はっきりと言った。しかし、一枝も黙ってはいなかった。
「ゆん、私のことも考えてよ。あれを突然聞かされてどうなった
と思う?身体が火照って仕方なかったわ。これから毎日ゆんの顔
を見る度に思い出すのよ、あの時のゆんの声を。忘れろったって
無理よ」
「それだけは許して、他のことなら何でもする。お願い」
由美は必死に逃げ道を探した。
「だめよ。まず彼に会わせて。それでもし彼がいいって言えばゆ
んも文句無いでしょ」
一枝は由美に頼んでもだめなことは最初から分かっていたので、
宏一に交渉するつもりだった。処女を卒業させてくれるだけでい
いのだから、男が拒否するはずがない、そう計算していた。
「そんな・・・、私、困る」
「私だって困っているのよ。これからもゆんと仲のいい友達でい
たいから、私だけ取り残されるのはいやなの。分かってね。言っ
ておくけど、私のピッチには録音機能が付いているのよ、ゆんも
知っているわね」
一枝はそう言うと、由美の土産の京都の和菓子の包みを解き、盛
んにほめ言葉を言い始めた。しかし、由美にはほとんど聞こえて
いなかった。
確かに、先月、一枝が最新型を買ったときにそう言って自慢して
いたのを思い出した。『録音されているのかも知れない』そう思
うだけで背筋がぞっとした。
由美がそこまで話し終わると、宏一は、由美の話をどうした
ものか考え込んだ。男としてみれば、向こうの方から処女を奪っ
て欲しいというのならさほどいやな話でもない。しかし、由美の
表情を見るととてもOKはできそうになかった。それに、相手の
言うなりになってしまうと言うのも面白くない。これを引き受け
れば、一枝が相手をして欲しいと言ったときにはいつでも引き受
けなければならなくなるだろう。
今では宏一も由美を愛していた。由美の泣き顔は見たくなかっ
た。
「由美ちゃん、困ったことになったね。あんなことしなければ良
かったよ、ごめんね」
「ううん、私が宏一さんに夢中になって電話のことをいい加減に
したのがいけなかったんです」
由美は、あくまで自分が悪いと言った。
「それで、一枝ちゃんはどう言ってるの?」
「あの、今度の木曜日のこの時間に宏一さんに会ってお願いする
って、そう言ってました」
「困っちゃったね。どうやって諦めてもらうか、相談しなくちゃ
いけないね。木曜日に少し早く来れる?」
「あの・・・・もし、宏一さんがいいのなら、私、大丈夫です。
我慢できます」
「だって、由美ちゃん、そんなのいやだろう?」
「私、宏一さんのこと、本当に好きなんです。宏一さんが私のこ
と、大切にしてくれるのはとっても嬉しいんです。でも、宏一さ
んが一枝ちゃんのこと、いいって言ってくれるなら、その方がい
いような気もするんです」
下着姿のまま、そう言っている由美の頬を涙が流れ落ちた。それ
でも由美は宏一に笑顔を作っている。
一生懸命笑顔を浮かべている由美の気持ちを踏みにじるような
まねはしたくなかった。由美がいてくれれば十分だった。しかし、
一枝を怒らせて噂をばらまかれても困る。証拠は確認していない
のだから、確認した上で突っぱねることもできないではなかった
が、由美が学校で辛い思いをすることを考えるとどうも得策には
思えなかった。
話し終えた由美が時計を見るとすでに8時を回っていた。ずっ
と一緒にいたかったが、帰らねばならない。由美は服を整えると、
宏一の首に手を回してきた。宏一はなにも言わず、二人でゆっく
りとキスをした。お互いの気持ちが十分に伝わる、心のこもった
キスだった。
部屋を出た由美は、駅に向かって歩き始めた。駅が近づいてく
る頃、由美のすぐ横に並んで歩く人影に気が付いた。
「一枝ちゃん?私を待ってたの?」
「そうよ、この辺りを通ると思って、コンビニで本を見る振りし
て待ってたの。宏一さんに話をしてくれた?」
「ええ、木曜日に三人で会うことにしたわ」
「そう、ゆん、怒ってるでしょ」
一枝は由美の顔をのぞき込むように言った。
昨日、由美に会ってから、一枝は『少し言い過ぎたかな』と後
悔していた。しかし、あれくらい強く言わないと一枝の願いを聞
いてくれないだろうと言うことも分かっていた。
あれやこれや考えたあげく、由美の様子を見に来たのだ。一枝
だって由美のことは大好きだった。もともと一枝のわがままなの
だから、こんな事で大切な友達を失いたくなかった。だから、由
美が思いっきり怒ってくれれば大人しく謝って忘れるつもりだっ
た。
「怒っているって言うより、困っちゃって」
由美は力無くそう答えた。
「あなたってほんとにお人好しなのねぇ。わたし、ゆんにぶたれ
るかと思ってビクビクしてきたのに」
「私が?一枝ちゃんを?どうして?」
「あなたには呆れるわ。彼氏を寝取られようとしてるのに私にそ
んな優しくしなくたって・・・」
そう言う一枝に、由美は少し力を込めてはっきりと言った。
「たとえ一枝ちゃんと寝たって、私と宏一さんの関係は同じよ」
その言葉にはわずかに棘が含まれていた。もともと大好きな一枝
に対する由美の精一杯の抵抗だった。
「あなたねぇ、男と女の関係なんてそんな綺麗なものじゃないわ
よ」
「一枝ちゃんはそう思うの?」
「新鮮な身体が目の前にあれば、大抵の男はなびくものよ。たと
え木曜日に宏一さんに断られても、私がゆんに隠れてこっそり会
いに行けば、まず間違いなく抱いてくれると思うわ」
一枝も言葉の中に棘をちりばめて由美に返した。由美の世間知ら
ずをののしったようで後味が悪かった。
「私はそうは思わない」
由美はもう一度はっきりと言った。一枝には由美の挑戦のように
響いた。
「宏一さんは真っ先に私のことを心配してくれたわ」
「それはそうでしょう。ゆんが目の前にいるんだから。でも、私
がこっそり会いに行ったら、いやとは言わないと思うわ」
一枝も言い返した。そう言わないと自分の立場がなくなってしま
うような気がしていた。
由美は、一枝の前に立ち止まると、初めて一枝をにらみ付けた。
一枝がびっくりするほど怖い目つきだった。
「一枝ちゃん、宏一さんに会ってから話した方がいいと思うわ。
木曜日の五時半にさっきのコンビニで会いましょう。このままじゃ
話が繋がらないもの。これ以上話をしても無駄だと思うわ」
「人が心配して様子を見に来たのに。いいわ、どうせお楽しみ
の後だから、身体が満足してるから、そんなこと言えるのよ。今
夜も思いっきり楽しんだんでしょ。ゆん、髪が乱れたままよ。身
だしなみくらい整えてね。みっともないわよ。じゃあ、あさって
五時半ね。バイバイ」
一枝はそう言うと、由美を追い越してさっさと行ってしまった。
由美は、猛烈に怒った。今までこんなに怒ったことはないくら
いの激しい怒りだった。『絶対に宏一さんは渡さないわ、どんな
ことになっても』そう心に言い聞かせた。『今まで仲良くしてき
たのに、その私の大切な宏一さんを横取りしようなんて、あんな
人だとは思わなかった』帰りの電車の中で悔しさと怒りで涙が止
まらなかった。
翌日も宏一は朝早くから仕事を始めた。まだかなり疲れていた
が、由美の体でストレスを解消していたので気力は十分だった。
仕事の合間にふと友絵のことが頭に浮かんだが、用事もないのに
総務部に行くことはできない。友絵もそれが分かっているからこ
の部屋にやってきたりはしないのだ。
木下部長は何食わぬ顔で仕事を続けているようだが、午前中だ
けで三回もパソコンの前に座って何かやっているところを見ると、
やはり謎のメールが気になって仕方ないようだ。今日はお昼過ぎ
に、
「このことを知っているのは何人いるんですか」
と言うメッセージと共に、先月の横領金額の一覧の付いたファイ
ルが届くようになっている。『もう少し我慢してもらいますよ』
と、宏一は胸の中でつぶやくと、仕事に戻った。
昼食に外に出るとき、友絵をちらりと見かけたが、向こうは気
付かないいようでそのまま同僚と出て行ってしまった。宏一は後
から付いていって偶然を装って同じ店に入ろうかとも考えたが、
友絵が困るだけだと思い、近くのそば屋で軽く済ます。
総務部長と約束した講習の準備は来月に入ってから始めればい
いことなので、当面の仕事をどんどんこなしていく。宏一の周り
にいる営業3課の仲間にも、宏一の迫力が伝わったらしく、時々
女性がお茶を入れてくれる他は近づいてこようとしない。宏一は
勢いに乗ったまま8時近くまで仕事をこなし、会社を出てそのま
ま洋恵の家に向かった。
今日は洋恵に切符を渡すことになっている。洋恵は宏一と勉強
を始めると、嬉しくて仕方がないと言ったように甘えてくる。
「ねぇ、先生、お母さんがね、今になってもまだ船は酔ったりす
るから飛行機の方がいいんじゃないかって言うの。船の方がずっ
とロマンチックなのにね」
「そうか、お母さんの心配はもっともだね。だけど、ほら、見
てごらん、この船、凄く大きいだろ?長さが百五十メートル、一
万二千トンの船だよ。えっと、わかりやすく言うと、洋恵ちゃん
の中学の校舎よりも大きいんだ」
宏一はそう言って切符と一緒に持ってきたパンフレットを見せた。
「えーっ、そんなに大きいの?だって、うちの学校四階建てだ
よ」
「ははは、この船の窓を見てごらん。見えるだけで四階あるだろ?
この下に乗用車デッキとトラックのデッキ、そのまた下に機関室
があるんだよ」
「すごーい、じゃあ、学校何かよりずっと大きいんだ」
「そうだよ。たぶん、倍以上あると思うよ」
宏一は洋恵の中学を見たわけではなかったが、確かにこの高速フェ
リーはそこらの学校よりは大きかった。
「後で渡すつもりだったけど、これが切符だよ」
そう言って乗船券と二等寝室の切符を見せた。
「わぁっ、これが切符なの、お母さんに見せてくる」
そう言うと、部屋を出て下に降りて行ってしまった。あまりに単
純に喜んでいるので宏一は苦笑した。すぐに下から足音が聞こえ
てきた。今度は母親と二人のようだ。
「どうもすみません。切符まで手配していただいて。これはそ
の分のお金です。それと、こっちはご迷惑をおかけする分のお礼
です」
そう言って宏一に封筒を二枚渡した。
「そんなお礼なんて結構ですよ。それじゃ、これは洋恵ちゃんに
渡して、向こうのご親戚の方に何かお土産でも買われたらいかが
ですか」
「そうよ。それがいい。私、明日何か買ってくる」
洋恵が高価な買い物ができると喜ぶと、
「いいえ、洋恵なんかに渡したら無駄になりますから。それにも
うお土産は買ってあるんです。先生に受け取っていただかないと、
主人にも怒られますし」
と、あくまで渡すつもりのようだ。
「分かりました。あまり固辞するのも失礼ですね。ありがたく
頂きます」
そう言って宏一はありがたく封筒を受け取った。それからしばら
く、母親にパンフレットを見せて、スタビライザーを装備してい
るので、よほど天気が悪くないと大して揺れないことや、泊まる
部屋の様子などを説明した。
母親は今まで気になっていたことを全部聞いてしまおうと、細
かいことまで丁寧に聞いてくる。二等寝室の部屋がカーテン付き
の二段ベッドの十人部屋だと聞いて母親も納得したようだ。
「洋恵が騒ぐようだったら、遠慮なくバチーンとやって下さって
結構ですから」
そう言って笑いながら下に降りていった。
実は、洋恵に渡した切符は、親を納得させるためのもので、
本当の切符は一等の切符を取ってあった。もちろん、今説明に使っ
た、使わずに捨てることになる二等寝室の切符は本物で、乗船直
前に上手く時間がとれればキャンセルするつもりだった。一等の
二人部屋にしないと洋恵を処女から卒業させることはできない。
母親がお茶を運んでくる時間になっても洋恵は宏一と船の話や
九州の話をしていた。洋恵があまり楽しそうに話をするので宏一
もそのままにしておいた。
お茶を飲み終われば二人の時間になる。しかし、お茶とケーキを
済ませても、洋恵は勉強を始めようとはしなかった。何かわざと
避けているようだ。
「さあ、洋恵ちゃん、少しは勉強しておかないと。来週はずっ
と遊んでいるんだから。さぁ、始めようか」
宏一にそう言われると洋恵はいやいやながらノートを開いた。し
ばらく勉強してから、宏一がいつものように脇から手を入れてい
くと、ビクッと身体を堅くして
「いや、だめ」
と脇を強くすぼめる。
「どうしたの?いつもこうされるのが好きなのに」
「今日はいや、そんな気分じゃないの」
そう言っていやいやをする。
宏一はどうしてさっきまであんなに楽しそうにしていた洋恵が
突然変わったのかが理解できなかった。それでも、ゆっくりと膨
らみを撫でていると、少しずつ幼い乳房は堅く膨らみ始めた。い
つもならこの辺りで洋恵が快感をこらえているのが分かるのだが、
今日は全くそんな様子がない。どちらかと言えば辛そうな顔をし
ている。
軽く両手で乳房を握ってみると、「クッ」と一瞬表情を変える
が、とても喜んでいるようには見えない。しかし、洋恵の身体は
正直に宏一に対して反応していたのだ。洋恵はこの快感を楽しめ
ないことが辛くて悲しく、早く宏一が諦めてくれないか、それば
かりを待っていた。
宏一がしばらく洋恵の膨らみをかわいがっていると、何かツン
とした匂いが鼻を突いた。何とも言えない、生臭いような、酸っ
ぱいような匂いだ。その瞬間宏一は洋恵が嫌がる理由を理解した。
そっと両手を抜き、
「ごめんね。もうしないからね。ごめんね」
と謝りながら優しく髪を撫でる。洋恵は、『分かってしまった』、
と思いながらも優しく撫でられる髪の感触に安心して目を閉じて
いた。
トップ |