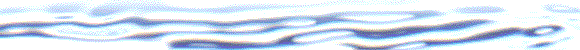洋恵は、水曜日ほど宏一を避けてはいなかった。しかし、宏一
が触ろうとすると、
「ごめんなさい、明日まで待って。ねえ、先生、明日だったら、
夕方に先生の所にいけるから、明日にして」
と言った。宏一がどうしようか迷っていると、
「ね、まだ身体の準備ができてないの・・・」
と恥ずかしそうに小さな声で言った。
宏一がまだなにも言わないので、洋恵は椅子を降りて宏一の前
に跪いた。
「でもお口でしてあげるから、ね」
そう言うと、ジッパーに手をかけた。宏一は洋恵のされるがまま
だった。洋恵はトランクスの中から小さくなっている肉棒を取り
出すと、口の中に入れた。丁寧に口の中で転がしたり舌で舐め上
げたり、一生懸命に宏一を満足させようとする。
宏一は携帯を忘れたことに気が付いていた。それが友絵の所に
あることが気になっていた。たぶん、宏一に渡さなかったことに
気が付いているだろう。
そのまま机の中にでもしまっておいてくれればいいのだが、たぶ
ん友絵は宏一に渡そうとして携帯を持っているのではないか。明
子が電話をしてこなければいいが・・・、そればかり考えていた。
洋恵は、宏一の肉棒が正直に反応を始めると嬉しくなった。口
の中で小さかったものは、次第に大きさを増してきた。もう口に
は全てはいらない。
「んんーっ、んん」、
洋恵は肉棒の劇的な変化にいつもながら驚いていた。今までは、
半分程度まで膨らんでいたから最初からかなり大きかったが、今
日は最初がとても小さかったので、どこまで大きくなるのかと驚
いてたのだ。
洋恵は、一旦口を離すと、手でしごきながら、
「先生、気持ちいい?」
ニッコリ笑ってそう言った。
「ああ、とってもいいよ。洋恵ちゃんのお口の中に出していいの
かな?」
「ウン、飲んじゃうから」
そう言うと、再び肉棒を含み、頭を小刻みに動かす。由美ほど口
が小さくないので半分以上は飲み込まれてしまう。
「洋恵ちゃん、もうすぐだよ。いい?出すよ」
そう言うと、洋恵の頭を両手で止め、最後だけは自分の腰を動か
す。宏一がぐっと肉棒を差し込んできたので洋恵は吐きそうになっ
た。そこになま暖かい液体が飛び込む。
「グフっ、ゲッ、ゴホッ、ウッ」
必死に涙をこらえながら飲み込んでいた洋恵だが、小さくなって
いく肉棒も優しく舐めて、最後にしみ出す分まで優しく飲んでく
れた。
翌日の土曜日の午後、宏一は膝の上で洋恵を横抱きにして、熱
い息をしながら悶えている洋恵を楽しんでいた。明日の夜には思
いっきり抱いてやれると思うと、丁寧に最後の準備をしておくこ
とにした。
それは、宏一が欲しくなるようにギリギリの所で我慢させておく
ことである。単に焦らし続けたのでは途中で反発されて身体が全
く反応しなくなることを知っていたので、あくまで優しくしなが
ら我慢させることが大切だ。
宏一の指が洋恵のすでに堅く膨らんでいるTシャツの上をゆっ
くりとなぞっていく。
「あう、先生、イヤン、こんなの、早く、早くぅ、して」
洋恵は宏一の膝の上で身体をくねらせて催促する。
「まだだよ、洋恵ちゃんの身体が明日一番感じられるように、
ゆっくりと慣らしておくんだからね」
「あん、そんなの、あうん、だめ、ちゃんとして、明日も、いっ
ぱい。あーん、恥ずかしい、ねぇ、先生、早くぅ、優しく、ね、
脱がせて」
そう言いながら、洋恵はゆっくりと自分でTシャツの裾をまくり
上げ、宏一に身体をさらしていく。
「いいかい、今日はここまでだからね。今日一日我慢すれば、
明日は今までよりもっと気持ちよくなれるから。だから我慢しよ
うね。先生だって我慢しているんだよ」
宏一は優しく洋恵の肌を撫でながら我慢するように要求した。
自分からブラジャーの上まで捲り上げた洋恵は、
「いや、ちゃんとしてくれなきゃ、先生、もう少し、いいでしょ、
明日もちゃんとできるから。ね、体が熱くなってきたの、ね、い
じわるしないで。今日まで待ってたのにぃ」
そう言いながら宏一の手を胸の膨らみに導く。軽く撫でてやると、
「はあっ、いい、先生、気持ちいい」
といいながら身体をくねらせる。すでに目は潤んでおり、両足を
擦り合わせて我慢している。
どうやら、由美の時のようには行かないようだ。
「どうしてもこのままじゃ我慢できないの?」
「うん、先生がこんな身体にしたのよ」
洋恵は喘ぎながらもっと先を要求する。
「じゃあ、一回だけだよ、いいね」
「うん、我慢する。だから、ちゃんとして、優しくいっぱいして」
「悪い子だ。こんなにおねだりばかりして」
「先生がしたのよ。こんないけない子にしたくせに」
「じゃあ、ベッドに座りなさい」
宏一は洋恵をベッドに座らせると横に並んで座り、後ろから抱き
かかえるように両手を脇から入れ、ゆっくりとブラジャーに包ま
れた膨らみを撫で始めた。
「我慢できなくなったら言うんだよ。お口で行かせてあげるから。
今日はこれ一回だから、いっぱい我慢するんだよ」
今まで宏一の部屋に来たときは、時間の許す限り何度も感じさ
せてくれた。だから、洋恵は一回だけでは明日まで我慢できる自
信はなかったが、宏一に言われたとおり、できるだけ我慢して快
感をたくさん得ようとした。
堅く膨らんだ乳房は宏一が優しく撫でるだけで快感の予感を沸き
出させる。宏一はお気に入りの乳房の下側の膨らみを確かめるよ
うにゆっくりと何度も撫で上げ、時々、ほんの少しだけ軽く揉ん
だ。すると洋恵は、あ、と軽く口を開くが、すぐに口を少しだけ
すぼめるようにして耐えている。
「はあっ、うっ、はっ、先生、もう少し、ね、もう少し、ね、強
くして」
もう少し強く揉んでもらえれば身体を快感が駆けめぐることを知っ
ているので身体をくねらせて宏一の手に幼い乳房を押しあて、な
んとか快感を作り出そうとする。
宏一は、洋恵の身体の感度が少しずつ上がってくるのにあわせ
て愛撫を少しずつ弱くしていった。
「いや、こんなの、はあっ、あぁ、お願い、ちゃんとして、優し
く、ね、もう、だめ、我慢できない、先生、早く、して」
洋恵は宏一にすがりつくように身体をこすり付けてくる。
「じゃあね、このまま後ろにゆっくり倒れてごらん」
宏一はそう言って洋恵をゆっくり後ろに倒してベッドに横たえると、
「今はとっても敏感になっているから、自分で触ったりしたらだ
めだよ、いいね」
そう言い聞かせ、洋恵の足下に跪いてパンツを脱がせ始めた。
「あ、いや、まずこっちからして、先生、胸から、下はまだい
や」
洋恵は力の入らなくなった体を使って宏一に抵抗しようとしたが、
スルッとパンツを脱がされてしまう。宏一が洋恵を舐め上げる体
勢を作ってから、両手で乳房を揉むように胸に手を伸ばしてきた
ので、
「このままするの?ブラも外して、ね、いいでしょ?」
とおねだりする。宏一は洋恵のおねだりを無視してブラの上から
最後の仕上げの愛撫を始めた。
「アアン、お願い、外して、このままじゃ、いや、外して、早
く」
身体を激しくくねらせながら洋恵は何度もおねだりをした。宏一
の目の前にある秘唇からは、すでに大きく膨らんだ秘核が頭を出
しており、秘口からはとろりとした液体が収縮するたびに吐き出
されている。
明子は、宏一の部屋の前まで来て足を止めた。宏一に渡された
鍵を取り出してから、差し込もうとしてふと考えた。このまま入
ろうかと思ったのだが、どうもいやな予感がする。
仕事の合間を縫ってきたので、3時間ほどしか一緒にいられない。
だから、宏一がいなければ夕食だけ作って立ち去るつもりだった。
部屋の中からは何も聞こえないが、何となく躊躇した。そこで、
一旦アパートを出ることにした。
「さぁ、はじめるよ」
そう言うと、宏一はブラジャーに包まれたままの乳房をゆっくり
と握っていく。
「あーっ、いいーっ、でも、あーっ、もう、いや、ねーっ」
洋恵の声が一段と高くなると身体がブリッジを作ってのけ反るの
が分かった。しかし、宏一はまだ舐め始めない。宏一の息が秘核
にかかる度に甘くじれったい感覚が沸き上がってくる。
「先生っ、我慢できないっ」
そう言うと、洋恵は身体を大きくくねらせる。
すると、ブラジャーがフッと緩くなり、洋恵の手が宏一の手を
ブラの中に導く。どうやら自分でブラを外したようだ。
「はーっ、アアン、やっぱりいい、これがいいっ」
安心したように洋恵の身体が悶える。『仕方のない子だ』そう思
いながらも堅く膨らんだ乳房をゆっくりと何度も揉み込み、快
楽を増幅させる。
乳房を揉まれる感覚に慣れてくると、宏一が舐め上げる体勢を
作ったまま息を秘核にかけられているので足を擦り合わせること
ができない洋恵は、腰の辺りのじれったさが頂点に達した。
「先生っ、もうだめ、早く、早く舐めて、いっぱい、早くっ」
洋恵の手が宏一の頭に伸びてくる。
「ちゃんと言いなさい。どこを舐めて欲しいの?言ったらいっぱ
いして上げる」
宏一が最後の命令を出した。
「いやぁ、そんなの、早く、はやくぅ」
洋恵は気が狂いそうなもどかしさに我慢できなくなっていたが宏
一の頭をグッと押しても腰を突き上げて迎えに行っても宏一はよ
けてしまう。
宏一がそう言ったからには、恥ずかしい言葉を言わなければ舐め
てはくれないことが分かっていた。そして、言えば必ずしてくれ
ることも。
「も、もう、いや、ク、クリトリスを舐めて、私のクリトリス
を、早く、あ、ああっ、凄いっ、あーっ」
宏一が軽く舌の先で弾くように舐めるだけで洋恵の腰は、ビンと
跳ね上がる。
「あーっ、もっと、もっとして、全部舐めて、はうっ、ううっ、
イイッ、先せっ」
洋恵は宏一の頭に手を回すと、渾身の力を込めて腰に押しつけ、
腰を跳ね上げた。
「あーっ、はうーっ、あーっ、いいーっ」
洋恵はグイグイ宏一の顔を押しつけて激しく悶えながら快感の頂
上に向かって上っていった。しかし、宏一は全てを満足させない
ように、秘核だけを重点的に舐めていた。それでも今の洋恵には
十分すぎる快楽を与えている。
「はあっ、いいっ、せんせっ、いいっ、うう、そんな、はうっ、
あーっ、だめ、いいっ」
洋恵は激しく身体をくねらせ、腰から更に深く宏一の口を迎えに
行く。足は自然に最大限に開かれ、潤いを十分にたたえた秘唇全
体で宏一の口を受け入れようとする。
しかし、宏一は微妙に舌で舐め上げる位置を調整して、洋恵の好
きな秘核の回りだけを丹念に舐め続けた。
「先生、このまま、もっと、下も、あうっ、早く、このままいっ
ちゃう、先生、全部、アアッ、いいっ、もう、先生っ」
洋恵の声が次第にせっぱ詰まったものになってくる。宏一は慎重
にタイミングをはかりながら、洋恵がいく瞬間を待った。
「早く、先生、いっちゃう、もう、アアッ、あ、あーっ」
洋恵がいく瞬間に軽く秘核を吸い上げてやる。その瞬間、凄まじ
い快感が洋恵の身体の中を駆けめぐり、身体がブリッジを作って
硬直する。
「あーっ、んーっ、うっ、うっ、うっ、は、うっ、はぁーっ」
やがて洋恵の身体から全ての力が抜けて、ぐったりとしてしまっ
た。
「せ、先生、もっといっぱい、して欲しかったのに、いじわる」
洋恵は、乱れた息の下から宏一に言った。宏一は優しくベッドの
上の洋恵を抱きしめながら
「でも、気持ちよかったでしょ?」
と言うと、潤んだ瞳で
「うん、よかった」
そう言いながら、まだ十分満足してはいないことを示すように身
体を宏一にこすり付けてくる。
「だめ、このままじゃ、またしたくなるから。、明日は全部して
あげるからね」
宏一はそう言いながら体を起こし、洋恵にパンツをはかせ始めた。
突然、宏一の部屋の留守電が鳴り始めた。洋恵はぐったりして
いるが、宏一はびっくりした。このまま放っておけばメッセージ
が流れて留守電になる。
しかし、友絵がかけてきたのなら携帯をそのまま持っていてくれ
るように言わなければならない。友絵が調べれば宏一の家の番号
も分かるし、明日の船の出航時間も知っている。桟橋に来て洋恵
と顔を合わせて欲しくはなかった。
「もしもし?」
「宏一さん、いたのね。今、駅を降りたところ、もうすぐいくわ」
宏一はあわてた。
「え?明子さん?駅に着いたの?わかった。待っているよ。そう
だ、途中で何か食べ物を買ってきてもらえない?」
宏一は少しでも時間を稼ごうとした。あわてて時計を見ると4時
前だ。
「もう買ってあるわ。夕食を作ってあげる。デザート付きよ」
「分かった。じゃあ、待ってる」
明子は、宏一のアパートの前で携帯をしまうと、じっと宏一の部
屋を見上げた。
宏一は電話を切ると、時間がないことにあわてて洋恵の方を振り
向いた。
すると、洋恵は今まで見たこともない冷たい表情で宏一を見下
ろしていた。
「先生、女の人からね」
「うん、会社の同僚なんだ。ここにみんなで集まって、今夜は
パーティをするんだよ。だから、食べ物を買ってきてって頼んだ
んだ。でも、もう買ってあるって」
宏一はとっさに嘘をついた。
「この部屋に来るの?」
洋恵は宏一の部屋を見回しながらいぶかしげに聞いた。
「うん、ほんの四人なんだけどね。彼女が最初みたいだね。だか
ら、悪いけど後は明日にしようね」
「はい・・・、分かりました」
洋恵は突然邪魔が入ったので納得できないようだったが、宏一と
二人の所に誰かが入ってくるのはいやだったので、手早く身支度
をすると、火照った体を持て余すように玄関に出た。
「先生、ほんとにただの会社の人?」
洋恵は玄関で靴を履きながら宏一に訪ねた。
「そうだよ、洋恵ちゃんが一番好きだって、さっきも分かったばっ
かりじゃないの」
そう言って洋恵を優しく抱きしめてキスをする。洋恵は安心した
ように身体を預けると、嬉しそうに唇を絡めてきた。
明子は、そろそろいいだろうと思ってエレベーターのボタンを
押した。しばらくするとドアが開き、中から少女が一人出てきた。
入れ違いに中に入る。すれ違う瞬間、明子の脳裏に響くものがあっ
た。
『あの匂いだ』明子は驚いた。少女とすれ違う瞬間の匂いはまさ
に宏一の部屋の布団に残っていた匂いだ。エレベーターのボタン
を押す。少女はそのまま出ていくかと思ったが、ドアが閉まる瞬
間、こちらを振り向いたようだった。
「あの子なの?あれが宏一さんの相手?」
明子は訳が分からなくなった。どう見ても中学生か、せいぜい高
校一年だ。『あんな子に嫉妬していたの?』明子は考え込みなが
ら宏一の部屋のベルを押した。
宏一はすぐに出てきた。
「やぁ、早かったね。さ、入って」
宏一はいつもと変わらない優しさで明子を迎えた。明子は部屋の窓
が開けてあることに気が付いた。夏なので不自然ではない。部屋に
はあの子の匂いは残っていないようだったが、感じとしてなんとなく
不自然な気がした。
一階のロビーにいた洋恵は、エレベーターが宏一のいる階で止まる
のをじっと見ていた。『綺麗な人、スーツのにあう、大人の女の人
だわ。買い物袋も持っていたし、きっとあの人だ』自分の中に何か
訳の分からないいやな感じが沸き上がってくるのが分かった。帰り
道、今は宏一とあの人が一緒だと思うと、次第にたまらなくイラ
イラしてきた。『早く他の人も来ればいいんだわ』そう思うと、
いてもたってもいられなくなった。駅のホームで電車を待っている
間、我慢できなくなった洋恵は公衆電話に向かって歩き出した。
「今まで家庭教師をしている女の子が来ていたんだ」
宏一は、明子の様子がどこか落ち着かないので思い切って切り出
した。
「そうなの?家庭教師をしているなんて初めて知ったわ」
明子は自分の言葉にどうしても棘があるのを止められなかった。
「うん、いつもは水曜日と金曜日の夜に自宅に行ってするんだけど、
時々うちに来るんだよ。そう、どこかですれ違わなかった?」
「うーん、そう言えばエレベーターホールですれ違った女の子がいた
けど、よく見なかったわ」
「そう、中学三年なんだ」
「そうなの」
『あの子に違いない』
「もうすぐ高校生なんだけど甘えんぼでね。うちに来ると全然おと
なしくしていないんだよ」
宏一はさりげなく洋恵がただの教え子であることを強調した。
明子は、昨日の携帯電話のことを考えていた。あの電話に出た
のは絶対にあんな子供ではない。たぶん自分と同じくらいの年頃の
女性だ。とすれば、もう一人いるのか?そんなことを考えながら、
料理を続けていた。しかし、こんな疑心暗鬼のまま宏一の部屋にいる
自分に対しても、勝手に宏一を疑っているようでいい気持ちがしな
かった。
部屋の電話がまた鳴った。
「もしもし?」
宏一が出ると、今、帰ったばかりの洋恵だった。
「先生、みんな来た?」
「洋恵ちゃん、どうしたの?」
「先生、みんなもう集まった?パーティーの」
「まだみたいだね」
宏一は、洋恵が疑っているのが分かった。これ以上詮索されたら
危ない。
「洋恵ちゃん、うちに来る?よかったら夕食、いっしょに食べて
いかない?」
「ううん、いいの。それじゃ、明日」
「ああ、じゃあね」
宏一は電話を切ると、
「今話した家庭教師の女の子だったよ」
「どうしたの?」
「女の子の家から早く帰ってこいって電話があるんじゃないかって。
でもまだだって言ったんだ」
「ふーん」
明子はベッドに座っていた。何となくあの子の匂いがするような
気がした。そして、明子の感があの子も宏一のことを好きだと言っ
ていた。今の電話は明子を恋人かどうか疑っているのだ。しかし、
ベッドにあの子の臭いが残っていたからと言って、宏一と寝てい
たかどうかはわからない。体臭の強い年頃なので、汗をかいたま
まちょっとベッドに潜っていただけでも臭いは残るし、甘えたり
気分が悪くなったと言ってベッドに入ることも考えられる。宏一
が好きならなおさらだ。だんだん訳が分からなくなってばからし
くなってきた。明子は気持ちを切り替えると立ち上がり、キッ
チンに行くと手早く材料を並べて料理を始めた。
「ねぇ、何を作るの?」
宏一も話題を変えた。明子もこれ以上こんな話をしたくはなかった。
「私の特製、豚の冷製とスープよ。簡単でとっても美味しいの。
もうすぐできるわ」
「へえ、楽しみだ。お腹が鳴ってるよ。早く食べたいな」
「料理だけでいいの?」
明子はいたずらっぽく笑った。宏一は一瞬、何のことか分からな
かったが、すぐに
「もちろん、食後は一番大切なものを食べちゃうからね」
「食べちゃうの?」
明子は笑いながら料理を皿に分けている。こんな会話をしていると、
何となく以前の雰囲気に少し戻ったような気がした。
明子は手早く料理を済ませるとテーブルに並べた。
「さあ、できたわ、もうお腹ぺこぺこ」
「わあ、こんなのすぐ作っちゃうなんて凄いね」
宏一もそう言ってテーブルについた。しかし、まだ何となく気まず
い雰囲気がある。
「これ、美味しいね」
「そうでしょう?ほんの数分で作ったとは思えないでしょ?」
明子はニッコリと笑って食べている。
「うん、これだけ美味しい料理をすぐに作れるなんて、ほんとに
大したものだね」
宏一がもう一度ほめると、
「さあ、早く食べてしまって。今日はほんとに時間がないの。あん
まりゆっくりしていると大切な時間が・・」
明子が話している最中にまた電話が鳴った。全く今日は電話の多い
日だ。宏一は、洋恵がまだ疑っているのかと思いながら立ち上がっ
た。
この瞬間、明子は思いきって立ち上がると、
「とってあげる」
と言って受話器に手を伸ばした。こんな大切な時間を邪魔されたこと
に怒ってもいたし、ビクビクしながら勝手におびえるのも嫌になった。
あの中学生の声を堂々と聞いてみたかった。
受話器を取ると、あの可愛らしい声が聞こえてきた。
「もしもし?あの、三谷さんのお宅ですか?」
忘れもしない、宏一の携帯をとったあの声だ。一瞬、予期していな
かったので固まってしまった。そこを宏一がごく自然に受話器を
取る。
「もしもし、三谷です。はい、あ、新藤さん」
「ごめんなさい。携帯電話を返すのを忘れてしまって。あの、私、
持っているんです。旅行に出かける前にお返ししなくちゃと思って。
それで、会社で住所を調べて・・」
『もういい!』明子はそのまま席を立って帰ろうと思った。
「そのまま持っていてくれればいいのに。会社の引き出しにしまおう
かと思ったくらいなんだ。携帯が無くたってかまわないよ」
『え?何のこと?』宏一の自然な返事に明子ははっとした。受話器
からは、
「でも、それじゃ何かと不便だろうし、いざというときにこちらから
連絡も付かないし、もし良かったら私が届けようと思って・・」
友絵は一生懸命口実を作って宏一に会おうとしていた。しかし、宏一
はここの部屋に来られても、明日、桟橋にこられても困る。だが、
無理に断るのも変なような気がした。
「分かったよ。それじゃ、明日の午後、空いてる?」
「はい、いつでもいいです」
「じゃあ、四時にJR川崎駅の改札で会おうよ。北口に近い方に
いるよ」
「はい、分かりました。四時に川崎駅の北口ですね」
「そう、じゃあ、明日ね」
そう言って電話を切ると、明子がニコニコして宏一に抱きついて
きた。
「おいおい、どうしたの?急に」
「ううん、会社に携帯を置き忘れてきたのね?」
「ああ、それを総務の女の子が、いざというときに会社から連絡が
付かないのは困るし、旅行に行くのに携帯がないと不便だろうからっ
て、わざわざ渡しに来てくれるって言うから、そこまでしてくれ
なくてもいいって言ったんだけど、あまり無理に断るのも悪くて」
「分かった、もう何も言わないこのままベッドに連れてって」
トップ |