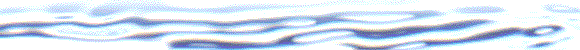肉棒をそそり立たせて宏一が洋恵の横に来ると、
「早く、先生、きて、ね、早く、入れて」
とせつなそうにねだる。宏一がゆっくりと挿入の体制に入ってい
くと、洋恵は宏一の首に手を回して、
「入ってきて、欲しいの、とっても欲しいの、奥までいっぱい入
れて」
と自分から腰の位置を合わせようとする。
肉棒をあてがうと、既に入り口は何度もしぼんだり広がったり
して早く中に受け入れようとしているのが分かる。洋恵は思いき
り足を広げて膝を引きつけ、宏一が入りやすい体勢を作る。
ゆっくり宏一が入っていくと、
「くぅーっ、いいーっ、もっとーっ、先生、もっと早くーっ、
アーッ、いーっ」
洋恵は全身を硬直させて宏一を受け入れた。しかし、宏一はゆっ
くりしか入っていかなかった。半分くらい入ったところで、
「どうだい?もっと欲しいの?」
といじわるをしてやると、
「もっと、もっと入れてぇー、奥まで欲しいの、奥が疼いて、早
くぅ」
と半分泣きながら腰を宏一に密着させようとする。
「ほうら、こうして欲しいんだろ?」
グッと奥まで進めると、
「イーッ、イーッ、イイーッ」
と顎を仰け反らせて激しく感じる。何度入っても、洋恵の中は素
晴らしいの一言だ。宏一は動きすぎないように注意しながら、何
度も深々と差し込んだり、入り口あたりで焦らしたり、あるいは
大胆に出没運動をしたり、宏一は先に終わらないように注意しな
がら洋恵をたっぷりと愛した。
宏一が我慢できなくなってくると、
「洋恵ちゃんのお口でもして頂戴」
と言って、肉棒を抜いてしまう。すると、荒い息を吐きながらも、
今まで自分の中で暴れていたものを口の中に深く飲み込み、けな
げに宏一が満足するまで愛してくれた。
宏一が再び
「さあ、横になって」
と言うと、両足を大胆に広げたまま宏一を待った。宏一は前から
したり、後ろからしたり、横になって入れたりして、洋恵に新し
い世界を教えていった。その間、洋恵は何度も軽い絶頂を迎えた。
宏一が口の奉仕で暴発を押さえている間、洋恵の秘口からは肉
壁が収縮するたびに液体が絞り出され、洋恵は焦れったくて仕方
がなかった。だから、宏一が再び入ってくると、一気に強い快感
が洋恵にあふれた。宏一は上手に洋恵だけをいかせることを覚え
始めていた。
途中、買ってきたサンドイッチや飲み物で休憩しながら、宏一
と洋恵は何度も絡み合った。洋恵は疲れてはいたが、一休みする
たびに宏一に身体を擦り付け、二人だけの世界に入っていった。
秘部はひりひりしてきたが、それでも宏一を受け入れる喜びは何
にもまして強かった。
お昼近くになって、同僚の中からポツポツと昼食の買い出しに
出かける姿がショーウィンドー越しに見えるようになった頃、、
史恵は内心イライラしながらショールームで接客中だった。本来
ならば、カウンターの割り当て時間が終わったので、書類整理を
してしまえば昼休みに入れたはずだった。営業所だから、営業部
の昼食はバラバラの時間にとる。決まった時間に休めるのはメカ
ニックくらいのものだ。
史恵は書類仕事が得意ではなかったが、今日、早く出るために
一週間も前からサービス残業を繰り返し、昨日までにほとんど片
づけてしまっていた。だから、今日は
12時前に出られるはずだった。しかし、
11時40分位になって史恵の得意客の不動産屋が尋ねてきた。
この不動産屋が最初に史恵の前に現れた頃、、史恵はまだ仕事
を始めたばかりで、そんな史恵に新車購入の話を持ってきてくれ
た客は確かに大助かりだと思った事もあった。しかし、あんな事
があった後で、さらに近頃では簡単な点検や修理の打ち合わせば
かりに長々と時間をかけるので、あまり会いたい客ではなかった。
その客が来たのだ。他にセールスの予定でもあれば別だが、む
げに断るわけにも行かない。不動産屋も史恵の顔を見て何かを感
じ取ったらしい、史恵を見ると
「おいの営業所の車ば3台ほど入れ替えたい思うとるが・・・」
と自信たっぷりに言い始めた。隣で接客している同僚が軽く微笑
んで『良かったね』と伝えてくる。しかし、史恵は目の前が一瞬
暗くなった。『あの思いをまた・・・』と悪夢がよみがえった。
一年半ほど前に史恵が働き始めた頃、最初はセールスのアシス
タントで、どちらかと言えばニコニコしているだけである程度は
ごまかせた。しかし、場数を踏んでくるに従って自分でも売らな
くてはいけなくなる。当時も就職はあまり良くはなく、
「セールスをやると言うのであれば」
と言う条件でつてをたどって採用してもらっただけに、やらない
わけには行かなかった。
最初の内は、先輩から客を紹介してもらうこともできたし、就
職したばかりの友人にも何台か買ってもらえたが、しばらくして
ネタがつきる頃から全く売ることができなくなった。ショールー
ムでの営業も上手くいかず、せっかく紹介してもらった客にも断
られた。元来、責任感とプライドの強い性格が裏目に出た。そう
なると笑顔も作れなくなり、
「もっとリラックスして話しかけないと」
と注意されてもきつい目つきで客に接していた。
そんな時、大学時代の部屋を世話してもらったことのある不動
産屋が現れた。営業のつらさを知っている人間には、史恵の表情
を一目見るだけであらかたの状況は飲み込めた。そして、新人の
史恵には驚くような、一気に四台の新車購入を持ちかけたのだ。
大衆車とは言え、四台も売れれば会社は史恵の今月の給料を
払ってもまだ十分お釣りがくる。更に、条件次第では他メーカー
の車を順次入れ替えても良いという。危ないとは分かっていても、
その話を他の男性セールスに回すだけの余裕はなく、のめり込ん
でいった。
その頃、史恵には短大時代からの恋人がおり、比較的安定した
つきあいを保っていた。まだ結婚までは考えていなかったが、
わがままな自分を受け入れてくれる彼とのつきあいは大切にした
かった。
しかし、不動産屋の商売時間が終わってから説明に足を運べば、
夜のプライベートな時間も作りにくくなってくる。セールスであ
る以上、土日でも時にはショールームに出なければいけない。特
に、景気が落ち込んでからと言うもの、何かに付けては発表会や
感謝デーで客を呼ぶ時代である。以前ほど彼と過ごす時間も作れ
なくなってきた。
そして、それが原因で彼と些細なことで激しく喧嘩して落ち込
んでいた翌週に、四台の車の購入契約書に判子を突くからと言っ
てホテルに呼び出された。やっとの思いでここまでこぎ着けた史
恵は、それでも男性セールスに代わって行ってもらおうと何度も
考えた。しかし、それをすればそんな風にセールスしていたのか
と言われてしまう。そうなれば叱責だけで済むかどうかも怪し
かった。
実際は、新人が当初売れない時期を過ごすのは当然のことであ
り、それを乗り越えて少しずつ接客というものを学んでこそ本当
のセールスレディーになれるのだ。新人をねらって身体を求める
横暴な客も時々はいるので、上司に一言相談すればベテランを代
わりに行かせるなり、最悪の場合は注文を断ってでも史恵を守っ
てくれたはずだった。
会社にとっても色がらみのスキャンダルは絶対に避けたいとこ
ろなので、史恵が一言誰かに相談すれば意外に簡単に片が付いた
はずだった。しかし、最初の一回以外は全て相手の方に出向いて
のセールスだったので誰も気が付かなかった。いつも別れ際に次
の予定を決めていたので営業所に電話がかかってくることもな
かった。
自動車の営業には比較的高額の金銭が絡むのでスキャンダルが
起きやすい。若いセールスレディーが扱うには金額が大きすぎる
と、外での営業を禁止しているところもあるほどだ。この営業所
でも、当初はそうだったが、この不況でそうも言っていられなく
なり、あたりの柔らかいセールスレディーは家族客に評判がいい
こともあって事実上は自由になっていた。
最初、史恵は上手く言いくるめてサインと判子を先にしてもら
い、ベッドに入る前に不動産屋がシャワーを浴びている時をねらっ
て出てくるつもりだった。しかし、史恵が唇を許してまで頼んで
も、
「シャワーはまずあんたが先じゃけん、その間にサインはしとい
ちゃる。判子はあんたがベッドに入ったら出しちゃるけん、後で
勝手に押せばよか」
と言って譲らなかった。
史恵は屈した。普段の史恵なら、本当の実力に裏付けられてい
ないセールスの結果など一時しのぎであることは十分に分かって
いるはずだった。しかし、今は何より一息つきたかった。会社で
一息つき、彼との時間を作って一息つきたかった。
シャワーを浴びてベッドに入ると、不動産屋は約束通り判子を
出してテーブルの上に置いた。そして、史恵のバスタオルを外す
とゆっくりと楽しみ始めた。史恵は、最初は何も感じなかった。
くすぐったくさえもなかった。ただじっとして、ボーっと男が身
体の上を這い回るのを感じていた。
しかし、自分の中心に指が入っていき、敏感な部分を触り始め
た瞬間、
「イヤーッ、イヤッ、イヤーッ」
と大声で騒ぎ出し、渾身の力で不動産屋の身体をベッドから突き
落とすとバスタオルを身体に巻き、判子を手にして不動産屋に向
かって言った。
「服を着て下さい。その間に判子を押します。それが嫌なら警察
に行きます」
あまりに冷たく言い放ったので、不動産屋もこれ以上深追いは
しない方がよいと思ったらしく、おとなしく服を着始めた。史恵
はバスタオル姿のまま、あわてて判子を突くとやっと服を着始め
た。それからは、
「ここの支払いはしておいて下さい」
そして営業所に帰ってから慌てて支度をしてから
「今日はこれで失礼します」
だけがその日史恵の口から出た言葉だった。
部屋に帰ると真っ先にシャワーを浴びた。ずっとシャワーを浴
びていたが、身体はいくら洗っても綺麗になっていないような不
快感が残った。目を真っ赤にしてすすり泣く声がシャワーの水音
に混じって響いていた。
その夜、いつもの時間に電話がかかってきた。彼からに間違い
なかったが、留守電さえも切っておいたので、ただむなしく部
屋に響くだけだった。そして、とうとう電話のコードさえも抜い
てしまった。その夜は一晩中泣き明かした。
自分の敏感な部分に触られた瞬間、何かを感じてしまった。し
かし、それは快感ではなくぞっとするような恐ろしい感覚だっ
た。全身がとてつもなく気持ち悪くなった。あれは快感だったの
か、悪寒だったのかは分からなかった。しかし、それが何より悲
しかった。自分の身体が本人の意思とは関係なく、何かを感じて
しまったことが悲しくて仕方がなかった。不動産屋に屈してしま
った身体が憎かった。そして、自分を責め続けた。
翌日は、会社に出る気にもならなかった。しかし、契約書だけ
は置いてこなければならない。何度も破り捨てようとしたが、ギ
リギリで思いとどまった。ここで破り捨てれば、あとで不動産屋
がきっとまた何か言ってくるに違いなかったからだ。疲れた身体
で営業所に行き、課長に簡単に報告して
「風邪を引いたらしいので休ませて下さい」
と言うと、課長は
「ああ、無理せずに休みなさい。二日くらい休んでもいいから」
とあっさり言った。
課長は真っ青で真っ赤な目をした史恵の表情と、四台もの契約
書から何かを感じ取っていたようだったが、何も言わなかった。
史恵にも、二日休めと言うのは意外に聞こえたが、今は何よりも
疲れていて、何もする気が起きなかったから、そのまま部屋に
帰った。
二日間は、誰にも会わず、電話にも出ず、外にも出なかった。
ただ、自分のしたことの悲しさに泣いていた。まるで自分で自分
を壊してしまったようだった。ほとんど食事らしい食事もしな
かったが、特に腹も減らなかった。
三日目になって、やっと気分が落ち着いてきたので朝食を取る
と、遅刻ではあったが出社した。少しやつれていたが、周りは何
も言わなかった。ただ、先輩のセールスレディーが、
「あなたがセールスした不動産屋さんから電話があったわよ」
とだけ伝えてくれた。
面白いことに、それ以後は次第に史恵のセールスが上向いてき
た。最初はほとんど投げやりでやっていたのだが、脈のある客は
それでも史恵の注意を引こうと自分が更に真剣であることを伝え
ようとした。史恵は、初めて一歩引いてみると言うことができる
ようになった。今までのように、ただ押しまくるだけでは誰もが
嫌がることに気が付いた。
少しずつセールスは順調になったが、彼とは結局別れてしまっ
た。何度も真剣に心配してくれたのはありがたかったが、それよ
りも一人になりたかった。
「私の最後のわがままだと思って」
と言ったのが別れの言葉になった。
それからしばらくして、史恵のセールスがセールスレディーの
月間でトップになったことがあった。職場の仲間が口々におめで
とうを言ってくれた。何をやっても楽しく、ツキが重なって出来
上がった結果だった。その週のある日のミーティングで課長が、
セールスレディー、特に若手の営業には注意が必要である、時に
は購入金額の多さに理不尽な要求をしてくるお客様もいらっしゃ
るが、無理だと思ったら断ってかまわない、自分を傷つけてまで
営業してもらおうとは思わない、後の影響の大きさを十分に考え
るように、と言うようなことを言った。
史恵は思わず口に手を当てた。課長はお見通しだったのだ。た
ぶん、事を表に出すと史恵に更に辛い思いをさせることになると
思って何も言わなかったのだろう、史恵が立ち直るのをじっと見
ていたのだ、と思った。営業の本当のつらさとは何か、少し分
かったような気がした。
今の史恵には新しい彼ができた。友人からの紹介で、事務機器
のセールスマンだった。仕事が同じセールスなので話が合い、休
日が合わなくても文句一つ言わなかった。それがとても暖かく感
じ、時々は泊まりに行っていた。しかし、最近はまた問題が起き
ていた。
今、史恵は、目の前で人が良さそうな笑いを見せている不動産
屋を前にして、どうしようか迷っていた。あれからも半年に一台
くらいのペースで新車を買ってくれていたが、この相手に限って
はセールスをショールームでしかしないことにしていたので、あ
れ以後は特に問題は起きていなかった。何を餌に誘われても絶対
に出かけていかなかった。
その不動産屋が今、目の前にいた。
「ちょうど昼じゃけん、食事でもせんとね。打ち合わせもある
けん」
と臆面もなく言ってくる不動産屋に
「こちらで話をするのではいけませんか」
と聞き返したが、
「ウチの社員の希望ば聞かんとならんし」
と引き下がらない。史恵はだんだん頭にきた。
「では、代わりのものを伺わせますので」
と標準語で慇懃に答えると、
「おはんじゃなかとか」と諦めきれないようだ。
とうとう史恵は我慢できなくなった。
「申し訳ありません。どうしても私が伺わないとだめだとおっしゃ
るのでしたら、この話はなかったことにしていただいて結構です」
と強い調子で言った。その声がショールームに響いたので、不動
産屋は慌てた。こんなとこでは誰に聞かれるか分からない。変な
噂でも立ったら不動産屋自信の商売に差し支える。
「またこんどごあんど」
と言うと、すごすごと帰っていった。やっと帰ったと思って時計
を見ると、既に
12時を過ぎている。早く出かけなければいけない。そこをセールスアシスタントチーフに呼び止められた。
「溝口君、ちょっと」
「はい」
「さっきの言い方は良くない。例え理不尽だと思っても、もう一
歩我慢できないのかな。相手はなかなかいないお得意さまだ」
「分かってはいますが、あの人だけは我慢できません。申し訳あ
りません」
「他のお客様に聞こえるような声で言うべき事じゃないだろう」
セールスアシスタントチーフはねちねちと史恵を叱責した。確
かにそれはそうだが、ああでもしないと引き下がらなかったろう。
史恵がだんだんと怒りを抑えきれなくなってくると、
「溝口君、これからもあのような対応をとられると、営業として
も迷惑がかかる。担当を外れてもらうがいいかね」
と向こう側で聞いていた課長が言ってきた。
「はい。申し訳ありません」
「よし、以後の担当は春岡君にする。休暇が終わったら早急に引
き継ぐように」
それだけ言うと席を立って食事に行った。
史恵は
「わかりました。今日はそろそろ失礼します」
と言うと、そそくさとロッカー室に入って着替えながら、内心は
喜んでいた。これでもう辛い思いをしなくて済む。引き継ぐ相手
は史恵の先輩のやり手のセールスレディーだ。今の史恵には、少
しくらいのセールスの実績などどうでも良かった。確かにこのと
ころ成績は良くないが、宏一に会えばリフレッシュできるだろう。
そう思うと、狭い駐車場を小走りに駆けて、愛車のエンジンを
かけた。今からだと4時近くになってしまいそうだった。『宏一
さんは待っててくれるかな?』分かり切った質問だったが、楽し
い質問だった。ここからインターチェンジまではほんの数分だ。
「先生、少し痛いの。何かひりひりするみたい」
宏一の上から被さるように四つん這いになり、乳房を宏一に含ま
せながら洋恵は言った。
「そうか、急に何度もしたからだね」
「ああん、もうすぐ先生とさよならなのに、もう少しだけしたい
のに・・・」
「お口でしてあげようか?」
「でも・・・、先生が欲しいの。・・・中に・・」
洋恵は何度もゆっくりと胸を動かし、宏一に乳首を含ませようと
する。しかし、宏一は微妙なところで洋恵を焦らし続ける。
「早くぅ、もう、先生、いじわるしないで。こんな風にされるか
ら、我慢できなくなってくるのにぃ。もう一回だけ。して」
冷静に焦らし続ける宏一の愛撫に、洋恵の身体が幼い欲望の虜に
なっていく。
「じゃあ、このまま洋恵ちゃんが上になって自分で入れてごら
ん」
「そんな、私から入れるなんて、いや、私、まだ中学生よ」
「その中学生がそんなおねだりしてるんじゃないの?」
宏一は軽く舌の先で乳首を転がす。
「あうッ、そんなことされたら・・、先生、アアン、先生がこん
な身体にしたくせにぃ」
「上手にできたらギュってオッパイもしてあげるよ」
舌の先で微妙に乳首を弾くと、
「うっ、いや、そんなの」
と胸をさらに宏一に押しつけてくる。
しかし、宏一が思ったように快感を与えてくれないのでとうと
う、
「もうっ、知らないっ」
洋恵は身体を下にずらせて自分から宏一の肉棒を迎えに行った。
しかし、宏一はまだ臨戦状態になっていない。しばらく宏一の股
間に擦り付けていた洋恵は、それに気づくといったん宏一の上を
降りて口と手で肉棒を愛し始めた。
トップ |