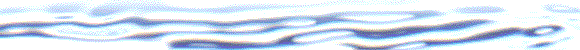「どこから回ろうか。史恵ちゃんが言ってた高千穂峡にする?」
「そうねぇ、そうしましょうか」
史恵はあれほど見たがっていたのに、いざとなったら余りその気
がないようだ。それでも、少しでも史恵の機嫌が直ればと思って
高千穂峡に行くことにする。宏一が改めて地図を見ると、どうや
ら少し離れた駐車場に車を置かなければいけないらしい。
地図を見ながら狭い道路をくねくねと走り、『本当にこんな所
で良いのか』と思うようなところを走り抜けると駐車場に着いた。
しかし、観光地という感じではとてもなく、周りには何もない。
どうやらここから歩いて行くようだ。史恵と二人で歩き始めたが、
かなりの距離を歩いたのにまだ着かない。しかし、時々戻ってく
る人とすれ違うところを見ると間違ってはいないようだ。ようや
くそれらしい場所に着いたのは、歩き始めてから
20分くらいも経ってからだった。
「やっと着いたみたい。あんなに離れたところに駐車場を造らな
くたっていいのに」
と史恵はブツブツ言っている。
やっと着いたところは、写真で見た景色とそっくりな、とても
綺麗なところだった。史恵の言ったとおり、カップルがボートで
絶景を楽しんでおり、男性が漕いで女性が写真を撮っている。
「ボート乗り場はどこかなぁ、史恵ちゃん、ボートに乗ろうか」
宏一は史恵の気を引いてみたが、史恵は何も言わずにじっと眺め
ている。
「史恵ちゃん」
宏一が肩に手をかけるとビクッと震え、
「待って、今、話したくないの」
とじっと見つめながら考え込んでいる。宏一は、せっかくの景色
が色あせてしまったような気がして、少し哀しくなった。それで
も宏一は、
「のどが渇かない?」
「少しだけお土産屋を見てみようか」
と話しかけ、史恵の気持ちが沈みすぎないように気を配った。史
恵は素っ気ない返事をしてはいるが、あまり嫌そうではないとこ
ろを見るとそれほど怒っているようでもない。
思ったより駐車場から先が長かったので、車に戻ってきたとき
には5時半頃になっていた。
「結構時間かかったね。早足で高千穂神社に行ってみる?」
と聞いたが、史恵は
「いいえ、部屋に戻りましょう。夕食の時間が近いから」
と小さな声で答えただけで、気のせいか目が赤いような気がした。
宿までの車中では、
「宏一さん、少し泣いてもいいですか?すぐに元に戻るから心配
しないでね」
そう言うと、下を向いた。やがて
「くっ、ううっ」
小さな声ですすり泣く声が聞こえてきた。しかし、宏一には何も
することができなかった。
宿には
10分ほどで着いた。部屋に入ると少しは気分が落ち着いたようで、宏一にお茶を入れてくれたし、少しは話をするよう
になった。6時になって食事のために離れに行ったときは、まだ
赤い目をしていたが時々は可愛らしい笑顔も見せてくれた。食事
は、あまり豪華では無かったが心のこもった田舎料理という感じ
で、山菜のおいしさをたっぷりと味わうことができた。何でも各
地の行楽地では輸入山菜を使うところが多い中で、ちゃんと地元
産のものを使っているとかで、宏一には聞いてもわからない山菜
ばかりだった。少し控えめな優しい味は、史恵の心に染み込んだ
ようで、小さな笑顔を宏一に向けながら、
「美味しい。この宿にして良かった」
としみじみと言った。酒はこの辺りの地酒を竹の筒に入れていろ
りで暖めたカッポ酒が宏一は気に入った。使い回しているのだろ
うが、確かに少し竹のいい香りがした。史恵は一杯、宏一は2杯
飲み、少しずつ二人の時間が楽しいものになっていった。しかし、
宏一は史恵の方ばかり見ていたのであまり食が進まず、結局半分
近くは手つかずだった。かえって史恵の方が、残しはしたものの
宏一よりたくさん食べたくらいだった。
時折短い会話を挟みながら二人の食事は進んだ。だから、時間
ばかりが過ぎていき、宏一のもどかしい気持ちを更に募らせた。
やがて7時を少し回ると、史恵が、
「宏一さん、そろそろ送って下さい」
と決意したように言った。
「やっぱり行くの?せっかく楽しくなってきたのに」
「さ、そろそろ出ないと」
史恵は立ち上がった。一度部屋に寄って、史恵のハンドバッグを
取って部屋を出ようとするとき、史恵は、
「宏一さん、バスターミナルではできないと思うから」
と言って宏一の頸に手を回してきた。そのまましばらく二人の唇
がお互いを求め合った。史恵はなかなか離そうとしない宏一の手
をそっと離すと、
「行きましょう」
と一言だけ言った。車から史恵の荷物を降ろして歩き始めると、
小さな街なのでバスターミナルまではすぐだった。バスが来るま
での間、史恵は宏一の手を握っていたが、何も話さなかった。バ
スが来て、史恵が乗り込むとき、宏一が荷物を渡すと、史恵は素
早く宏一の唇にチュッとキスをすると、
「宏一さん、ごめんなさい。でも帰ります。日程はそのままにし
ておいて下さいね」
とそれだけ言うとバスに乗り込んだ。窓から小さく手を振る史恵
を乗せた遠ざかっていくバスを見ながら、宏一は史恵が言ったこ
との意味は何なのだろうと考え込んでいた。『途中から合流する
と言うことだろうか?それとも鹿児島の部屋には来ないで欲しい
と言うことだろうか?』いろいろ考えたが、分かるはずもなかっ
た。そんな宏一を残してやがてバスは走り去っていった。
そのまま部屋に帰るのはしゃくだったし、一人でじっとしてい
るのも辛いので、宏一は近くの食堂に入って改めて飲み直すこと
にした。ぶらりと歩いていると、一見の田舎風レストランという
感じの店が見つかったので飲み直すつもりで入ってみる。あまり
大きな店ではなかったので学生のグループの隣に座ることになっ
たが、楽しく騒いでいる邪魔をしないように静かに注文を告げる。
こちらの名物の竹寿司を食べてみると素朴ないい味だった。
やっと気分が少し落ち着いたので、周りを見る余裕ができた。
宏一の隣に座っている学生は
10人ほどのグループで、8人のテーブルでは収まらずに宏一のテーブルも使っているようだった。
宏一の近くには女性が二人と男性が一人座り、女性の一人はほと
んど話をせずにぽつんと言う感じで座っている。時々チラッと宏
一の方を見ているようだ。しかし、その女性以外のメンバーの座
はかなり盛り上がっているようで、女性も含めて全員で酎ハイを
お互いに飲ませて喜んでいる。
「ほら、有紀も飲まなきゃ、あんたのための飲み会なんだから。
ほら、もっと酎ハイ、飲みなさいよ」
宏一の近くの席の女性が向かいの女性に勧めている。
「私はもういい。ビールで十分」
「何いってるの、ビールなんてもう無いわよ。ほら、酎ハイ飲ん
で盛り上がって騒ぎましょう」
有紀と呼ばれた女性はそれでもテーブルの上を探し、ビール瓶を
見つけると、
「私はこっちで良いの」
と手を伸ばす。しかし、酎ハイを勧めていた女性は、
「え?ビールなんて・・・それは駄目よ!こちらの方の・・」
と言う。有紀はあわてて手を引っ込め、
「すみませんでした」
と謝るのを手で止めて、宏一は、
「良いですよ。もしよかったら飲んで下さい。どうせ余るビール
だから」
と言うと、今までよほど気分がめいっていたのだろう、
「ありがとうございます。頂いても良いんですか?」
と宏一の勧めるビールにコップを差し出してきた。そして仲間の
方を向くと、
「ごめんなさいね。そういうわけで私はビールで十分です」
とあからさまに言う。この一言で座が少し白けてしまい、隣のテ
ーブルでは男性同士がぶつぶつと関係のないことを言って話を逸
らしてしまった。
宏一はビールだけ注いで、さっさと自分一人で食べ始めるつもり
だったが、こうなると放っておくのも無責任なような気がして、
少し連中の話が戻ってきたところで、相変わらず一人で黙々と食
べている有紀に、
「ごめんなさいね。余計なこと、したかな?」
と小さな声で言った。
「いいんです。あ、私が注ぎます」
そう言いながら、体を宏一の方に向けてきた。
「なんか、変な出会い方だけど、三谷です。よろしく」
「いいえ、こちらこそ。福山です」
「有紀さんて言うんだっけ。そう呼んでもいい?」
「ええ、みんなそう呼んでますから」
有紀の仲間が突然始まった二人の会話に興味を集中しているのが
わかる。
「すみません、邪魔するつもりじゃなかったんだけど。三谷宏一
です。よろしくお願いします。グループ旅行ですか。楽しくて良
いですね」
そうグループのメンバーに挨拶すると、女性の一人が、
「おひとりで旅行ですか?」
と聞いてきた。
「本当は一人じゃなかったんだけど、連れが突然帰っちゃって・
・・。だから今は一人です。これからも一人かな?」
しかし、宏一の話にはそれほど興味があるわけでもないらしく、
その女性は適当に返事をすると再びグループの仲間と話し始めた。
どうやらグループの仲間に入れてもらえないらしい。仕方なく宏
一は再び自分の寿司をゆっくりと食べ始めた。しかし、有紀だけ
は時々、
「三谷さんはもう高千穂峡に行きました?」
とか、
「高千穂神社は素敵でしたよ」
と話しかけてくる。有紀はグループのほかのメンバーと話をして
いても突然それを無視して宏一に話しかけるので、次第に誰も有
紀に話しかけなくなってきた。
宏一はふと時計を見た。まだ8時だ。宿に帰って一人で過ごす
にはまだかなり早い時間なので、もう少しこの店で粘ることにす
る。そこで、思い切って高千穂牛の鉄板焼きを頼み、日本酒も注
文した。鉄板焼きが届く頃には有紀は宏一の前に座り、宏一と差
し向かいという感じで話をしていた。
「もしよかったら箸で突っついて下さい。一度食べてみたかった
んだ。九州の牛肉を」
「三谷さんはどこから来たんですか?」
「東京だよ。世田谷」
「へぇ、やっぱり東京からも来るんだ」
「有紀さんはどこから?」
「私たちは名古屋から。私たちほど遠くから来る人なんていない
かと思ったんですけど、やっぱり東京からも来るんですね」
「そりゃ住んでる人が多いもの。どこにだって行く人はいるさ」
「どうやってきたんですか?飛行機ですか?」
「川崎からフェリーで来たんだ」
「船の旅なんて素敵ですね」
「天気も良かったから良い旅だったよ」
「お連れの方はどうして帰っちゃったんですか?」
「え?ええとね。どう言おうかな・・・」
「あ、いいです。ここじゃ、ね。私の方も言い難いし。その話は
後にしましょう」
そう言うと有紀は鉄板焼きに箸を延ばし、美味しい美味しいと言っ
て喜んで食べ始めた。しばらくすると、有紀のグループでは銘々
が財布を出してお金を数え始めた。
「有紀、出るわよ」
とさっきまで宏一の隣に座っていた女性が声をかける。気が付く
と椅子を回して向こうのテーブルに座っていた。
「いい、私もう少しここにいる。先に行ってて」
有紀は全然動こうとしない。
「何言ってるの。これからみんなで高千穂神社に行って夜神楽を
見てから散歩しようって話してたの。有紀だって散歩したいって
言ってたじゃない」
「いいの、先に行ってて。後から追いつくかもしれないから」
「夜道を一人で歩く気なの?早く行きましょうよ」
「ごめん。一人で考え事したいの。わかって」
「いいよ。それなら先に行こう。待ってたって仕方ないし」
一人の男性がそう言って話が付いたようで、ぞろぞろとグループ
は店を出ていった。
「三谷さん、もう一杯もらっていいですか?」
有紀はコップを宏一に差し出すと少し怒ったような顔でそう言っ
た。
「ああ、いいけど・・・」
宏一はビールの追加を頼むと、
「俺のせいではぐれちゃったのなら御免なさいだね」
と言った。
「いいんです。三谷さんのせいじゃないことくらいわかると思い
ますけど。私があの人たちと一緒にいたくなかっただけなんです」
そう言って有紀は追加のビールをぐいっと飲んだ。
「喧嘩でもしたの?あ、言いたくなければいいんだよ」
「あの中に私の彼がいたんですけど、さっき出るときに私に話し
かけてきた女がいたでしょ。あの子と二股かけられてたんです」
「へえ?あの子がねぇ。それじゃ怒るのも無理無いね」
「本当はホテルの部屋は彼と一緒だったんですけど、ここに来る
前にそれに気が付いて怒って彼を追い出しちゃったんです」
「さっきわかったの?それじゃ冷静になれって言う方が無理か。
でも、ほかの人たちは知ってたの?そのこと」
「知ってたみたい。誰もびっくりしなかったから」
「そんなことって。そのもう一人の女性も知ってたの?」
「あの女?もちろん。あっちが後からなんだから!」
有紀は相当頭に来ていたらしく、一気に宏一にしゃべった。どう
やら、有紀が怒っているのでにぎやかに飲んで騒いでごまかそう
としていたらしい。その有紀をなだめる役が先ほどの女性だった
ようだ。しかし、お互いに話しにくく、暗くなっていたところに
宏一が現れたと言うことのようだ。
「さ、私のことは全部話しました。今度は三谷さんの番。どうし
てここにいるのか話して下さい」
有紀はビールを差し出しながら宏一に言った。宏一は、最初、男
友達と二人で来て、友人に急用ができて帰ったと言うことにしよ
うと思っていたが、有紀が正直に話しているようなので、宏一も
ちゃんと話すことにした。
「その子とはどれくらい会ってなかったの?」
「4年近くかな」
「へえ、そんなに会って無かったのに、よく二人で旅行する気に
なったわねぇ。それって結構すごいことじゃない?」
「そうかな?でも、こんな事になるんなら同じことだよね」
「わかんないけど、予定はそのままにしてって言ったのならあん
まり深刻に考えなくてもいいんじゃない?」
「でも、彼女は間違いなく鹿児島に帰ったし、残りの日程中にも
う一回会えるかどうかわからないんだよ」
「それはそうだけど・・・、でも、私みたいに突然破局って言う
訳じゃないみたいだけど」
「そうかなぁ・・」
二人はお互いに恋人から離れてしまったもの同士で結構真剣に話
が盛り上がった。
そのころ、東京の宏一のワンルームマンションでは、制服姿の
一枝が机に座り、その服の裾から差し入れられた手がふっくらと
した膨らみを愛撫していた。ゆっくりとした繊細な動きは、長い
時間をかけて一枝の体に少し反応を引き出していた。
「あ、あん、ねぇ、もう、いいでしょ、これくらいにして・・」
しかし、膨らみを撫でる手は執拗にゆっくりと動き続ける。
「は、んん、ねぇ、感じたから。もう感じたから許して・・・」
その声を聞くと膨らみを這い回っていた手の一つがスッと離れて
いったので、一枝は一瞬安心したが、その手はスカートの中に入
っていった。
「だめ、それはだめ、そこはイヤ」
一枝が嫌がったが、その手は迷うことなく秘丘の奥を目指し、薄
い布地の上からゆっくりと揉むように愛撫を始めた。
「だめ、許して、ああん、ゆん、許して、今そこをされたら・・
・、ああ、ああん、こんなのイヤぁ」
一枝の甘い声が部屋に響く。
その日の夕方、一枝は由美に呼び出された。その時、由美は宏
一に頼まれたことがあると言って一枝を部屋に誘った。一枝はそ
う言われると何も言えず、何かがおかしいと思いながらも言われ
るままに部屋に入った。
由美はそのまますぐに汗を流すと言ってシャワーを浴び、その後
で一枝にもシャワーを使わせた。そして、
「宏一さんから、ちゃんと感じられるようにしておいてって言わ
れたの」
と言うと、一枝を椅子に座らせ、ゆっくりと一枝の身体を可憐な
指で愛撫し始めた。最初はなかなか上手くできずに時間ばかりか
かってしまい、一枝が我慢できずに椅子を立ったこともあったが、
二人で少し学校のことや友達のことを話して気分を変えてからは
少しずつ一枝も感じるようになってきた。
そして今、やっと次の段階に進んだのだ。
木曜日の夕方、一枝の目の前で宏一に愛されて以来、由美はずっ
と我慢してきたが、だんだん一枝が宏一に抱かれるのが我慢でき
なくなってきた。自分は宏一に会いたくて仕方ないのに、来週の
日曜に最初に宏一に会うのは一枝なのだ。
自分の人の良さに呆れてしまったが、今更宏一に言えるはずもな
い。もし言えば宏一は一枝のことは忘れてくれるだろうとは思っ
たが、一枝をがっかりさせたくなかったし、宏一にもそんな自分
を知られたくなかった。あれこれ考えた挙げ句、一枝の身体を宏
一と同じように由美自身が扱うことで、一枝にも準備ができるし
自分も一枝を思い通りにしたという満足感が得られると思ったの
だ。できれば、一枝に由美が今まで何度も言わされたようなおね
だりの言葉を言わせてみたかった。そうすることで、由美が一枝
の弱みを握れるような気がしていた。
由美の細い指がそっと一枝のパンツの下の部分を撫で始めると、
一枝の反応は明らかに強くなった。
「ン、ゆん、ダメ、もういいでしょ、ああ、ここまでにして。お
願い。これ以上はイヤ」
「一枝ちゃん、本当に止めていいの?もっとして欲しいんじゃな
いの?」
「イヤ、許して、お願い、ンンッ、そんなにしたら・・」
「そんなにしたら、どうなの?」
「イヤ、イヤ、ゆん、お願いだから、止めて」
どうしても由美が思っているようには進んでいかない。本当に嫌
がっているような気がするのだ。
「ね、ゆん、あん、これ以上はしないで。怖いの。やめて。お願
い」
一枝は快感に翻弄されながらも必死に由美に頼んでいた。そこで
由美にはやっと一枝が由美のようにおねだりをしないわけが解っ
た。一枝はこれから先、どの様に自分の身体が反応するか知らな
いのだ。快感を得られるかどうか、感じるかどうかすら解らない
のだから、いくら焦らしてもおねだりなどするはずはなかった。
一枝は不安で仕方ないのだ。
「一枝ちゃん、もっと感じさせて上げる。心配しなくていいの。
私に任せて」
由美はどうしていいか解らなかったが、とりあえず一枝にベッド
に入るように言った。
「ゆん、本当に宏一さんがこうしなさいって言ったの?本当?」
ベッドに横たわり、由美に制服のジッパーを降ろされながら一枝
は怯えたような目で由美に訪ねた。
「そうよ。最初に感じるまで時間がかかったらすぐに夕方になっ
ちゃうわよ。なるべくなら宏一さんに感じさせて欲しいでしょ。
だから宏一さんがそう言ったの。一枝ちゃんの身体を感じやすい
ようにして上げてって」
由美は諭すようにゆっくりと一枝に話した。一枝としては、宏一
と過ごせれば感じようと感じまいとどちらでも良かったが、そう
宏一が考えてくれているのなら、それはそれで嬉しいことだった
から由美にもう少し身体をまかせることにした。由美は一枝の制
服のジッパーを下げると、ブラジャーの上からゆっくりと愛撫を
再開した。
「ほら、一枝ちゃんのここ、膨らんできてる。感じてきた証拠よ」
「イヤ、そんなこと言わないで、ゆん、恥ずかしいから」
「ほら、足だってこんなに擦れ合って。こっちも感じてきたのね」
「イヤ、そんなこと言わないで、ね、ここまでにしよう」
一枝が明らかに嫌がっているのに気が付いた由美は、あわてて胸
を揉んだ。
「くっ、あん」
一枝の身体が反応する。そこで、由美は一枝のスカートの中に手
を入れると秘核の辺りをゆっくりと愛撫し始めた。
「ああっ、ゆん、それをされると・・・あん」
一枝の身体から力が抜け、由美の与える愛撫に身体をまかせてき
たことがよく分かった。由美は一枝の体に快感を発生させること
に意識を集中した。宏一が良くやるように左手でブラのカップを
揉みながら自分の口でもう一つのカップを愛撫し、右手で秘核の
周りをゆっくりと撫でる。
「ああっ、ゆん、こんなこと、こんな事しちゃダメ、どうしてこ
んな事知ってるの?アアン、ねぇ、どうしてぇ?」
一枝の身体は次第に快感のレベルを上げていき、未知の領域に入っ
ていく。
由美は一枝の服を脱がせることにした。
「ちょっと身体を楽にして、今脱がせて上げるから」
そう言うと、ゆっくりと制服を脱がせていった。いつもは脱がさ
れるばかりで、脱がすことなどないので、服を脱がせるのは結構
大変だと言うことに気が付いた。
一枝はかなり恥ずかしかったが、服を脱がされるよりは感じて
いる姿を見られる方が恥ずかしかったので、あまりイヤではなかっ
た。しかし、由美がブラジャーを脱がすときはさすがに手で胸を
隠した。先週見た由美の姿はまだしっかりと目に焼き付いていた。
自分のプロポーションはそんなに悪いとは思わなかったが、由美
の身体は一枝が見ても段違いに綺麗だった。
「ゆん、恥ずかしいよ。ゆんに見られるなんて」
一枝は小さな声で囁いた。
「目を閉じて、今私が確かめて上げる。一枝ちゃんがどれくらい
感じるのか」
「そっとしてね。ゆん、お願いだから」
「大丈夫。私に任せて」
由美はゆっくりと一枝の手を広げると、乳房の周りに指を這わせ
た。頭の中では宏一が自分にどれくらいの強さで、どれくらいの
早さでしていたか、一生懸命思い出しながら。パンツ一枚の一枝
が由美の愛撫を受け入れていた。甘い声と共に一枝の身体がゆっ
くりとうねるように動き始める。
トップ |