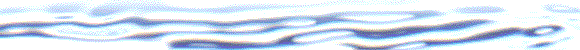宏一は更に由美を攻めることにした。由美の下の方に移り、目の
前で愛撫をする度に縄をなうように絡め合っている由美の足をグ
イッと大きく開くと、ショーツ一枚隔てただけの茂みの上の辺り
にゆっくりと顔を押しつけ、唇でついばむように愛撫を加え始め
る。
ほんの少しだが布地越しにシャリシャリとした感覚が伝わってく
る。その感覚を楽しみながら、ゆっくりと下に下りていく。
既に最初にすりすりされた時から、由美の秘芯は強烈な感覚を生
み出していた。由美はぐっと歯を食いしばって耐えようとしたが
、宏一の顔が下に降りる気配を見せると、とても我慢できそうに
ないと直感した。しかし、絶対におねだりをするのはイヤだった。
「ぐっ、ううぅっ、はあぁっ、くっ、く、うぅ」
声とも息とも言えない音が由美の口からでてくる。由美の秘芯は
既に濡れそぼっているようで、布地の中心にはかなり大きなシミ
ができている。
そこを宏一に残酷に愛撫されると、由美は大きく仰け反って快感
に飲み込まれそうになっている自分を必死に支えた。しかし、も
ういくらも保ちそうにない。
「ああっ、そ、そこは、ああっ、だめ、だめよ、ああん、はうっ」
宏一の唇がシミのある辺りを軽く這い回ると由美の腰はぴくんと
跳ね上がってしまう。何度もそこを唇が通り、軽く布地を刺激す
るだけで予感を通り越して強烈な快感が身体を走り抜け、何度も
腰が跳ね上がるのをどうしようもなかった。
くぐもって辛そうな由美の声とは対照的にゆさゆさと腰が上下運
動を始め、宏一の唇が布地を通して与える感覚をむさぼり始めた。
しかし、それだけでは身体を焦がすような焦れったさばかりがた
まってしまう。
そこまで身体が暴走を始めても、由美はまだぎゅっとシーツを握
りしめ、宏一の頭を擦りつけたい衝動を何とか抑えようとしてい
たが、もうほとんど何も考えられなくなってきた。そしてついに
由美は、
「ああっ、いやぁ、ああっ、だめっ、いやあ、くうっ、はうぅ、
ハアハアはあ、ああっ、いやっ、絶対いやあーっ」
と大声を出し、はっきりと拒絶した。その声の強さに宏一は呆然
として愛撫を中止すると、由美はくるりと後ろを向いて泣き始め
た。その肩をそっと抱く。
「どうしたの?由美ちゃん、なんで嫌がるの?」
「宏一さん、女の人と付き合ってるでしょ?私に何も言わないで」
その言葉に宏一は驚いた。由美は何を知ったのか?宏一の何を見
たのか?誰か他の人が由美に教えるとは考えにくいから、きっと
宏一が誰かと一緒にいるのを見たのかも知れない、そう予想する。
「由美ちゃん、どうしてそう言うの?教えて」
「土曜日に・・・・」
「土曜日?九州から帰ってきた日だね?土曜日にどうしたの?」
「私、見たの、宏一さんが・・・・川崎駅で・・・・」
宏一は『しまった』と思ったが、同時に安心もした。その程度の
ことなら何とでも言える。第一、宏一自身も別に予定していたこ
とではないのだ。
小さな背中をふるわせて泣いている由美の肩に手を掛け、こっち
を向かせる。由美は一度は嫌がったが、宏一が更に抱き寄せると、
されるがままに宏一の腕の中に入ってきた。
「言いかい、聞いて」
宏一は由美の背中を優しく撫でながらゆっくりと話し始めた。
「あそこで会ったのは新藤さんて言って、会社の人なんだ。実は、
旅行の途中に会社から緊急の電話があって、旅館で食事中にあわ
ててパソコンを使ってしばらく仕事をしたんだよ。それで、会社
の部長がお礼に粗品を出してくれたんだけど、それを丁度ついで
があったって言って届けてくれたんだ」
「どうして会社の部長が粗品を出すんの?宏一さんは仕事をした
だけでしょ?」
「だって、休暇中に突然電話がかかってきて仕事をさせられたん
だよ。あの時は新藤さんも何度も休暇中に電話してごめんなさい
って謝ってたんだ。だからじゃないかな?駅まで来てくれたのは」
由美は何かおかしいとは思ったが、それがなんなのかは分からな
かった。どうして良いか分からずにそのままじっと宏一の腕の中
で考え込んでいる。
宏一はここで由美が信じてくれないと、せっかく由美と過ごす時
間が味気ないものになってしまうので、どうしても信じて貰う必
要があった。
しかし、由美が何となく納得していないのは分かっていても、ど
うすればいいのか、はっきりと分からなかった。由美はあの時の
様子を思い出していた。確かに宏一は驚いていた。だからきっと
宏一が言うように、相手の方が宏一を勝手に待っていたのは間違
いないだろう。
しかし、一緒に中に入る時の様子、コーヒーショップで宏一を見
ていた女の人の嬉しそうな表情は絶対に普通の関係とは思えなかっ
た。はにかむような感じ、ぱっと明るく笑った時の笑顔、ほんの
数秒のことだったが由美の頭の中にははっきりと映像が残ってい
た。
だが、相手が勝手に熱を上げていると言うこともあり得る。宏一
は由美が疑った状態でいるのはなんとしても避けたかった。この
ままではどこで何がばれるか分からない。なんとしても納得して
貰う必要があった。
でもこれ以上は何を言っても同じことだろうと思う。特に何の証
拠もないので、結局は由美が宏一の言うことを信じるか信じない
かだけなのだ。
宏一は勝負に出た。再び優しく由美の背中を愛撫しながら首筋に
唇を這わせる。抱きしめられた状態なので由美には拒めない。
「由美ちゃん、信じてくれないの?こんなに由美ちゃんのこと、
好きなんだよ」
「あ、ああ、宏一さん、だめ、今はだめ・・・・待って・・・・
あん、ああっ、感じてくる・・・・」
「由美ちゃん、好きだよ」
由美は宏一の言葉を信じようかと思った。そうすればいつものよ
うにとろけるような炎の中に身体を投げ込むことができる。それ
は強烈な誘惑だった。
「由美ちゃん、誤解なんだ。分かって、ね?」
由美の心は揺れた。感じたくて仕方のない敏感な身体は、優しい
愛撫だけでなく宏一の言葉さえ気持ちよく感じさせる。
「はうぅ、そんな・・・・だめ、そんな事したら・・・・ああっ、
いや、今はだめですっ!」
何とかあの光景を思い出し、由美は力を入れて宏一の腕から逃げ出
した。その由美を見て、宏一は諦めた様子でベッドを下りると、そ
のまま立ち上がって服を着始める。これからが本当の勝負だ。その
宏一の仕草がとても冷めたものだったので、由美は戸惑った。
「あの・・・・・」
「由美ちゃん、信じてくれないんだ」
それだけ言うと宏一は服装を整え、下着姿の由美を残して部屋を
出ていこうとする。
「宏一さん・・・・あの・・・」
「由美ちゃんは信じてくれないんだね。でも、別に何の証拠も見
せられないし、これ以上、何を言っても由美ちゃんの気持ちを変
えることなんてできないよ。全部言いたいことは言ったよ。でも
信じてくれない。悲しいよ」
それだけ言うと、宏一はさっさと荷物をまとめて部屋を出ていっ
た。部屋に残された由美は唖然とした。今の今まで宏一に求めら
れても許さない、とだけ考えていた。
しかし、今の宏一の態度は由美の想像を超えていた。このままで
は宏一を失ってしまうかも知れない、そんな予感が一気に由美の
心に沸き上がる。
あんなに大好きな宏一が去っていくかも知れない。嫉妬で宏一を
拒絶したが、本当は今でも大好きなのだ。このままでは他の女の
人の所に行ってしまうかも知れない。そこまで考えて、由美は戦
慄した。
この部屋に来てくれなくなることはないだろうか?そうなったら
父の不正がばれるのを助けてくれるという、二人にとって一番大
切な約束はどうなるのか? 由美は自分が宏一を引きつけておか
なければいけないと言う二人の関係の本質を思い出し、大慌てで
服を着て荷物をまとめると部屋を走り出して宏一を追った。
エレベーターの中で服装を何とか直し、ドアが開くと同時に全力
で走る。しかし、外の道には宏一の姿は見あたらなかった。訳も
分からず由美は更に走り出す。しかし、駅まで走っても宏一は見
つからなかった。全力で走ったので激しく息をしていたが、その
つらさよりも宏一がいなくなるかも知れないと言う恐怖の方が由
美を包んでいた。
トップ |