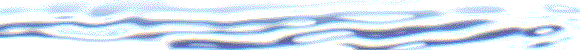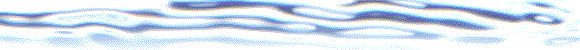
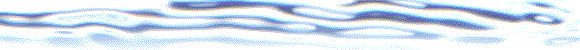
途中の乗り換えが順調だったので、宏一は待ち合わせ時間の10分近く前に着くことができた。まだ友絵は着ていないと思っていたが、改札の近くまで来るとポツンと立っている友絵が見えた。しかし、その表情は暗く、とても男性と待ち合わせしている女性には見えなかった。あまりに暗い感じだったので、宏一の足が鈍ったほどだ。どうやって声をかけようか迷いながら近づいて行くと友絵のほうが見つけたらしく、にっこりと微笑んでくれた。それは、あまりに直前と表情と違ったのでちょっと面食らっていると、「ちょっと先に来ちゃいました」
と朗らかに笑っている。
「ごめん、待った?」
「いいえ、ほんの今来たところですよ、宏一さん」
「そうか、それじゃ、夕ご飯にいこうか?」
「ねぇ、何を食べさせてくれます?」
「どうしようかなぁ、食べたいものはある?」
「そうですねぇ、食べたいものって言うよりは雰囲気かな?」
「雰囲気?店の?どんな?」
「えーと、ちょっと華やかな感じがいいな。でも、高級でなくたって良いんです。ただ、いつもと少し違う雰囲気がいいなって思っただけだから」
「そう、雰囲気的には和食よりもイタリアンとかフレンチかな?」
「う〜ん、フレンチも素敵だけど、この前食べたし・・・」
「わかった。イタリアンだね。ちょっと待っててね」
宏一は何軒か予約が囲うか電話をかけていたようだが、やがて、
「それじゃ、行こうか」
と改札には入らずにJRで新橋まで行ってから銀座線へと移動し、外苑前で降りてすぐのレストランに友絵を案内した。
「うわぁ、なんか、イタリアンって感じですねえ。なんか東京じゃないみたい」
ウェイティングバーの席に着いた友絵は雰囲気に驚いている。
「ちょっと待ってほしいって言ってるから、ここでまず何か飲もうか」
そういうと宏一は自分にはビール、友絵にはホワイトワインのスピリッツァーを注文した。程なくそれが運ばれてくると、
「ここは人気の店だから当日予約は無理かなぁっておもったんだけど、運良く空きがあったみたい。混んでいる店って、評判ばっかりでおいしくない店が多いんだけど、ここは別だよ。特別な味じゃないけどね」
宏一がこの店を選んだのには理由があった。今日突然電話を掛けてきたことや昼間の様子、そして改札で見かけたときの様子からして、きっと何か辛いことがあったに違いなかった。だから、同じイタリアンでも銀座の店のように静かな雰囲気の所を選んでしまうと、食事の会話が湿っぽくなりそうだと思ったので、せめて食事くらいは楽しく、明るく楽しみたかった。その後でバーに誘うつもりだったので、もし友絵が何か打ち明けたいことがあれば、そこで話してもらえばいい、このまま無理をして明るく振舞っている友絵の心の扉を開けたら、友絵の心が壊れてしまいそうだ、と心配したのだ。
「この店に入ってくるとき、なんか雰囲気がもう違ってましたよね。イタリアンで魚介類の水槽がある店なんて初めて見ました」
と友絵はホワイトワインスピリッツァーを珍しそうに飲みながら興味津々という感じで話しかけてくる。
「そうだね、イタリアでも南の方にあるローマのお店だから、新鮮な魚介類も売り物なんだよ」
「ところで宏一さん、これ、何なんですか?」
「飲みやすいだろ?」
「はい、とっても。なんか難しい名前で覚えられなかったけど」
「ははは、白ワインに炭酸を混ぜたものだよ」
「え?それだけ?」
「それだけ」
「なんか、もっと凄いものかと思ったのに」
「カクテルって、すごいものじゃないよ」
「そうなんだ・・・・、またひとつ勉強になりました」
「別に勉強に来てるわけじゃないから・・・」
ちょっと宏一が口を尖らすと、
「でも食事に関しては宏一さんのほうが絶対すごいもの。いつも私を驚かせてくれるから」
「そんな、驚かせようなんて思ってないよ。ただ・・・」
「大丈夫、わかってます。本当に今日は、こういうお店に食事に来たかったんだなぁ。静かなお店だったら泣いちゃってたかも?フフフ」
友絵はさらりと言うと、
「今日は楽しみ。あ、宏一さん、今日はゆっくり付き合ってくださいね」
友絵はちょっといたずらっぽく言うと、スピリッツァーをぐいっと飲んだ。
「あ、そんなに一度に・・・。口当たりはいいけど、白ワインが半分入ってるんだから気をつけないと」
「大丈夫、私には宏一さんが付いているんだから」
と友絵が笑った。
「どういう意味なんだい、それ」
「え?そういう意味ですよ」
そう言ってにっこり笑う。その笑顔は本当に素敵だった。どうやら友絵はこのレストランが気に入ったらしい。さらに少し話をしていると、ウェイターが二人を呼びにきた。バーの勘定はテーブルに回してもらうように言い、席を移す。
友絵は店内の装飾にさらに興味を掻き立てられたようで、キョロキョロと見回している。サラ(英語のサロン)と呼ばれるメインダイニングはイタリアンレストランの特徴であるオレンジ色の電球で照らされており、少し暗いのに落ち着いた明るい雰囲気を演出している。席はすでに三分の二ほど埋まっていた。
「メニューのオーダーはどうしようか?」
「あのぉ、お任せしてもいいですか?」
「いいよ。多かったら残してね」
「はい、でも残しません。多分、きっと・・・絶対・・」
「無理しちゃだめだよ。夜はまだまだ長いんだから。いっぱい食べすぎると動けなくなるよ」
宏一がウィンクすると、友絵の顔がぱっと赤くなった。
「あの・・・でも、きっと・・美味しいから・・・・」
「ごめん、ちょっといじめちゃったかな?大丈夫なようにオーダーするから安心して」
「宏一さんたら。もう、お願いしますよ」
「はいはい、えーと・・・」
そうは言ってもイタリアンはフレンチよりもパスタがある分だけ余計に注文しないと全体を楽しめない。そこで宏一は友絵に鱸のカルパッチォ(刺身)と夏野菜のタリアッテレ(パスタ)そして太刀魚の炭火焼、自分にはプロシット(生ハム)とオマールのグリル、そして子羊のローストを注文した。海の幸が盛り込まれたサラダは二人で一つだ。ワインはキリッとした口当たりのタスカンの白をカラファ(ハーフピッチャー)で、赤ワインは手頃なキャンティをフルボトルで頼んだ。
「なんか、ワクワクしてきました」
「オーダーしたのはどれも古典的な料理ばっかりで、ここはそういうのが美味しい店なんだけど、最近は味が少し落ちたって言う話もあるし、今日はどうかな?」
「大丈夫ですよ。きっと美味しいですよ」
「きっと、タリアッテレは手打ちだから美味しいと思うんだ」
「へぇ、手打ちパスタなんて初めてかも?」
そうこうしている内にアンティパスト(前菜)が届き始め、友絵は鱸にオリーブオイルの香りが合うと大喜びだったし、宏一のプロシットが大きな塊から目の前で薄くスライスされるパフォーマンスにも大喜びだった。白ワインはあっさり目の辛口にしておいたので話が弾んでいるうちにいつの間にか無くなってしまい、気が付いたときには赤ワインのティスティングを勧められていた。話が弾んでいたのでそれはスキップしてすぐに注いでもらい、二人は話を楽しんだ。そのキャンティもフランスの赤のようにどっしりとしていないので友絵でも楽しむことができた。
「・・・その時はオレンジケーキが食べたくてスペイン村に行ったみたいなものなのに、なかなか売っている所がわからなくて。一箇所しかないんですよ。探しているうちにパレードが始まっちゃって、楽しみにしていたのに・・・」
「どうしてスペイン村ではオレンジケーキが有名なの?」
「よくわからないけど、バレンシアオレンジを使ってあるらしくて、とっても評判良いし、確かに美味しいの」
「それでたくさん買ったんだ」
「頼まれた分はその日のうちに宅急便で送りました」
「オレンジケーキくらいなら、いまどきインターネットで買えるんじゃないの?」
「それが、いろいろインターネットで買えるのに、そのケーキは売っていないんです。そこに行かないと買えないようになってるの」
「そうか、そうやってお客を呼んでいるわけか。それで、パレードは見れたの?」
「見れましたよ」
「何だ、心配するほどじゃなかったんだ」
「ディズニーランドみたいに混んでないから」
そんな話をしているうちに、カンタンテ(歌手)が登場した。もともと話し声で賑やかになっていたところに登場したので、一気に場が盛り上がる。
「うわぁ、素敵。楽しいですね」
と友絵も拍手したり手拍子を取ったりと夢中になっている。登場したときに少し歌ったカンタンテは、次に各テーブルを回りながらリクエストを取り始めた。やがて宏一たちのテーブルに回ってくると、リクエストはないか聞いてきた。
友絵を見ると、断るという雰囲気よりも何か頼みたそうだ。宏一はイタリアの歌など知らなかったが、それでも何とか思い出してフニクニ・フニクラを頼むと、カンタンテは大喜びで歌い始めた。山登りの歌なので調子がとりやすく、聞く分には楽しみやすい。この曲は回り中の客も楽しそうに聞いていた。
カンタンテが登場するときに、ちょうど二人のメインディッシュが出てきたのだが、あまりに歌に熱中していたので殆ど味を覚えていなかった。ただ二人とも、『冷めないうちに食べないと』とパクパクと食べたので、美味しいとは思ったがワインとじっくり楽しむ、という雰囲気ではなかった。友絵は宏一がいつの間にか食べ終わっている自分の皿に気が付いて『あれ?』という顔をしたのを見逃さなかった。そして、
「なんか、あっという間に食べちゃったみたい。私のも気が付いたら無かったもの」
とワインを注いでくれた。
「そうか、どうする?デザートでも頼む?ここのはちゃんとした美味しいデザートだよ」
「ううん、もう十分。それよりもお話がしたいな」
「わかった。それじゃぁ、コーヒーを飲んだら店を出ようね」
「はい」
最初友絵は、この店に入るまで宏一に話ができるかどうか不安だった。無理に明るく振舞うだけで全神経を消耗してしまう感じで、とても自分のことを話す勇気が出そうになかった。それでも友絵の心は自分のことを宏一に聞いてほしかった。たぶん、嫌われるかな、とは思っていたが、それはそれで良いと思っていた。。そして宏一はその危険を冒しても自分を受け止められるか試す価値のある男性だった。もし自分を受け止めてくれる人がいるとすれば、今は宏一しかいないのだから
でも楽しい食事を十分に楽しんだ今は、かなり軽い感じで話ができそうだった。もちろん、話を始めれば言葉に詰まることもあるだろうが、今はそれほど話を始めることが気にならなかった。
カンタンテが去った後のコーヒーは、楽しいけれど少しだけ落ち着いた感じで和やかなものだった。
「どうだった?この店」
「もちろん、最高です」
「料理は?」
「美味しかったですよ。それも、とっても!」
「タリアッテレは?」
「こんなこというと怒られるかもしれないけど、うどんみたいですね。ううん、美味しかったんです。とっても。ただ、歯ごたえとかがうどんに近いかなって」
「まぁ、イタリア風手打ちうどんて言う感じなんだろうね。ソースが野菜系のあっさりしたものだったからそう感じたのかな?もともとはイタリアの庶民派のリストランテだしね」
「でも、本当にどれも美味しかったです」
「ワインもあっという間に無くなっちゃったしね」
「そう!この前横浜で食事したときは、結構ワインはたくさんあった気がしたんだけど、今日はすぐに無くなっちゃった」
「同じだけ頼んだのに、本当にあっという間だったね」
「私、イタリアンにはまりそう、かも?ふふっ」
「良かった、それじゃぁ次を楽しみにして、店を出ますか」
「はい」
宏一はカードで支払いを済ませると、タクシーを拾って竹芝まで行くように言った。
トップ |