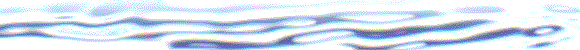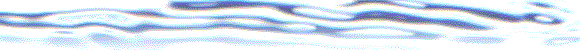
[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
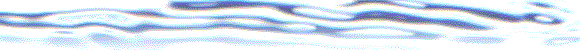
「宏一さん、白ワインで牛肉って合いますか?」「もちろん」
「でも、お肉には赤ワインですよね?」
「そんな決まりがある訳じゃないよ。好きなワインを飲めばいいのさ」
「そうですか・・・・」
由美は今ひとつ納得していないようだった。そこで宏一はちゃんと説明しておいた方が良いと思った。
「由美ちゃん、説明させてね。俺が今、白ワインを飲んでいるのは好きなカリフォルニアの白ワインがあったからで、この辛口の白ワインはホワイトジンファンデルって言うブドウから作っていて少しくらい濃い味の牛肉にも負けない味わいと、それだけでもすっきりと飲める軽やかさがあるからなんだ」
「お肉にも魚にも合う白ワインがあるんですか?」
「好みの問題もあるけど、俺は両方に合うホワイトジンファンデルのワインが大好きだよ。でも、このブドウは作るのが難しくて毎年一定量ずつ作るのはとても難しいから商売にするには向かないんだ。だから値段は意外に安いんだよ。だから、見つけた時には必ず飲むね」
「へぇ、それじゃ、宏一さんはラッキーだったんですね」
「そうさ。今年は初めてだからね」
「宏一さん、私も少しだけ飲んでも良いですか?」
「だいじょうぶ?」
「・・・・・たぶん・・・・・でも、やっぱり止めておきます」
由美はトワイライトエクスプレスの時の失敗を思い出した。
「まぁ、ウィスキーやブランデーじゃないから、少しだけなら大丈夫かな」
「でも・・・・・」
「飲んでみたいんでしょ?」
由美はコックリと頷いた。
「良いよ。香りを味わってごらん」
そう言うと宏一はグラスを由美に私、由美は恐る恐るワインを少しだけ口に含んだ。
「どう?」
「良く分からないけど、酸っぱいだけじゃなくて、何て言うかライムみたいな香りがします。ブドウみたいな香りも」
「やっぱり由美ちゃんはお酒を楽しむ素質があるね。美味しい?」
「はい」
そう言うと、由美はもう一口だけ飲んでから宏一にグラスを返した。
「大人になったら一緒に飲もうね」
「はい」
由美はその時、宏一とこのままいつまでも一緒に居たいと思った。そして、自分の成人式に宏一が再びこのホテルのこのレストランでお祝いをしてくれる姿を夢見た。
「宏一さん、一つ聞いても良いですか?」
「ん?なに?」
「このホテルはどうやって見つけたんですか?」
「実は知り合いに頼んだんだ。良いホテルを見つけて欲しいって」
「そうなんだ。お友達に詳しい人がいるんですか」
「そうだよ。一人で旅行会社をやってるくらいだから」
「凄い人とお友達なんですね」
「そうだね。彼は凄いよ。一人で世界中の飛行機やホテルを簡単に見つけちゃうんだから」
「そうなんですか」
由美はその旅行会社の人が男性だと知って安心したらしく、話題を変えた。
「それじゃ、ワインはどうやって詳しくなったんですか?」
「ワインはアメリカに行った時によく飲んだし、日本に帰ってきてからも飲んでるからね」
「アメリカにも行ってたんですか?」
「うん、学生時代に少し住んでたし、仕事でも行ったりしてたから」
「それで英語も上手なんですね」
「俺の英語は生活英語だから受験には向かないと思うけどね」
「違うんですか?」
「日本では結構英語を変に教えてるんだ。ウソじゃないけど、何て言うか、英語って言うのは言葉なんだから使って見るのが一番だけど、どっちかって言うと学問て言うか、英語学を教えてるみたいで。例えば先に使い方や用法や動詞の変化ばっかり教えてるだろ?」
「はい・・・って言うか、私、そう言う方法でしか習ってないから・・・・・・」
「本当はそれが大切らしいんだけど、やっぱり使ってこその英語だと思うからね」
「でも、使ってこそって言っても、日本の中じゃ・・・・・」
「そうだけどね。まずはしゃべることが大切だから、高校生になったら英語の時間は日本語を使わないとか、そんなのが大切だと思うよ。そうやって身振り手振りでも何でも使ってコミュニケーションしていくとだんだん使い方が上手くなっていくモンなんだ。言葉ってそんなもんだよ」
「そうかも知れませんね。今度私に教えて下さい。宏一さんのやり方で」
「それじゃ、今から英語しか使っちゃいけないよ」
「え?今から?良いですよ。やってみます」
「Yumi, how do you feel for this dinner. Are you enjoying this?」
「うーん・・・・ハイ・・・I'm enjoying this dinner very much」
「Great! You make enough communication in this evening」
「Evening? ちょっと待って下さい。今は無しですよ。宏一さん、もう夜なんだからnightじゃないんですか?イブニングなんですか?」
「それじゃ由美ちゃん、イブニングっていつまで?何時まで?」
「それは・・・・・・6時くらいかしら?」
「学校では習わなかった?」
「イブニングは夕方って・・・・」
「それが日本の教え方なんだよ。本当は夕方だったり少し暗い夜だったりするんだけど、日本語訳を覚えさせたら名詞の勉強はそれでお終いなんだ。本当はイブニングって言う単語をどうやって使うかまで教えないといけないんだけどね」
由美はなんか、宏一の演説に付き合わされているような気がして少し面白くなかった。
だから、
「それじゃ、何時までなんですか?」
と少し挑戦的な響きを含めて宏一に問い正した。
「決まってないよ」
宏一は静かに答えた。
「ずるい。それじゃ、覚えようが無いじゃないですか」
「由美ちゃん、夕食までがイブニングで、夕食が終わるとナイトになるんだ。だから時間は決まってないんだよ」
「え?そうだったんですか。初めて知りました」
「もう怒ってない?」
「え?怒ってなんかいませんよ」
「良かった。ごめんね。もう英語の時間はお終い。由美ちゃんに嫌われたくないから」
「ああん、もうお終いなんていやぁ」
「その言葉はベッドに入ってから聞きたいな」
「宏一さん!」
「ははは、ごめんね」
二人の会話はくつろいだものであり、誰も近づけないほどの親密さを含んでいた。二人は会話を楽しみ、食事も楽しんだ。由美は鴨肉を興味深く噛みしめながら宏一の話を聞いたし、宏一はロース肉を焼き上げた香ばしい香りを鮮烈なワインの香りが洗い流していく不思議を何度も楽しんだ。
由美は宏一との時間を楽しみながらも、二人だけの時間が物凄い勢いで流れていくような気がして少しだけ寂しかった。この宝石のように輝いていて大切な時間をつなぎ止めておく方法があれば由美はどんなことでもしただろう。今、宏一は由美の目の前で由美だけを見つめている。それは由美がずっとずっと待ち望んでいた二人だけの時間なのだ。
デザートが運ばれるくらいの時間になると、由美はだんだん落ち着きを無くしてきた。
「ん?由美ちゃん、どうしたの?」
宏一は由美が急いでデザートを食べ始めたので少し驚いた。
「何でもありません」
「でも、なんか急いでいるみたいだね」
「宏一さん、覚えてますか?なるべく早く戻ろうって言ったのを」
「うん、覚えてるけど、部屋に行きたくなったの?」
「もう食事はたっぷり楽しんだから」
「お腹はいっぱいになった?」
「はい」
「でも、ちゃんと全部食べていこうね。途中で席を立つのは失礼だから」
「ハイ、ちゃんと全部食べます。だけど、こうやって早く食べちゃったら次が早く来るかと思って」
「それはそうだろうね。よし」
宏一はウェイターを呼ぶと、残りを全て出してくれるように言った。
「宏一さん、それは失礼じゃないんですか?」
「全然。だって、残したりする訳じゃなくて、全部を一緒に楽しみたいって事なんだから。どっちかって言うと好みの問題さ」
「ふうん」
「なんだい、そのふぅんて言うのは」
「いいえ、なんか宏一さんに都合の良い解釈の仕方だなぁって思って」
「そうかもね。でも、元々お客さんて言うのは千差万別で我が儘なものだよ」
「やっぱり宏一さんは大人だなぁ」
「由美ちゃんだって大人でしょ?」
「いや・・・・、そんなこと・・・・・」
宏一は何気なく言ったのだが、由美はそう取らなかったらしい。しかし、敢えてそこは指摘せずに流すことにした。
「ねぇ由美ちゃん、もういっぱいだけお酒を飲んで良い?」
ふと見ると宏一のボトルが空になっている。
「それともお酒臭いのは嫌?」
「ううん、良いです。でも、後で私の我が儘も聞いて下さいね」
「うん、なんだから分からないけど良いよ」
そう言うと宏一はカルバドスのロックを頼んだ。
「これはリンゴから作ったブランデーで、とっても香りが良いんだ」
「わぁ、素敵。ちょっとだけ香りをかがせて下さい」
「良いけど、強いお酒だから飲んじゃダメだよ」
「はい」
そうは言ったが、あまりに香りが甘くて素晴らしいので由美はほんの少しだけ舐めてみた。
「ああっ、ダメだって」
「ゲホッゲホッ、うっぐっ、はっ」
由美はたちまち舌をいるようなアルコールに咽せてしまった。
「だからダメだって言ったのに」
「苦くて美味しくないです。でも、香りは素敵です」
「由美ちゃんにはまだ無理だよ」
「私だってお酒を飲めるようになりたいのに」
「ダメだよ。お酒は二十歳になってから」
「嫌です。今飲めるようになりたーい」
「もう酔ってきたのかな?」
「酔ってなんかなーい」
そう言いながら二人はデザートを楽しみ、最後のコーヒーまで辿り着いた。
トップ |