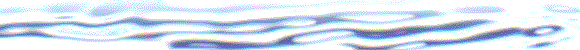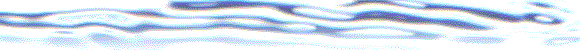
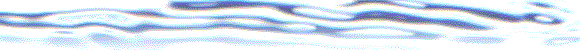
由美の今感じている快感こそが由美の支えだった。一枝が何を言ってもこの快感には勝てない。由美は喜びの中、肉壁で宏一の肉棒を締め上げ、たっぷりとした潤いの中で肉棒から白濁した液体を搾り取ろうとしていた。宏一は由美の絶頂が近づいていることに気が付いていた。しかし、宏一自身、もう余り持たなくなっている。自分が動かずに由美の動きだけで放出してしまいそうだった。
「ゆん、いきたいの?」
一枝はあまりに激しい由美の反応に少し戸惑いながらも念を押した。
「そおっ、いっちゃん、もうダメになる。わたし、もうがまんできない。ああぁぁっ、ううぅっくうぅぅっ、そんなにされたらダメになるぅッ」
「ゆん、いっていいわよ」
「いいの?いっちゃん、いいの?」
「いいわよ。はやくいっちゃいなさい」
他人の絶頂になど長く付き合っていても仕方がない、そう思った一枝は由美に終わるように言った。
「ああぁぁぁぁっ、ああぁぁっ、ああっ、ああっ、もう、ああぁぁぁぁぁぁぁーーーーっ」
由美は一際透き通るような高い声を上げると、後は急に何も言わなくなり、携帯からは激しい息づかいばかり聞こえてくるだけだった。
「ゆん、いった?」
「うん、いっちゃん、ありがとう。わたし、うれしかった・・・・・」
「ゆん、凄いんだね。ちょっとびっくりしたよ」
「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、私だって、はぁ、はぁ、こんなになるなんて思わなかった」
「よく言うわ」
「いっちゃん、明日。がんばってね。宏一さんなら優しくしてくれるから」
「うん」
「まだ怖い?」
「え?」
「怖かったから電話してきたんでしょ?」
「え・・・、まぁ・・・・・」
「大丈夫。さっきの私みたいに、きっと上手にいけるよ」
「そうかな?」
「だいじょうぶ。いっちゃんなら」
「ありがと。それじゃ、切るね」
「バイバイ」
由美はそう言うと携帯を切り、尻を高く上げたまま再びベッドに沈んでいった。宏一は放出寸前までいった肉棒を抜きながら、
「一枝ちゃんと話しながらなんて凄いことするね」
と言ったが、何となく由美の気持ちも分かる気がした。
「宏一さん、私、宏一さんを感じてたからいっちゃんとちゃんと話ができました。だって、こうでもしていないと意地悪しそうで」
「そんなに嫌なら一枝ちゃんのロストなんて手助けしなきゃ良いのに」
「ううん、いっちゃんのためになりたいの。変でしょ?私もそう思います。でも、宏一さんのことも一枝ちゃんのことも大切だから」
「でもね由美ちゃん、俺のことも考えて欲しいな。これ、どうしてくれるの?」
宏一はいきり立ったままの肉棒を由美に見せながらブンブン振った。
「ごめんなさい。少しだけ、ちょっとだけ休ませて下さい。もうすぐですから。まだ身体が重くて、力が入らないの・・・・」
「由美ちゃん、本当にいったんだね」
「はい、凄かったです」
「それじゃ、今度は俺が拗ねる番だな。由美ちゃんが一枝ちゃんとのことに夢中になって、俺のことを考えてくれないから」
「宏一さん、そんなこと・・・・」
「少し休んで身体が楽になったらこっちへおいで」
「はい。もう少しですから」
由美はそう言うとベッドに初めて身体をたっぷりと投げ出し、楽な姿勢をとった。その可愛らしい尻の間からは少しだけ秘芯が見えており、明らかにテラテラと光っているのが分かった。
宏一はベッドから降りると冷蔵庫からチューハイを一本取り出し、渇いた喉に流し込んだ。先程は殆ど動いていなかったが、それでも由美の尻を抱えながら由美が動きたいように支えているだけでも結構疲れた。それに、あと一分由美が持ちこたえていたら、きっと宏一の方が先に放出していただろうと思った。ただ、由美が動いて宏一がじっとしたまま快感を得るという新しい形が新鮮な気がした。
やがて、由美がガウンを纏って宏一の所に来た。
「宏一さん、さっきはごめんなさい」
そう言うと由美は宏一の前に跪き、宏一が開いた足の間に顔を埋めて肉棒を口の中で扱き始めた。
「由美ちゃん、さっきいったばかりなのに、また欲しくなったの?」
宏一がそう言うと、由美は口で扱いていた肉棒を出すと手で扱きながら、
「だって、あれは一枝ちゃんと話してたから」
と言って少し拗ねたような顔をした。
「それじゃ、面白いことをしてみようか?」
「何ですか?」
「まず、ガウンを前と後ろ逆に着てごらん」
「え?前と後ろを逆?」
「そうだよ。してごらん」
由美は怪訝な顔をしながらも宏一に後ろを向いて立つとガウンを一度脱いでから前と後ろを逆に着た。これで由美は背中から足下まで綺麗に肌を出すことができる。
「それじゃ、俺の膝の上においで、同じ向きで座るんだよ」
「はい」
由美は宏一に支えられながら、膝の上に座った。
「どう?」
「宏一さんの上に座ってるなんて。それに、とってもあったかい」
由美はガウンを開くと宏一と肌が密着することに小さな喜びを見つけた。
「それに、ほら、どう?」
「ああんっ、それを出されるとぉッ」
宏一が両足を軽く開くと、上に乗っている由美の足も一緒に自分の足も開かれてしまった。そして、宏一が足の間に挟んでいた肉棒を解放すると、いきなり肉棒が由美の秘部に当たってきた。宏一はそのままソファをリクライニングの位置にして身体を真っ直ぐに伸ばしていく。
「どう?」
「あん、宏一さんたらぁっ、ちょっと、これは、あんっ、当たってるぅッ」
由美は、宏一の身体が頭が高く足が低くなっているために、斜面に寝ているような感じになったが、一点だけ力強く由美の身体がずり落ちるのを止めているものがあった。それは由美の秘唇を押し分けつつあり、更に中に入ってこようとしていた。
「いや?」
「だって、こんな風にされたら、ああっ」
由美は宏一が軽く腰を突き上げたのでびっくりした。いきなり強い快感がきたのだ。
「由美ちゃんはどうするのかな?」
「あぁぁん、いやぁ、宏一さん、ちゃんと、ちゃんとして下さい」
「ちゃんとってなあに?」
「だって、このままじゃぁ、ああん、前になりたいぃ」
「だぁめ。このままだよ。さっきは由美ちゃんだって自分の好きにしたでしょ?そのお返しだからね」
「だって、あの時はぁ、ああん、腰が落ち着かないぃ」
由美は自分の腰をどこに置いて良いのか分からず、ただジタバタと腰を左右に振ったり前後に動かしたりしたが、それは宏一の肉棒を挑発しただけだった。
「由美ちゃん、いい加減に観念したら?」
「どうすればいいんですか?」
「それは由美ちゃんがよく知ってることだよ」
「・・・・・・・・・・・・」
「知ってるだろう?」
「・・・・・・・・はい・・・・・」
「それじゃ、何て言うの?」
「・・・・・宏一さんのオチンチンを入れて下さい」
「それだけ?」
「あの、・・・私の中にオチンチンを入れて下さい」
「それだけでいいの?」
「え?はい・・・・入れて下さい」
由美はガウンを前後ろ反対に着ているため、由美の背中から足まで宏一の肌をたっぷりと感じることができ、更に二人が2枚のガウンに包まれている格好になるので不思議な安心感を感じていた。だから、自分でも簡単に挿入をおねだりすることができた。
「それじゃ、こうするから入り口を合わせてごらん」
そう言うと宏一は由美の腰を両手で下から引っ張り上げ、由美がそっと入り口を合わせると、今度は逆に由美の身体を下に下ろしていくことで由美の中に入っていった。
「ああぁっ、宏一さん、凄く先っぽが堅い。あん、こんなにおっきかったら入らないぃ、ああぁん、あん、さっきは簡単に入ったのにぃ」
「そうだよ。やっと二人っきりになったからオチンチンだって喜んでるんだ。ちゃんと入れてくれないと・・・・」
「ああん、だって、あぁっ、やっと入った。あああぁぁぁぁ、中に入ってくるぅ」
由美はやっと先端を飲み込むことに成功すると、身体をクネクネと尺取り虫のように動かして身体を宏一の上で下にずらしていった。
「あぁ、ああ、ああん、はぁぁぁぁぁ・・・・」
由美は力強く自分の中に入ってくる肉棒を喜んで受け入れた。しかし、宏一はそれ以上何もしようとしなかった。ただ、肉棒を入れてじっとしているだけだ。
「宏一さん、お願いです。動いて下さい」
「ちゃんと『それだけで良いの?』って聞いたのに『入れて下さい』って言ったろ?だから入れるだけ。さっきは由美ちゃんが自分から動いて上手にいけたでしょ?今度も自分で動いてごらん」
「いやぁ、さっきは特別ですぅ。宏一さぁん」
由美は甘えた声を出して宏一に懇願したが、宏一は動こうとしなかった。由美の肉壁は活発に動いて肉棒を締め上げており、宏一はその動きを楽しむことにしたのだ。それに、2回放出した後なので放出に対する欲求はそれほど強くない。それよりも由美をたっぷりと楽しみたかった。
「由美ちゃん、それじゃ、こうしてあげるね」
そう言うと由美のガウンの中を宏一の手が這い回り始めた。そして、微妙な位置から乳房をからかい始める。由美はガウンの中を宏一の手が這い回るという初めての体験に一気に感じ始めた。
「いやぁぁ、宏一さん、そんな嫌らしいことしちゃ、ダメですぅ」
「セックスって言うのは嫌らしいことをするんだよ」
「それはそうですけど・・・ああん、こんなことされるなんてえっ」
宏一の手は由美の乳房の周りを触り、撫で、敏感に膨らんだ硬い乳房を優しくつついてきた。今日初めてじっくりと乳房を愛される由美は、その感覚に夢中になってしまった。
「宏一さん、お願いです。触るならちゃんと触って下さい」
「それじゃ、おねだりをしてごらん」
「ああん、ここまでしておいてまだ言わせるんですかぁ?あん、ああん、いやぁ、早くおっぱいを揉んで下さい。我慢できません」
「こう?」
「ああぁぁぁぁぁぁーーーーっ、嫌らしいぃぃーーーっ」
「止めた方が良いの?」
「いやぁぁっ、絶対止めちゃダメェーッ」
由美はガウンの中で宏一に乳房を優しく揉まれながら、身体をクネクネと動かして挿入も楽しみ始めた。それは由美の中に埋もれていた女そのものだった。
トップ |