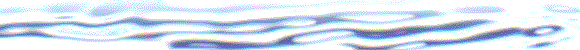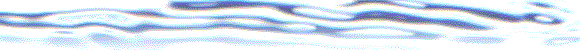
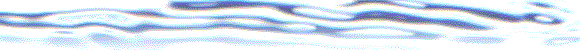
由美は今日のこの夜を特別なものとして記憶したかった。大切な思い出の一つにしたかったのだ。この部屋に泊まるのがいくらするのかは知らないが、安くないのだけはわかる。だから、いくら宏一が大人でお金持ちだとはいっても、宏一にだって特別なはずなのだ。
「制服を着ても良いですか?裸はちょっと・・・」
「うん、いいよ」
「それなら・・・・・・」
「制服を着た由美ちゃんが料理と並んでテーブルに並んでるところ、写真に撮っても良い?」
「写真に?」
「うん、あのテーブルの上に由美ちゃんとまだ残ってるいろいろな料理を並べて写真に撮りたいんだ。きっと綺麗だと思うんだ。でも、その写真の意味が分かるのは俺たち二人だけだよ」
宏一に言われて由美は納得した。裸の写真ではなく制服姿ならそれほど心配することはない。それに、その写真の持つ意味が二人だけの秘密の写真と言うのもうれしい。いい記念になりそうだ。そう思うと由美の胸が高鳴った。
「うわ・・・それって素敵かも・・・・・はい、いいですよ」
「よし、決まりだ」
「それじゃ、簡単にシャワー浴びても良いですか?さっき吹き出しちゃったときにあっちこっちソースとか髪に付いたみたいだし」
「うん、待ってる」
「はい、それじゃ、直ぐに浴びてきますね」
そう言うと由美は裸のまま起き上がると、制服を持ってシャワーブースに向かった。宏一は部屋着姿でテーブルのところに行き、食べ終えた料理の皿を片付け、食べかけの料理や手が着いていない料理を綺麗に並べ始めた。そしてふと思ってガラステーブルの端を見てみると、耐荷重120㎏というシールが見えた。これなら由美が乗っても全然問題なさそうだ。
宏一は安心して料理の並べ替えを進めた。食べかけの皿は上手に集めて一つの料理のように見せ、飲みかけのドリンクは注ぎ直して並べる。
やがて由美が戻って来たときには、宏一が気合いを入れて料理を集めただけあってテーブルの上には新しく注文した料理が届いたかのような綺麗な料理が並んでいた。
「うわぁ、宏一さん、とっても綺麗。さっきまで私が散々食べて散らかしたのに、全然そんなんじゃない。新しく届いたみたい」
「気に入ってもらえて良かった。それじゃ由美ちゃん、ここのスペースに身体を横にしてみて」
「ここ?どうやって?」
「うん、ここに座って、仰向けになってごらん」
「でも・・・・お皿に触りそうで・・・・・よいしょ・・・・こう?」
由美はそうっとテーブルの上に横になって左右の空間を確保した。
「うん、そのまま上を向いて横になるんだ。仰向けだよ」
「はい・・・・・・・・こう?・・・・・どうですか?」
由美は宏一の指示通りに身体を横たえて宏一を見上げた。由美の頭の横にはオレンジジュースがあり、その横には食べかけの海老フライとまだ手の付いていない鯛とホタテのアメリケーヌソースに合わせた皿を並べてある。その横には手の付いていないクラブハウスサンドイッチに由美の食べかけのベジタブルサンドイッチを合せて一盛りにしたものがあり、さらにその横にはチャーハンと五目焼きそばの残り、カツ重や握り寿司を纏めたものを置いた。そして由美の腰の辺りにはケーキとフルーツのデザート類を並べる。
「まだこんなにあるなんて・・・・・でも綺麗」
由美はそう言ったが、さっきまでお腹いっぱいだったのに既に満腹ではなくなっていたので、食べられそうな気もしていた。
「うん、綺麗だよ。それじゃ写真を撮るね」
そう言うと宏一は携帯を設定すると、由美の上半身と料理の写真から撮り始めた。もちろん由美は料理よりだいぶ大きい被写体なので、普通に撮ってしまうと料理が小さくて見栄えがしないので、料理を近くにして由美を向こう側に置くことで写真の中のバランスを取る。由美は宏一が撮影している間、静かにじっとしていたが、だんだん自分も料理の一部になったような気になっていた。
「ちょっと部屋を暗くしてみるね」
そう言うと宏一は部屋の明かりを落とし、テーブルの上のスポットライトだけにする。すると、暗い部屋の中で由美だけがスポットライトを浴びて周りの料理と共に浮き上がり、背景の夜景とのバランスが絶妙な写真が撮れた。
「うん、由美ちゃん、綺麗だよ」
「ちょっと見せて」
「うん、ほら」
宏一が見せると、由美は幻想的な雰囲気の写真に驚いた。それに他の写真も料理と自分の対比が綺麗だ。自分の制服の色は地味だが、料理のカラフルな色合いがそれを補っているので自分がとても綺麗に見える。
「すごい、こんなに見えてるんだ。宏一さん、これ、すごいですよ」
「どう?記念になった?」
「はい、絶対大切にします。誰にも見せないけど、宝物です」
「良かった。少しまぶしいと思うけど、ライトはこのままにしても良い?由美ちゃんがとっても綺麗だから」
「はい・・・良いです・・・・目をつぶるかも知れないけど・・・・・」
「うん、わかった。それじゃ、料理は片側に寄せておこうね」
そう言うと宏一は皿の位置を由美から少し離し、L字のテーブルの横に回り込むと由美の制服の上から優しく撫で回し始めた。由美は目をつぶって静かに任せている。もちろん由美だって写真撮影だけで終わるとは思っていなかった。こうなるのは予想していたことなのだ。
「由美ちゃん、ブラジャー付けてないんだ」
「はい、付けた方が良かったですか?」
「ううん、由美ちゃんはブラジャーを付けなくても胸のラインが綺麗だからね。写真を撮ってるときは気が付かなかったよ」
宏一が言うと由美が目をつぶったまま安心したかのように軽く微笑んだ。宏一は由美の美しさを堪能するために直ぐに裸にはせず、ゆっくりと楽しむつもりだ。制服の上から繊細な愛撫を施していく。
「キスして・・・・」
由美がキスをおねだりしてきたので、宏一はたっぷりと舌を絡め合ってキスを楽しんだ。由美は次第に身体が熱くなり、制服の上からの弱い愛撫では焦れったくなってきたが、さすがにテーブルの上で脱がせてとは言えない。しかし、一定のペースで続く宏一の愛撫に次第に身体は熱を帯び、だんだん我慢できなくなってきた。由美の熱い息が静かな部屋に流れていく。
「宏一さん、ずっとこのままですか?」
「もう少しはこのままだよ」
由美はまだ我慢しなければいけないことにがっかりした。しかし身体は更に焦れったく、敏感になっていく。すると、とうとう両足がグッと擦り合わされた。
「焦れったくなってきた?」
宏一が優しく聞くと、由美はコクンと頷いた。
「ベッドに行きたい?」
「まだ、だいじょうぶです」
「それじゃ、今度はこっちだね」
そう言うと宏一は由美のプリーツスカートの中に手を入れ、中心部へと進んでいく。すると、パンツは穿いておらず、指は直接秘部に到達した。由美の秘唇はねっとりと濡れており、まだそれほどではない。
「あうっ」
由美が反応すると、宏一は由美の秘唇の中に指を入れ、ゆっくりと掻き回していく。
「あ、あ、あ、あ、あ、あ・・・・ああ、あ、あ、あ・・・・・」
由美の小さな口が少し開き、熱い吐息が漏れ始めた。
「気持ちいい・・・・・・」
由美が目をつぶったまま囁いた。
「そのままゆっくり気持ち良くなってごらん」
宏一の声に由美は静かに目を閉じたまま股間の感覚に身を委ねた。指使いが『優しい』と思った。そう、宏一の指使いはいつも優しい。そしてそのまま同じペースで続いていく。だから感じてくると、自然に感覚がそれに合わせて盛り上がっていくので、いつも自分ばかりが夢中になってしまう。『そう言えば、いっちゃんが言ってたっけ・・・・・宏一さんの触り方が一番、あんなに気持ち良くなれるのは宏一さんだけって』
一枝は宏一に抱いて貰ってから自信ができたのか、程なくして彼を作ったのだが、『下手なの。とにかくなんでも強くするから痛くて』と笑っていた。由美は秘唇の中をゆっくりと動き回る宏一の指を感じながら、『いっちゃん、羨ましいでしょ。今、こんなに優しくして貰ってるの』と思った。
宏一は由美が次第に感じていく表情を見下ろしながら、由美の感じ方をコントロールしていた。いきなり強くするのではなく、由美がゆっくりと登っていく最小限の愛撫を与えることで由美の身体を開発していくのだ。
「どう?」
「気持ちいい・・・・とっても・・・・・キスして」
由美が再びキスをねだったので、宏一は更にねっとりと舌を絡めていく。由美は可愛らしい舌を絡めながら息を弾ませ始めた。もちろん、このまま直ぐに絶頂を与えるつもりはない。それくらい由美だって承知しているはずだ。
宏一はスカートから指を抜き去ると、再び制服の上からの愛撫を始めた。
「あん、あ、ああぁぁぁ、こんなことするなんて・・・・」
由美は服の上からの愛撫にも敏感に反応した。両手を上げて制服の胸を差し出すと、宏一の指先が乳首の周りを回る度に両足をグッと閉じて胸の快感を散らす。しかし、乳房は少し放っておかれた間に敏感になっており、だんだん制服が邪魔になってきた。由美は宏一を見上げたが、宏一は優しい眼差しで見下ろしているだけだ。
「おねだりを・・・・・・・」
そこまで言ったが後が続かない。ここでおねだりしてしまえば、後は夢中になってしまうのがわかりきっている。由美は、せめて特別な今日だけはしっかり可愛い子でいようと決心した。
「どうしたの?おねだりしたいの?」
「いえ・・・・・んんん・・・・ん・・んぁぁ・・・んんんっ」
由美は『このまま制服のジッパーを下ろしておっぱいを両手でグッてされたら、どんなに気持ちいいだろう』と思ったが、その想いを封印した。
しかし宏一の愛撫は巧みだ。一定のペースで刺激してくるのに、乳首の近くに来たかと思えば裾野を丁寧になぞり、そして乳首に向かって円を描くように上っていって乳首の近くで離れてしまう。分かっていても焦れったい。
「はぁ、はぁ、はぁ、んんっ、はぁ、はぁ、はぁ、んんああぁぁぁぁ、はぁ、はぁ、はぁ・・・・・」
微かな喘ぎ声が出始めた。
「おねだりしたければ、しても良いんだよ」
宏一の声に、由美はニッコリ笑って首を振った。
「綺麗だよ。由美ちゃん。とっても綺麗だ」
宏一の声に、由美は思わずちょっとだけ『なんて呑気なの』と思ってしまった。
「おっぱいが、少し高くなったかな?」
宏一は突然そう言った。
「確かめてみよう」
そう言うと、制服のリボンの下にあるジッパーをジーッと下げていった。由美はおねだりせずにおっぱいを揉んで貰えるかと思って一瞬喜んだ。しかし、期待は裏切られた。宏一はそっと制服をめくって乳房を覗き込むと、ジッパーを上げてしまった。
「ちょっと高くなってるね。おっぱいも感じてるんだね。嬉しいよ」
そう言って再び愛撫を再開した。
「あああぁぁ、そんなことされたら、我慢できなくなりますぅ」
由美は半分泣きそうな目で宏一を見つめた。
「おねだりしたいの?」
宏一が聞くと、コクンとしてから首を振った。
「したいけど、したくないの?」
由美はコクコクと頷いた。
「わかったよ」
宏一はそう言うと、乳房の愛撫を止めてしまった。由美は心からがっかりした。すると、宏一は由美の足下に回り込み、ソファに座ると由美の腰をグッと引き寄せて足を開いた。膝から下はテーブルからはみ出してだらりと下がる。大きく開いたので茂みが見えそうだ。由美は思わずスカートを押さえた。
「それじゃ、こんどはこっちね」
そう言うとソファに座ったまま由美を引き寄せ、秘部の近くに口を持って行く。熱い息が秘核に掛かり始めた。
「クッ・・・」
由美はスカートを捲り上げると宏一の頭に被せた。しかし、長さが足りないので宏一の頭を隠すことはできなかった。更に宏一は口を秘部の直ぐ近くに持ってくる。由美にはもちろんこれからすることがはっきり分かっていた。
「由美ちゃんをそっと食べちゃうからね」
「こんなところで・・・・・・・」
「そっと食べるからね。動かないで」
そう言うと、ゆっくりと口を近づけていき、熱い息を何度もかけながら舌先で秘核の直ぐ下を少しだけチロチロと舐め始めた。
トップ |