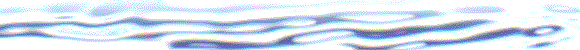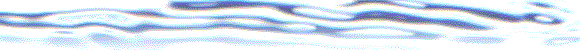
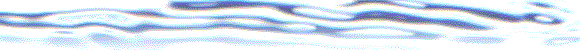
「でも、私が洋恵の紹介で家庭教師を始めたとして、その後で洋恵が新しい彼とうまくいかなかったらどうするの?また先生のところに戻るの?」
さすがに葵は鋭いところを突いてきた。
「そうね。でも、香奈にも言われたの。全力で新しい彼を好きになれって。前の彼がダメだったのは、しょっちゅうセンセに相談したりしてたからだって。もっと相手を真剣に好きになるように努力しろって言われたの。だから私、葵に話してるの。葵なら私の気持ちに整理が付くから」
「そう、そこまで考えてるんだ」
それから二人は当たり障りのない話を少しして別れた。
洋恵は葵について、香奈の言うように身持ちの堅い女の子だと思っていたので、宏一が手を出そうとしても葵が受け入れないだろうと思っていた。だからもし、新しい彼とうまくいかなくなったら、こっそり宏一に会いに行けば必ず優しくしてくれるはずだと思ったのだ。これなら、宏一に優しくして欲しいときに、いつでも会いに行ける。
もともと、宏一に紹介する女の子は宏一を受け入れない女の子であると同時に、結衣よりも魅力のある女の子でなければならなかった。そんな女の子が簡単に見つかるはず無いと思っていたのだが、それが見つかったのだ。洋恵はこのチャンスを逃すつもりは無かった。葵なら結衣より絶対可愛いし、成績だって上のはずだ。
洋恵は葵に結衣のことを言わなかったが、宏一が葵に夢中になって葵を落とそうとすればするほど、結衣のことは忘れていくだろうと思っていた。しかし葵にその気が無いのだから宏一の心は結衣から離れるだけだ。逆説的な言い方だが、宏一の心を結衣から引き離す準備が整ったことで自分は新しい彼を受け入れる準備ができたと思った。
一方、飲み始めた宏一とさとみは乾杯ビールに始まって次々に料理を平らげていくうちに、最初の少しギクシャクした感じは薄れ、次第に打ち解けてきた。そしてさとみは気持ちが楽になったからか、いつの間にか好き勝手にいいたいことを言うようになっており、宏一に我が儘放題になっていた。
「宏一さん、なんか、楽しい」
「うん、俺も楽しくなってきた」
「えぇ?なってきた?それじゃ、最初は楽しくなかったの?」
「だって、最初はさとみさんが夕食だけ誘ってくれた理由がよく分かんなかったから、ちょっと緊張してた」
「それで楽しくなかったの?」
「楽しくなかったって言うより、ちょっと緊張しただけ。さとみさんは緊張してなかったの?」
「全然。だって、宏一さんが夕食に連れてってくれるんだもん」
「それじゃ、ごめんね」
「謝っちゃだめぇ。こんなに楽しいんだからぁ」
「それじゃ、そろそろワインに行く?」
「もう一軒行く」
「えっ?他の店に移るの?」
「魚はもう食べたから。次はお肉の店がいい」
「ありゃ、そりゃ大変。ここには肉もあるのに」
「ううん、移りたい。でもどうして大変なの?」
「だって、空いてるかなぁ?今が一番混む時間だからなぁ」
宏一は慌てて肉の店を探し始めた。しかし、探してみると意外に見つからないものだ。肉料理の店は多いのだが、イタリアンで肉というのは意外に少ない。多くは肉を提供する和風の店なのだ。それでも宏一は何とか見つけると電話をかけ始めた。そして、3軒目でようやく席が取れた。
「よし、良いよ。行こう」
「え?本当に席が取れたの?」
「もちろん。さぁ、肉を食べに行くよ」
宏一はそう言うと伝票を持って席を立った。さとみも慌てて後に続く。実は、さとみは宏一に無理を言って甘えたかっただけだった。困った顔が見たかったのだ。しかし、宏一はきちんと対応してくれた。さとみは『ちょっと我が儘すぎたかな?でも、直ぐにお願いを叶えてくれるなんてやっぱり宏一さんだ』と思った。
「ちょっと歩くよ。新橋じゃなくて有楽町だから」
そう言って歩き始めたが、ちょうどタクシーが通ったのでそのまま乗り込んだ。
「ごめんなさい。急にわがまま言ったりして」
「おやおや、あれだけ勢いよく盛り上がってたのに、急に大人しくなっちゃって」
「だって・・・・・・・」
「直ぐに着くよ。だいじょうぶ。たぶん美味しい」
「うん・・・・」
着いたところは有楽町の駅前で、案内された席はランドマークになっているFUJIYAの大きなネオンの目の前だった。
「うわ、これはインパクト有る」
「そうだね。楽しくなりそうだ」
宏一はそう言うと、すぐに肉料理とワインを注文することにした。
「さとみさんはワインの好みはあるの?」
「ううん、よく分かんないから。あんまり経験無いし」
「それじゃ、肉料理だけど白と赤だと、どっちが好き?」
「肉料理だと赤じゃないの?」
「うん、分かった。それじゃ、両方頼んでみようか」
「両方飲むの?」
「うん、ハーフボトルにして、白と赤と一本ずつ。俺は白も好きなんだ」
「わかったわ」
「肉料理は適当に注文しておくね」
「お任せよ」
宏一はメニューを見ると、素早く数種類の肉料理とワインを注文した。
「ホルモン系も入れておいた」
「イタリアンのホルモン?」
「そう、内臓系だね。ハチノスの煮込みがあったから。トリッパって言うんだ」
「ハチノスってホルモンよね?イタリアンでハチノスだなんて」
「イタリアンは内臓系料理も多いんだよ。フレンチと違ってイタリアンは庶民派料理だからね。きっとさとみさんも気に入ると思うんだ」
「それは楽しみ。で、ねぇ、今度の店は前より静かね」
「うん、二軒目だからと思って、こう言う雰囲気の店にしたんだけど、さっきのみたいに賑やかな方が良かった?」
「ううん、そんなことない。こっちの方がずっと良い。・・・・もう、全部宏一さんに任せちゃおうかな・・・・・」
「うん、さとみさんの好みをもっとよく知りたいし。任せてよ」
「そうじゃなくて・・・・・・・」
「まだお腹は減ってる?肉の入るスペース、有る?」
「たぶん、だいじょうぶ。ねぇ、さっき私、うるさかったでしょ?」
「うるさくはなかったけど、賑やかだったね」
「周りの音に負けないようにって大きな声で話してたら陽気になっちゃって」
「ううん、ストレスがあるときは大きな声を出すのも良いんだよ」
「我が儘だったでしょ?」
「まぁ、ね」
「あのままあの店にいたら、きっともっとワインをがぶ飲みして、きっと宏一さんをホテルに引っ張ってったと思う」
「ええっ?さとみさん、そうなの?」
「たぶん、ね・・・・・でも、宏一さんがこっちに店に連れてきてくれたから」
「そうかぁ、それじゃ店を移らなかった方が良かったかなぁ」
「そんなことは・・・・・。でも、同じだったかも・・・・」
「え?」
「ううん、なんでも無い。部屋の片付けをしていたら、なんだか気が滅入っちゃって、ちょっと発散したかったの。でも、そんなこと言えないでしょ?でも、宏一さんはちゃんと分かってて思いっきり発散させてくれたから」
「発散できた」
「うん、すっごく。だって、あんなに騒いだの、久しぶりだもの」
「それはよかった」
そんな話をしていると、次々に料理が運ばれてきた。さとみは馬肉のグリルには手を付けなかったが、トリッパは気に入ったようだ。
「ハチノスのイタリアンがこんなに美味しいなんて驚き」
「日本と一緒で、徹底的に臭みを取り除いてから丁寧に料理するんだ」
「日本と一緒かぁ。だからイタリアンて人気あるのね」
「そうそう。イタリア人も日本食は好きだって言うしね」
「宏一さん、イタリアは行ったこと無いの?」
「うん、残念ながら。フランスとドイツとスペインだけ。スペインは料理が美味しいよ」
「へぇ、そうなんだ。それじゃ、今度連れてってね」
さとみはそう言いながら、自分から宏一におねだりしていることに驚いていた。
「うん、良いよ。スペイン料理ならタパスって言う小皿料理でお酒を飲むんだけど、味は日本とよく似てるしね。ヨーロッパではイタリアンと同じでタコを食べるし」
「え?ドイツやフランスはタコを食べないの?」
「食べないと思うよ。見たこと無いもの。最もドイツなんかは芋と豆ばっかりで海産物そのものが少ないしね」
「それじゃ、次はスペインね。博多の屋台も素敵だったけど、世界旅行みたいで外国の料理も素敵」
「それじゃ、今日のイタリアンと博多の屋台だったら、どっちが好き?」
「博多の屋台」
「どうして?」
「あの屋台で私は変わったんだもの。本当に素敵だった。私を知らないみんなが私のために乾杯してくれたのよ?こんな素敵なこと、有る?」
「そうだなぁ。確かに。でも、屋台で変わったの?皮焼きじゃなくて?もつ鍋でもなくて?」
「そう。博多の屋台。なんか、私が変わったって自分で思ったもの。あ、私、変わったって」
「そうなんだ。そう言うことって有るんだ」
「私も驚いたけど、確かに変わったの。宏一さんだって分かったでしょ?」
「変わったのが?えっと・・・・・・」
「もう、そう言うこと本人の目の前で言う?」
「ごめん。あ、でも、屋台で飲んだ後、帰る途中の駐車場で・・・・・」
「でしょ?変わったの」
「そうだった。ふうん、博多の屋台か・・・・・。また行こうね」
「うん、絶対連れてって。でも、今はまだダメ」
「どうして?」
「だって、まだ何もできてないもの。引っ越し荷物の片付けだけで寂しくなって音を上げてるのよ」
「寂しくなって・・か・・・・。それは仕方ないと思うよ。それに、何もできてないどころか、新しい一歩を自分で歩き始めてるじゃないの」
「嬉しいこと言ってくれてありがと。でも、どうして仕方ないの?」
「だって、さとみさんはそれまで、結婚するつもりだった人と一緒に暮らしてて、その準備をしてたんだ。結局別れることになったけど、それまでは一人暮らしなんて考えもしなかったでしょ?だからそれまでは結婚に全てが向かってたんだから、新しい一歩で気持ちがまだその環境に慣れてないんだよ」
「それって、慣れの問題なの?」
「そうだよ。単純に慣れの問題」
「気持ちの問題じゃなくて?」
「そりゃ、気持ちだって揺れ動くだろうから、それで辛い思いをするかも知れないけど、それだって一人になれるかどうかの問題だから。辛いとは思うけど、少しずつ確実に慣れてくるからね。もう少しの我慢だよ。人は慣れるのって、意外に早いものなんだ」
「宏一さんたら・・・・・」
話がちょっと重くなったので宏一は話題を変えた。
「ところで、肉に白ワインてどう?」
「うん、すっごくいい。ちょっと驚き。スッキリしてて美味しい」
「そうだろ?俺は真夏にステーキをキンキンに冷やした白ワインで飲むのが好きなんだ」
「それって素敵かも・・・・・私もやりたい」
「そうだね。それも次の課題にしておこう」
「早くしたい」
「うん、分かった。それじゃ、金曜日はどう?」
「金曜日か・・・・・そうね」
「金曜日に都合を付けてくれるなら、だけど」
「都合ならとっくに付いてるのに」
「え?だって検討中って・・・・・・・」
「ちゃんと『前向きに』って言ってあるのに。もしかして本当にまだ検討中だって思ってたの?」
さとみは宏一のばか正直な性格に呆れてしまった。
「ごめん。だって、その気になった後で断られたら悲しいから」
「なんでも先回りして心配りしてくれるのに、そう言うところだけは全然ダメなのね。中学生だって分かることなのに」
「ごめん」
「ううん、今のは私が言い過ぎた。ごめんなさい」
さとみはきちんと頭を下げた。そして次に来たホロホロ鳥の煮込みは宏一に取り分けてくれた。
「これも美味しいわね。ふふふっ、今日はなんか新しい体験ばっかり。そっか、これも自由になったご褒美なのね。きっと寂しさとセットなんだ」
「そうだよ、さとみさん。それが自由って事なんだ。将来が決まってる安心感がない代わりに、何でもできる自由がある」
「よし、それじゃ、自由に乾杯しましょう。白ワインで」
「うん、乾杯」
さとみは寂しさを受け入れた。受け入れても寂しいのは無くならないが、それで良いと思えたのだ。それで心がスッと軽くなった。すると、今度は宏一に甘えたくなってきた。
「ああん、ダメ、楽しすぎてコントロールが利かなくなってきた」
「どうしたの?酔ったの?」
「それもあるけど・・・・・・・今日は食事だけって言ったでしょ?」
「うん、そうだよ。だから二次会は用意してないよ」
「今日は本棚と衣装棚を整理する予定だったの」
「うん」
「でも、嫌になっちゃった。もっと宏一さんと一緒がいい」
「え?だって、自分でやらないと終わらないよ。一人暮らしなんだから」
「そう、だから困ってるの。明日はキッチンをやらないといけないし。金曜日はデートだし」
さとみは悪戯っぽく舌を出して笑った。
トップ |