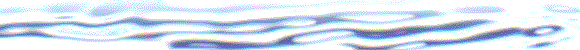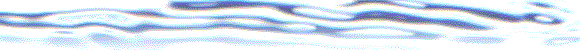
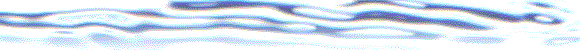
「いいですか?」
「うん、それじゃ、このまま入れてごらん?」
宏一がそう言うと、由美は一度立ち上がって入り口の位置を合わせてから宏一の上に乗ってきた。
「ああっ、くううっ」
由美は難なく肉棒を収めたが、由美の中は既にねっとりと潤いに満ちており、中は既に狭くなっている。
「由美ちゃん、こんなになって・・・・・ずっと我慢してたの?」
宏一の問いには答えず、由美は伸び上がって腰をクイクイと押し付け始めた。
「ああっ、あっ、あっ、奥まで来ましたっ、凄いっ、良いっ、ああっ、ああっ、ああっ」
宏一は左手で由美の腰を引きつけ、右手で左の乳房を揉み上げながら右の乳房を口の中で可愛がっていく。
「ああっ、いきなり全部するなんてっ、ああっ、ああっ、全部いいっ、ああっ、ああんっ、もっとぉっ」
由美は堪めていた思いが一気に噴き出したようで、あっという間に夢中になって駆け上がり始めた。『宏一さんが食べたいのなら・・・・』と思って我慢していた気持ちが一気に噴き上がる。このまま続ければ由美がいってしまうのは明らかだ。由美の中はどんどん狭くなってきている。由美は一気に駆け上がるつもりで自分も腰をグイグイ押し付けてきている。
「ああっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、いっちゃいそうですぅっ」
由美はもう時がないことを宣言した。さっき中断された分を取り戻すつもりなのだ。
しかし、そこで宏一は考えた。このまま由美をいかせてしまえばいつもとあまり変わらないし、後はベッドに行くだけだ。それは確かに楽しいが、それでは二人の思い出にならない。宏一はこの時を二人の思い出としてしっかり刻みつけたかった。もういくことしか頭の中になかった由美とそこが違っていた。そこで宏一は動きを全て止めてしまった。
「あっ、ああん・・・・・宏一さん・・・・ああん、いやぁぁぁ」
「由美ちゃん、まだ朝食が終わってないよね?」
「え?なんのこと?ああんっ、あんっ、どうして・・・・・」
高まったまま中断された由美はクイクイと腰を押し付けて不満そうだ。
「ちゃんと朝ご飯を終わりにしてからベッドに戻ろうね?」
「え?だって・・・・ああんっ」
「まだ食べ終わってないだろう?」
「ああん、だって、あんっ、このまま・・・・あああぁぁぁ、ああぁーっ、ああんっ」
由美は固い肉棒の先端が身体の奥深くを突き上げて肉棒の感覚を確かめた。肉壁が絡み付く快感をもう我慢したくなかった。
「あんっ、ああぁっ、ああんっ、あぁーっ、だってぇっ、ああっ、ああんっ」
じっとしていることができない由美の身体は、勝手に宏一の上で蠢き始めた。自分の動きだけでいこうとしているのだ。
「まだだよ。ほら」
由美の身体が動き始めると、宏一は由美を抱きしめて軽く立ち上がり、腰をひいて肉棒を抜き去ると由美を同じ向きにして後ろから貫いた。乱れていたバスタオルが解けて床に落ちた。
「ああんっ、やぁっ、ああっ・・・・あっ・・・・うしろ?ああぁぁぁんっ」
宏一の上に座って貫かれる格好になった由美は、そのまま腰を突き出して肉棒を一気に奥まで飲み込んだ。しかし、宏一はそれ以上は何もせずに動かない。
「さぁ、まだ朝ご飯が残ってるでしょ?ちゃんと食べてからね」
そう言うと宏一は由美の腰をグッと引き寄せた。
「はうぅっ・・・そんな、無理です。ああん、できません」
由美は既に高まってきているのだ。今更朝食など、どうでも良かった。しかし、宏一は譲らない。
「さぁ、コーヒーを飲んで、パンを食べちゃってね。手は届くでしょ?」
「ああん、後にしましょう。食べたくないぃ」
「だめ、食べなさい」
「ああんっ、こんな格好でぇ、ああんっ、朝ご飯なんてぇ」
由美は嫌がったが、頭の中ではなんとなく分かっていた。宏一はこうやって焦らして楽しんでいるのだ。だから由美も本気で嫌がったりはせず、震える手をコーヒーカップに伸ばした。
「ああん、コーヒーを飲んでパンを食べれば良いんですか?」
「そうだよ」
そう言うと宏一は由美の乳房を両手で包み込んだ。
「はあんっ、だめっ」
由美は敏感になっていた乳房を包まれて声を上げた。身体が反応して、思わずコーヒーカップを落としそうになり、少しこぼしてしまった。
「飲めません。ああぁぁぁ、やっぱりベッドに行きたいですぅ」
「だあめ、ちゃんと飲みなさい」
そう言いながら宏一は由美の固い乳房を優しく揉み上げている。
「ああぁぁ、だめぇ、気持ち良くて、ああん、あああぁぁぁ」
「さぁ、がんばって」
「こんなこと、ああぁぁ、ああんっ、あうぅぅんっ、いやぁぁ」
宏一が譲らないので、由美は快感をなんとか我慢してコーヒーを飲もうと再びコーヒーカップを持ち上げた。
「直ぐに飲みますからぁ、ああぁぁんっ、そんなに乳首を可愛がらないでぇ」
「さぁ、ちゃんとできるかな?」
「裸で朝食なんてぇ、あぁぁぁ、気持ち良くて、ああん」
「そうだよ。二人っきりの朝だからね」
由美は気合いを入れてコーヒーを飲もうとしたが、コーヒーを口の中に入れようとしても気持ち良いのが優先して流し込めない。それでもなんとか口には入れたが、飲み込もうとした時に快感が湧き上がって少し口からこぼしてしまった。
「ンあああぁぁっ、ああああっ、飲めません。やっぱりだめぇ」
「さぁ、もう一度だよ。ちゃんと飲みなさい。パンにも手は届くでしょ?」
「とどくけど、ああんっ、うううっ、んあぁぁっ」
「特別な朝食だよね?」
「特別すぎますぅっ」
由美は宏一のあまりに勝手な言い方に少し腹が立ち、その分だけ快感を押さえ込むことができた。そのまま一気にコーヒーを飲み込み、パンに手を伸ばして口に押し込む。
「んああぁぁ、んあぁぁ、んんんんああぁぁんんあぁん」
由美の声からパンを食べたことが分かった宏一は、ご褒美に両方の乳首を丁寧にコロコロしてやった。
「良い子だ。ご褒美だよ」
「んはあぁぁぁぁぁぁぁっ、んああっぁんんんっ、ふぁっ」
由美は乳首の快感にあわせて無意識に腰を押し付けてしまったので、沸き上がった快感で肉壁が締まって一気に肉棒の快感も与えられ、仰け反って声を上げた時にパンを少し吹き出した。
「んああぁぁ、食べましたからぁ、あああああ、もう許して下さいっ。コーヒーも飲みましたからぁ、もういやぁぁ、我慢なんて絶対ムりぃっ、はぁっ、はぁっ、ああんっ」
由美はきちんと言われたことをしたのだ。それならばご褒美を与えなくてはいけない。
「良い子だ。ご褒美をしてあげるよ。どうして欲しいのかな?」
「どうでも良いから直ぐにしてぇっ」
由美は後ろから貫かれたまま宏一の上で悶えた。もう朝食など頭から消えていた。今は愛されることしか考えられない。
「それじゃ、ソファだね」
そう言うと宏一は由美を貫いたまま立ち上がると肉棒を抜き去り、ソファにどっかりと座ると肉棒をそそり立てた。
「おいで」
宏一の言葉が終わらないうちに由美が吸い寄せられるように宏一の上に乗ってきた。そのまま肉棒を一気に収めると、声を上げて伸び上がって腰を動かし始めた。
「ああっ、ああっ、ああっ、いいっ、ああっ、ああっ、ああっ」
我慢に我慢を重ねただけに、一気に駆け上がっていく。
「良い子だ。最高にしてあげる」
宏一はそう言うと、目の前で声を上げて悶えている由美の乳房を両手で揉み始めた。
「ああんっ、ああっ、ああっ、もう止めちゃいやぁっ、このままぁっ、ああんっ、あっ、あっ、ああっ」
由美は一直線に駆け上がっていく。由美の肉壁がぎゅうぅっと締まってきた。
「ほら、もっとちゃんと入れなさいっ」
宏一は由美の腰をグッと引き寄せて肉棒を更に奥へとねじ込んだ。
「うあぁぁっ、くうぅっ、深いーっ」
肉壁が締まってきてから更に深く肉棒をねじ込まれた由美は仰け反って声を上げた。宏一は由美が仰け反ったことで目の前に差し出された半球形の乳房にパクッと吸い付くと、右手で乳房を揉み込みながら左手で細い腰をグイグイ引きつけ始めた。由美が大好きなやり方だ。
「ああっ、ああっ、ああっ、いいっ、いっちゃいそうっ、ああっ、このままぁっ」
由美は宏一の動きに合わせて自分も腰をクネクネと押し付け、一気に駆け上がった。
「ああっ、いっちゃうぅぅぅ、ああっ、ああっ、きたっ、いっちゃういっちゃうーっ」
由美は声を上げると思い切り仰け反って最高の瞬間をもぎ取った。
「はうぅぅーっ、はうっ、はうっ・・・・・ううっ」
身体で鋭い快感が弾け、由美は宏一の上でビクンビクンと痙攣すると、クネクネと動いていた身体の動きが止まった。
「はっ・・・ううっ・・・・うっ・・・・・・うんっ・・・・うっ・・・・・」
更に何度か由美の身体が痙攣し、快感をたっぷりと身体に満たすとそのまま由美は宏一に抱きついてきた。
「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ・・・・・・」
「どうだった?」
「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ・・・・素敵すぎます、こんなことされたら、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ・・・・」
由美は鈍い感覚の中に、まだ肉棒がしっかりと奥に入っているのを感じながら、宏一に愛される幸せに浸っていた。
「でも、また私だけ・・・・・ごめんなさい」
「大丈夫。とっても気持ち良かったよ。もう少しだったかな?今でもまだ気持ち良いよ」
そう言うと宏一は、由美の身体を再びグッと引きつけて由美の中の感覚を確認した。
「あん、まだだめですぅ。身体がまだ・・・・・もう少し待って・・・・・」
「それじゃ、身体が落ち着いたらベッドに行こうか?」
「はい・・・・・」
由美は宏一の肩に頭を乗せてまだ幸せに満たされている。ゆっくりと身体の感覚が戻ってくるのを感じながら、この幸せな時間が永遠に続けば良いと思った。
宏一は朝の光の中で全裸の由美の身体を楽しめる幸せを噛み締めた。
「ほら、外を見てごらん。飛行機が大分飛ぶようになったよ」
「はい・・・・でも・・・・・」
「どうしたの?」
「ここも素敵だけど・・・・・・外の景色はどうでも良いです」
「そう?」
「はい、宏一さんとこうやっていられるなら、それが一番だから」
「うん、そうだね」
「でも宏一さん、私の身体、もう見慣れてるから嬉しくないでしょ?」
「なんのこと?」
「私の身体をいつも見てるから、少し飽きちゃったかな?って思って・・・」
「それって、俺が上手にできなかったって事?」
「ううん、そんなことない。絶対無いです。でも、いつもしてもらってばっかりだから、宏一さんもきっと飽きちゃうと思って・・・・」
「まだそんなこと言ってるの?由美ちゃん?それって、俺の愛情が足りないって事だよね。もっと由美ちゃんを幸せにしないとだめだね。がんばるから」
「ごめんなさい・・・・私、そう言う意味じゃなくて・・・・・・」
「由美ちゃん、俺が言いたいことは分かってるよね?」
「はい・・・・・分かってます」
「それじゃ、どういうこと?言ってごらん」
「宏一さんは私の身体じゃなくて、私が好きだって・・・」
「そう言うこと」
「ごめんなさい。こうやってると、とっても幸せなんです。だから、この幸せがきっともうすぐ逃げちゃうんじゃないかって思って・・・・だから・・・」
「だから二人で努力し続けないといけないんだよね」
「はい・・・・・・」
二人は繋がったまま、再びたっぷりとキスを楽しんだ。由美の頬に一筋の涙が流れ落ちたが、二人共気にしなかった。気持ちは十分通じていたからだ。
「宏一さん・・・・・・」
キスが終わると由美は宏一をじっと見つめた。
「どうしたの?」
「宏一さんのおちんちんが・・・・・・」
「言ってごらん?」
「また固くなって・・・・・当たってます」
「そうだね、由美ちゃんの中が動き始めたみたいだよ」
「だからかな?身体がまた・・・・・・」
「感じてきた?」
「はい・・・・・ベッドに連れてってください」
「うん、わかった」
由美は立ち上がって肉棒を抜こうとしたが、宏一はそれを制して由美と繋がったまま由美の膝の下に手を入れて腰を抱きしめた。
「しっかり掴まって」
そう言うとそのまま立ち上がる。所謂、駅弁スタイルというやつだ。
「ひゃぁんっ、そんなっ、ああっ」
由美は久しぶりの駅弁に驚いたが、しっかりと宏一に掴まると、繋がったままベッドに運ばれていった。
宏一は由美を抱いたまま、一度ベッドに腰掛けてから仰向けになり、由美を上に乗せたまま身体をずらして正しい位置に横たわった。由美は宏一の上になったままだ。
ただ、宏一はこのまま再開したかったのだが、由美の方はそうではなかった。
「宏一さん、一度抜いてもらっても良いですか?」
「うん、良いよ。どうしたの?疲れた」
宏一が肉棒を抜くと、由美はそのまま身体を宏一に擦りつけて甘えてきた。
「違います。このまましてもらうのも幸せなんだけど、こうやって見たくて・・・、良いですよ。ちょっと甘えたかっただけだから、もう大丈夫。入れても」
由美は宏一の胸に顔をすりすりしながら幸せそうに甘えている。
トップ |