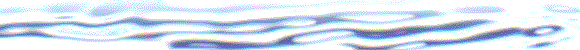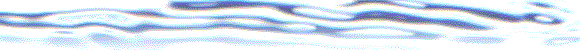
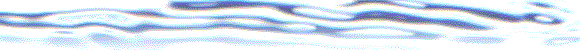
「それなら、いくつ食べられるか記録に挑戦だね」
「普通のお好み焼きでしょ、それから広島風のでしょ、それと・・・・」
「シーフードもチーズも色々あるよ」
「うわぁ、楽しみ」
「それと、由美ちゃんにリクエストしたのは全部届いたって言ったっけ?」
「バッチリです」
由美は勢いよくそう言ってから少し恥ずかしそうに下を向いた。
「どうしたの?」
「宏一さん、喜んでくれるかな?って・・・・」
「それはお好み焼きの後の楽しみだね」
「はい・・・・・」
「明日、結局お父さんは来ることになったの?」
「はい、来ます。お昼は家で食べるって。だから12時くらいかな?」
「いつもそれくらいなの?」
「大体・・・・でも、お昼は食べて来たり来なかったり」
「それじゃ、何時まで居られるの?」
「11時くらい・・・・・・・・」
「お昼の準備は?」
「終わってます。と言っても、うどんですけど」
「お昼を食べたら、お父さんと出かけたりするの?」
「時々は。家にずっと居ることもあるし・・・・・」
「お父さんと病院に行くんでしょ?」
「はい、それは必ず。だから病院の面会時間が終わる前に行かなきゃいけないから、二時くらいには出かけます」
「そのお母さんの病気の様子はどう?少しずつ良くなってるの?」
「最近は、悪くなってないって感じで・・・・でも、ちょっとずつ良くなっているような・・・・・・・。明日、それでお医者さんと話をするんです」
「何か相談?」
「大きな病院に移すかどうか・・・・」
「それは心配だね」
「その方が早く治るみたいなんです。だから・・・・」
「それならその方が良いね」
「でも、それだと遠くなって、今みたいに簡単に面会に行けなくなるから、それが心配で」
「そうなんだ。お母さんにしてみれば、毎日でも由美ちゃんの顔を見たいよね」
「それで明日相談しようって事になってるんです」
「そうか、由美ちゃんはどっちが良いの?」
「早く治るなら、病院を移っても良いかなって」
「やっぱりそれが一番か。そうだよね」
「はい、治ってからもリハビリとかあるみたいだし」
「入院が長引くと体力が落ちるからね。リハビリは結構長く掛かるよ」
そんな話をしているうちに、二人は宏一の部屋に着いた。
「さぁ、入って。なんか恥ずかしいけど」
宏一が招き入れると、由美はキョロキョロと見回しながら入ってきた。
「お邪魔しまぁす。うわ、男の人の部屋だ」
由美は男の部屋に驚いた。別に散らかっているわけでも、汚いわけでもないが、明らかに部屋の中の全てのものの配置が大雑把で、一言で言えば雑だ。ポスター一枚に気を遣ってきっちり貼ってある女の子の部屋ではない。
「散らかってるけど、気にしないでね」
「そんなことないです。きちんとしてます。散らかってる部屋を急いで片付ければ直ぐに分かるもの。宏一さんの部屋はきちんとしてます」
「そう言ってもらえて嬉しいよ」
「でも、女の子の部屋みたいにコーディネートとか全然考えないんですね」
「そうか、女の子の部屋って統一感があるものね。家庭教師してたときに教えてた女の子の部屋なんて、カーテンからベッドカバーなんか全部色が統一してあったなぁ」
その一言に由美は反応した。この部屋に来た最大の目的は他の子の痕跡があるかないか確認することなのだ。由美はさりげなくあちこちを見始めた。
「今、お好み焼きの準備をするからね。そこのちゃぶ台の上で焼こう」
「はい」
由美は取り敢えず、明らかな女の痕跡はないことに安心した。そこで、次のチェックに取りかかった。
「宏一さん、お手洗いを借りても良いですか?」
「あぁ、もちろん。でも、先にシャワーを浴びちゃう?」
「いいんですか?」
「その間に準備をしたいから、そうしてもらえると助かるよ。俺はもうさっき済ませたから」
「はい、それじゃ」
由美はそう言って着替えを持って立ち上がると、浴室に向かった。まだ着替えは普通の着替えで、宏一のリクエストのではない。それはもっと後で着替えるつもりだった。浴室は普通のユニットバスで、バスの中でシャワーを浴びるタイプだ。
宏一はさっきシャワーを浴びたと言っていたが、時間が経っているのか、もう熱気は残っていなかったし、シャンプーの残り香も少しだ。由美はシャンプーのボトルを手に取って匂いを嗅いでみて、残り香と同じであることを確認して安心した。『やだ、私、なんでこんな事してるんだろう』由美は罪悪感を感じた。ただ、取り敢えずこの部屋にいる子の影は無さそうだと思った。
由美がシャワーを終えて髪を軽く乾かしてから出てくると、宏一はちゃぶ台の上にホットプレートとお好み焼きの材料を乗せているところだった。
「もうすぐ準備できるよ」
「うわぁ、なんかすごい。こんなに色々あるんですか?」
「うん、由美ちゃんとお好み焼きなんて考えたら楽しくなっていろいろ買ってきちゃった」
そう言いながら宏一は摺り下ろした山芋をボウルに入れている。
「それは、何ですか?」
「これは山芋。大阪風のお好み焼きには山芋を入れるんだ」
そう言って宏一は見ずに溶いた小麦粉と混ぜている。
「先ずは大阪風の豚玉だね」
「大阪風なんですね」
由美は興味津々だ。
「さぁ、ここに座って」
宏一は由美を座らせると、山芋を混ぜた生地に刻んだキャベツを混ぜ始めた。
「それ、宏一さんが切ったんですか?」
「もちろん」
「こんなに細く切れるんですか」
「良い包丁を使ってるからね」
「良い包丁を使うと、綺麗に細く切れるんですか?」
「やってみる?」
そう言うと宏一はキッチンから包丁をとキャベツとまな板を持ってきて由美の前に置いた。
「切ってごらん?」
由美は恐る恐るという感じで包丁を持つと、少しだけキャベツを切ってみた。
「え・・・あ、すごい、ほとんど切ってる気がしない。スッスッて入ってく」
「そうだろ?良い包丁だと簡単に切れるんだ」
「びっくりしました」
「ま、それはそうとして、ホットプレートのスイッチを入れてよ」
「あ、はい」
「それじゃ、温まるまでちょっと待ってね。その間に、由美ちゃんにはこれ」
そう言うと宏一はサラダを渡した。
「ステキ。綺麗。これ、宏一さんが作ったんですか?」
「ううん、買ってきたものを盛り付けただけ。サラダって意外に手間が掛かるからね。由美ちゃんはいつもどんなサラダを食べるの?シーザーサラダが良いの?それともコブサラダ?」
「えっと、よく分かんなくて」
「これはコブサラダになってるけど、切ったゆで卵が入ってて、野菜が四角く切ってあるだろ?シーザーサラダが良ければブルーチーズ入りのドレッシングもあるよ」
「お任せしても・・・・・良いですか????」
「それじゃ、先ずこれで食べてみてね」
宏一はそう言うと、マヨネーズをサラダの上にかけた。
「はい」
「それと、こっちの方にちょっとだけシーザードレッシングをかけておくね。ちょっと食べてごらん」
「はい」
由美は興味津々でサラダを食べ始めたが、直ぐに角切りの野菜が気に入ったと見えてどんどん食べていく。
「こう言うコロコロした野菜のサラダも美味しいです。それと、こっちのブルーチーズのドレッシングも」
「よかった」
「やっぱり、宏一さんは丁寧に心を込めてくれるんですね。どれも綺麗に大きさが揃ってる」
そう言って由美はニコニコと笑顔で食べ進めていく。
「そろそろ鉄板が温まったかな」
そう言って宏一はお好み焼きの生地を流し込んでいった。
「それじゃ、隣では広島風を作ろう」
そう言うと宏一は生地を薄く鉄板に広げて、山盛りのキャベツを載せてその上に豚肉を乗せた。
「すごい量のキャベツ。広島風って、こうやって作るんですか。作ったの、見たことなくて」
「うん、千切りだから量が多く見えるけど、直ぐにぺったんこになるよ。大阪風より少し手間が掛かるんだけどね」
そう言うと宏一はビールを取り出して由美にノンアルコールカクテルを渡して乾杯した。
「これ、美味しいです。オレンジの香りがとっても良い」
「よかった。ノンアルのスクリュードライバーだからね」
宏一はそう言うとつまみの焼き鳥を食べたり、サラダを食べたりしている。
そうこうしているうちに、最初に作った大阪風の方に火が通ってきた。
「ひっくり返すよ」
「それ、両手でやる奴?えいって?」
「そう、ほうら、えいっ」
宏一は両手に持った小手で上手にひっくり返し、そこにソースを塗って鰹節や青ネギをかけ、マヨネーズとソースで仕上げを始めた。
「うわぁ、おいしそう」
「うん、もう少しだよ」
そう言うと宏一は、今度は広島風の方に少し記事を書けてから両手で裏返し、横で麺を焼き始めた。
「宏一さん、控えめに言っても、すっごく楽しいです」
「ほう、由美ちゃんがそれだけ褒めてくれるなんて、なかなか無いなぁ」
「そんなことないです。いつも褒めてます」
「そうだっけ?」
「そう、昨日だって・・・・・・・」
そこまで言ってから由美は顔が耳まで真っ赤になった。ベッドでの会話と激しくいってしまったことを思い出したのだ。
「まぁ、いいや。それじゃ由美ちゃん、食べてみようか。どっちも豚玉だから、大阪風と広島風の違いを楽しもう」
「早くぅ、食べたいぃ」
うん、それじゃ、広島風は麺の上にお好み焼きを載せて、ソースは当然オタフクソースだね。宏一は手際よく仕上げに入った。由美は皿を持って宏一が取り分けてくれるのを待っている。そして焼き上がった大阪風は宏一がそれぞれを切り分けて由美に渡すと、由美はふぅふぅしながら食べ始めた。
「美味しいっ、宏一さん、美味しいですぅ」
「よかった」
由美は宏一が出してくれるものなのだからきっと美味しいだろうと思ってはいたが、想像以上のおいしさに嬉しい驚きに一気に食べていった。
「大阪風はふっくらとしていてキャベツの甘さが引き立ってるし、何か食感が独特で美味しいです。広島風は焼きそばに少し焦げたところがあって、いろんな食感が楽しめるしキャベツは固まって入ってるから柔らかくて甘くて最高です」
「そうだね、大阪風の方には山芋が入ってるから独特の生地の食感になるよね。でも広島風の方が一口の中でいろいろ同時に楽しめるかもね。それじゃ、次はシーフードで作るよ」
「はい、お願いします」
「大阪風のと広島風のと両方作る?」
「はい、それがいいです」
「わかったよ」
宏一は由美が豚玉を食べている間にシーフードのお好み焼きを作り始めた。その間にも由美はすごい勢いで食べているので、宏一は焼き上がった豚玉を切ったものを何度も由美の皿に追加しなければならず、宏一自身はほとんど食べている時間が無かった。それでも宏一は由美の弾けるような笑顔が見られてとても幸せだった。
そして、シーフードのお好み焼きが焼き上がる頃になって、やっと宏一にも少し時間が出てきた。宏一は3枚目の準備をしてから、やっとビールに手を付けた。
「宏一さんも食べてください。美味しいですよ」
由美は自分の食べる速度に合わせて宏一が準備をしているから宏一が忙しくしていることに気が付いていないのか、真顔で宏一に食べるように進めた。
「うん、そうだね。俺も食べようっと」
そう言うと宏一は残っていた大阪風の豚玉を全部自分の皿に移した。
「ああっ、私の豚玉ぁ」
「あ、ごめんごめん、それじゃ、これは由美ちゃんの分」
そう言って半分を由美の皿に移した。由美はそれに直ぐに箸を付けながら聞いた。
「宏一さん、シーフードは大阪風と広島風で具が違うんですか?」
「うん、どうせならと思って、それぞれ代表的なものを入れて見たんだ。だから大阪風はイカ、タコ、海老の定番にして、広島風はイカと海老に牡蠣を入れたんだよ。本当は広島風にはアナゴを入れたい所なんだけど、東京じゃ簡単には手に入らないからね」
「うわぁ、楽しみですぅ」
「ふふっ、俺はご飯の後の由美ちゃんの下着姿が楽しみだよ」
それを聞いた由美はドキッとして箸を止めた。お腹がいっぱいだとスタイルに影響するかも知れないし、激しく動けないと思ったからだ。由美が心配していることに気が付いた宏一は慌ててフォローした。
「うそうそ、先ずお腹いっぱい食べてよ。お好み焼きだから消化は早いから。デザートを食べてる間にお腹は空いてくるよ」
「いいんですか??本当に?」
トップ |